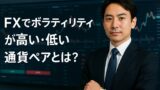「スイスフランショックで爆益を出した人がいるって本当?」「自分も同じようにトレードできたら…」

スイスフランショックは、ほんの数分のうちに為替相場が大きく崩れ、一部のトレーダーに1000万円単位の利益をもたらした一方、多くの投資家が追証や破産に追い込まれました。

本記事では、この極端な相場の中で大儲けすることに成功したトレーダーの具体的なポジション・判断軸・行動環境を紐解き、なぜごく少数の投資家だけが“勝者”となれたのか、その背景と実行力を掘り下げていきます。
- 📌スイスフランショックで大儲けしたトレーダーの戦略がわかる
- 📌成功者に共通する判断軸と資金管理を解説
- 📌急変時に動ける環境の整え方が見える
- 📌今後に活かせる教訓を学べる
スイスフランショックの概要と勝者の背景
スイスフランショックとは何が起きたのか?
こちらの記事でもご紹介した通り、スイスフランショックとは、2015年1月15日にスイス国立銀行(SNB)がユーロスイス(EUR/CHF)の下限1.20を撤廃したことで、為替相場が瞬時に暴落した出来事を指します。
これは、SNBが2011年から維持していた「1ユーロ=1.20フランを下回らせない政策介入」を突如終了したことに起因しています。
この発表は事前の予告もなく行われたため、市場では極めてパニック的な反応が起こりました。
ユーロスイスをはじめとする関連通貨ペアが瞬間的に大幅に下落し、取引が成立しない、約定しない、という異常事態も発生。多くのFX業者でもスプレッドが極端に拡大し、トレーダーの資金が一掃されたほどの影響を及ぼしました。
スイスフランショックは「介入終了の一言が世界の相場を揺るがした」歴史的な事件であり、為替市場のリスク構造を見直す契機となりました。
スイスフランショックは何pips動いたのか?【市場記録】
スイスフランショックでの代表的な通貨ペア、EUR/CHFはわずか数分で約2,300pips、USD/CHFでは1,500pips以上の急落が記録されました。
この規模は通常の1日の変動幅の数十倍にあたります。
以下は、当日の主な通貨ペアの変動幅です。
| 通貨ペア | 変動幅(概算) | コメント |
|---|---|---|
| EUR/CHF | 約2,300pips以上 | 歴史的な1.20防衛撤廃に反応し急落 |
| USD/CHF | 約1,500pips | 米ドル建てでも極端な動きに |
| GBP/CHF | 約2,000pips超 | クロス通貨も巻き込まれて混乱 |
この変動は、リーマンショックやチャイナショックを超えるレベルの瞬間的暴落として記録され、
一時は「為替相場が崩壊した」とすら表現される事態となりました。
ユーロスイスフランが“無限に介入”と呼ばれた理由とは?
2011年から2015年初頭まで、SNB(スイス国立銀行)は「EUR/CHFが1.20を下回らないように無制限に介入する」と明言していました。
これは、ユーロ圏不安が高まる中でスイスフランに資金が集中し、自国経済に打撃が及ぶのを避けるための防衛策でした。
実際には「無限の介入」などは存在しませんが、SNBが“必要な額を上限なく投入する”と表明していたため、
市場では「スイスがフラン高を全力で抑え込んでいる」と受け止められていました。
この前提がある中での突然の撤廃だったため、「絶対に守られる」と信じていた多くの投資家・ファンドがポジションを誤り、逆に大打撃を受けたわけです。
いわばこの出来事は、「中央銀行の約束は永遠ではない」というリスクを世界中に知らしめた瞬間でもありました。
なぜスイスフランは“最強通貨”と呼ばれるのか?
スイスフラン(CHF)は、長年にわたり「安全通貨」として世界の投資家に信頼されてきました。
その背景には以下のような要因があります。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 永世中立国 | 地政学リスクから最も遠い立場にあるとされている |
| 政治・経済の安定 | 財政規律が極めて強く、中央銀行の信認も高い |
| 通貨発行体制の信頼性 | 金準備・国債発行残高の少なさが際立つ |
とくに欧州危機・米国債務上限問題・アジアの政治不安などが起きるたびに、スイスフランには資金が流入し、円と並ぶ“逃避通貨”の役割を果たしてきました。
スイスフランが「最強通貨」と呼ばれるのは、投機的な強さではなく、安定性と信用の極致としての存在だからです。
2025年現在のスイス政策金利は?ショック再来の可能性は?
2025年4月時点でのスイス国立銀行(SNB)の政策金利は1.50%です(※2024年12月の利下げを反映)。
これはユーロ圏よりやや高い水準を保っており、対ユーロでの為替安定化を意識した水準と見られています。
2022〜2023年にかけて続いたインフレ抑制のための利上げ局面から一転、2024年末には世界的な金利調整局面に入り、スイスもそれに追随してやや緩和的な姿勢に転じた形です。
🔍 では、スイスフランショックのような出来事は再び起こり得るのか?
答えとしては「極めて低いがゼロではない」です。
現在、SNBは通貨介入について明確な防衛ラインを設けておらず、為替水準には柔軟姿勢をとっています。
したがって、当時のような「市場との約束を裏切る」ような突然の政策変更は想定されていません。
ですが、万が一の地政学ショックや金融システム危機が起きた際には、スイスフランが再び世界中から“資金の避難先”として注目され、急騰するリスクは常に存在します。
大儲けできたのはどんなポジションを取っていた人か?
スイスフランショックで大きく利益を上げたのは、明確な下向きトレンドを狙ってユーロ売り・フラン買いを持っていたトレーダーたちです。
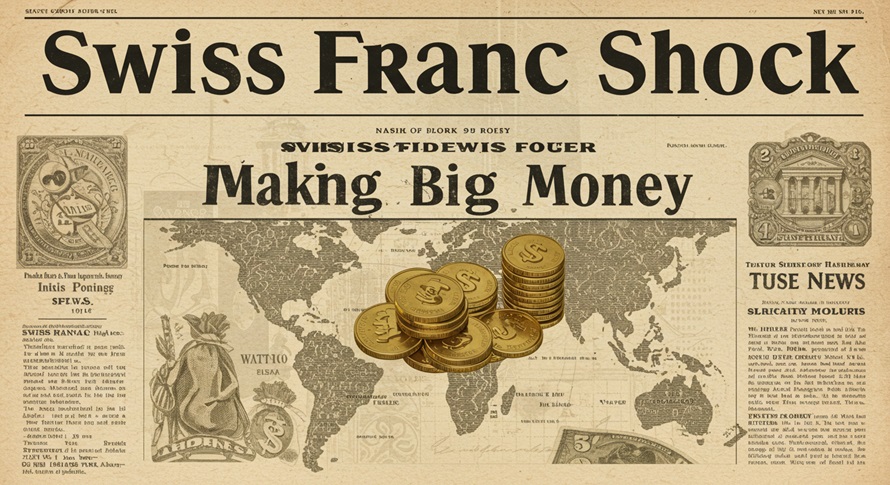
以下は、大儲けできた人々に見られた典型的なポジション例です。
| 戦略タイプ | ポジション内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| ユーロ売り継続型 | EUR/CHFショートを長期保有 | SNB撤廃の可能性を事前想定/リスクヘッジ付き |
| ヘッジファンド型裁定 | 複数通貨で逆張りポジション組成 | 複雑な組合せで機械的対応・資金潤沢 |
| 指標タイミング型 | USD/CHFやGBP/CHFの戻り売り | SNB発表の数十秒後に売り急行/短期決済型 |
中でも最も大きな利益を得たとされるのは、SNBの突然の発表が来る可能性をリスクの一環として織り込み、ポジションを限定的に持っていた短期トレーダー層です。
「動いたら一気に取る。動かなければコスト最小限で撤退」という構えが功を奏した事例です。
“勝者”たちが共通していた判断軸とは?
スイスフランショックで利益を出せたトレーダーに共通するのは、相場の空気を読む直感ではなく、「違和感を見逃さない構造的判断」です。
彼らが実際に重視していた判断軸は以下の通りです。
| 判断軸 | 内容 | なぜ重要だったか |
|---|---|---|
| 中央銀行の発言変化 | SNBが「1.20防衛ライン」への言及を減らしていた | 相場からメッセージが消えたタイミングで違和感を察知 |
| オプション市場の反応 | プットが増加、プレミアムが歪んでいた | 一部機関投資家の先行行動を読み取れた |
| スイス経済の重圧 | 通貨介入による副作用が表面化していた | 継続困難とのシグナルとして反映されていた |
いずれも「確定情報」ではなく、可能性を前提に行動を組み立てていた点が共通しています。
予測というよりも、万が一に備えた準備ができていたかどうかが、成否を分けた最大のポイントでした。
トレーダーの戦略分析と教訓【勝ち筋と再現性】
1日で1000万円超を得た投資家の実例【事後報道ベース】
ショック当日、日本国内外で報道された内容の中には、わずか数分で1000万円超の利益を得た事例もありました。
たとえば、日本の一部ネット証券のインタビューによれば、
→ 直後の暴落で、15分以内に+1200万円の利益を確定。
*その理由として「防衛ラインの撤廃はあり得ると1ヶ月前から予想していた」と語っています。
また、ある機関系トレーダーは、事前にSNB会見予定日をマークし、ポジションサイズを徐々に減らした上で、「スプレッドが拡大しないうちに即座に売りを展開」する自動判断システムを組んでおり、数時間でCHF建てで5桁万円超(数千万円規模)の利益を計上したと報じられています。
これらに共通しているのは、
-
大きなポジションをあえて維持し、爆発を狙ったのではなく、構造の綻びに反応して仕掛けた点
-
結果的に利益が出たが、シナリオが崩れれば即撤退する体制も整えていたことです
相場急変時に対応できる「動ける環境」とは?
相場が数秒で激変するショック相場において、“反応できるかどうか”はトレーダーの戦略以前に、環境面で決まる部分も大きいです。
実際に利益を出したトレーダーが整えていた環境は、以下のようなものでした。
| 環境要素 | 内容 | 成功との関連 |
|---|---|---|
| 約定力の高い業者 | ECN口座・STP方式での約定を利用 | スプレッド拡大・滑りの被害を最小化 |
| 通信回線の高速化 | VPS・光回線などで常時監視状態を構築 | 突発的変動でも注文が通る確率が高まる |
| 分離型ポジション管理 | 本番口座とは別に「仕掛け専用口座」を用意 | 余計な建玉を避け、狙い撃ちに集中できた |
トレード技術だけでなく、「チャンスが来た時に確実に利確できる状態が整っていたか」が勝敗の分かれ目でした。
成功者に共通する資金管理の考え方
スイスフランショックで大儲けできたトレーダーは、運任せのギャンブルではなく、あらかじめ損失に耐えうる資金構造を設計していました。
以下は、実際に報道・証言から見えてきた「勝者の資金管理モデル」です。
| 管理項目 | 成功例での実践 | 狙い |
|---|---|---|
| レバレッジ | 実効5倍未満で制御 | 想定外の逆行時に耐える余力を確保 |
| ロスカットレート | 建玉ごとに個別設定(ATR×2〜3) | 大きな動きへの“揺らぎ”を受け止める幅 |
| 証拠金構成 | メイン+分離口座運用 | 機会損失とリスク管理の両立 |
| ポジション集中度 | 資産の20%以上を一方向に賭けない | 予測の不確実性を前提とする設計 |
ポイントは、「絶対に当たる」という前提ではなく、「外れても死なない」前提での設計にあります。
この守りの仕組みがあったからこそ、結果的に攻めることができたのです。
なぜ多くのトレーダーが動けなかったのか?
一方で、ほとんどのトレーダーはスイスフランショックに対してまったく対応できなかったのが現実です。
それは単なる「予想の外れ」ではなく、動けない要因が複合的に重なっていたことが要因でした。
主な動けなかった理由
-
情報遮断: SNBの発表が想定外のタイミングだったため、情報取得に遅れた
-
指標スケジュールに非注目:「発表すらあると思っていなかった」という油断
-
固定観念:「スイスは約束を守る」「1.20は絶対」が市場心理に根深かった
-
レバレッジ過多: フルレバでユーロロングを抱えていたため、逆行と同時に即死
さらに大きな要因は、「信じて持ち続けた人ほど損をした」という構造です。
ある種の“忠誠心”が裏目に出た典型例とも言えるでしょう。
当時使われていたインジケーターや判断材料とは?
テクニカル的には、スイスフランショック直前に明確な異常サインが出ていたわけではありません。
ですが、経験豊富なトレーダーたちは、いくつかの「違和感の兆候」を感知していたとされています。
参考にされた判断材料の例
| 分類 | 指標・材料 | 解説 |
|---|---|---|
| テクニカル | ATR(平均的な値幅) | ボラティリティが異常に収束していた |
| サポレジ | 1.20の下支えゾーン | フロアラインが異様に“薄く”感じられた |
| ファンダメンタル | SNB発言/市場オーダー情報 | 発言頻度の減少・板の厚み減少に違和感 |
また、一部のプロトレーダーはオプション市場の異常動向(プットオプションの偏り)を手がかりに、「防衛ライン放棄の可能性」に備えてポジション縮小や逆張り準備を進めていたという情報もあります。
ショック相場でトレンドをつかむ3つの着眼点
相場が急変する局面では、「従来のセオリーが通用しない」と感じる場面が多くなります。
ですが、実際にショック相場で勝てたトレーダーは、トレンドの初動を捉える“兆し”に注目していました。
以下は、スイスフランショックのような急変時に有効だった3つの視点です。
| 着眼点 | 説明 | 活用方法 |
|---|---|---|
| 流動性の急減 | 板がスカスカになり始める | 板読みや気配値で異常を察知しやすい |
| ヒゲの異常反復 | 長い上下ヒゲが続出 | 市場が迷っている合図=転換の前兆 |
| “静かすぎる”相場 | 直前まで異様に安定 | 逆に「嵐の前の静けさ」を疑うべき兆候 |
特に「動かない相場」が長く続いた後ほど、トレンドの転換時は鋭角になります。
日頃から“違和感に気づく感覚”を鍛えることが、ショック相場への唯一の備えといえるかもしれません。
高ボラティリティ時代に活きる逆張りと順張りの使い分け
スイスフランショックは、トレンドが一方向に崩壊した特殊な例でしたが、本質的には「順張りで波に乗れるか」「逆張りで反転に備えられるか」の使い分けが成否を分けました。
高ボラ相場での戦略比較
| タイミング | 順張り | 逆張り |
|---|---|---|
| ショック初動 | ◎(大きく利幅が取れる) | ✕(突発に逆らうと危険) |
| ショック中盤 | △(追随リスクあり) | △(判断ミスが命取り) |
| 反転兆候後 | ✕(過去の流れに拘ると危険) | ○(セーフティトリガー重視で反転狙い) |
勝者たちは、初動で順張りに徹し、反転局面で逆張りに転じる「柔軟な切り替え」ができていたことが多いです。
どちらの戦略が優れているかではなく、「相場が求めている行動に即座に対応できるかどうか」がポイントとなります。
今後のスイス相場で同様のチャンスはあり得るか?
2025年4月現在、スイス国立銀行(SNB)は為替への直接介入を行っておらず、かつてのような明確な“防衛ライン”も存在していません。
ですが、以下のような状況下では、類似の急変動が発生する可能性があります。
-
スイスが再び利下げに転じ、他国との金利差が極端に広がった場合
-
ユーロ圏やアメリカで金融ショックが起こり、安全通貨としてCHFが買われ過ぎた場合
-
SNBが「過度なフラン高」を問題視し、再介入を示唆した場合
つまり、相場の背景・政策姿勢・市場の期待が複雑に絡んだ時、かつてのような“極端な動き”が起こる地盤は完全には消えていないということです。
今後もスイスフランを取引対象とするなら、「静かに積み上がる異常サイン」に気づく姿勢が欠かせません。
成功トレーダーたちから学べる再現可能な教訓
スイスフランショックで利益を出せたトレーダーたちは、特別な情報や才能を持っていたわけではありません。
共通していたのは、「備えていた」「想定外に対応できた」という、ごく基本的な行動原則です。
以下は、ショック相場で成功した人たちから得られる再現可能な教訓です。
-
中央銀行の政策発言の“変化”に敏感であれ
→ 内容より「言わなくなったこと」「減ったこと」に注目する -
相場が動かない時間に“何か”を感じ取れるかが分かれ目
→ 静かな相場ほど、大きな変動の予兆を含んでいる -
約定力・情報取得力・通信速度=動ける環境を整えておくこと
→ 準備がない者に、チャンスは“見えていても”取れない -
損失に耐える資金管理を常に前提とせよ
→ 当たったときに爆発する設計より、外れたときに生き残る設計を優先する -
利益は“正解のご褒美”ではなく“対応の成果”である
→ 予測よりも構えの柔軟さが勝敗を分ける
相場で稼ぐ力とは、「情報を知っているか」ではなく「情報にどう構えるか」で決まります。
この原則は、2025年の今も変わることはありません。
よくある質問Q&A10選
Q1:スイスフランショックは何pips下がったのですか?
A:EUR/CHFは約2,300pips、USD/CHFでも1,500pips以上の急落が確認されました。瞬間的に流動性が消えたため、正確な計測が困難な場面もありました。
Q2:スイスの最強通貨といわれる理由は何ですか?
A:永世中立国・経済の安定性・金融政策の信頼性があり、地政学的リスク時に買われやすいため、最強通貨と称されます。
Q3:ショック直前に予兆はありましたか?
A:明確なシグナルは出ていませんでしたが、SNBの発言頻度低下やオプション市場の偏りを感知したプロもいました。
Q4:どうして一部の人だけが大儲けできたのですか?
A:リスクを承知でユーロ売りポジションを維持していたか、異変の兆しに反応して即時対応できたからです。
Q5:今後もショック級の急変動は起こる可能性がありますか?
A:介入の予兆がない現在、再現性は低いですが、金利差・地政学・金融不安によって起こる可能性はゼロではありません。
Q6:2025年現在のスイスの政策金利はいくらですか?
A:2025年4月時点でスイス国立銀行(SNB)の政策金利は1.50%です(2024年末の利下げを反映)。
Q7:今回のようなチャンスを再現するにはどうすればよい?
A:「起きたら動く」だけでなく、「起きるかもしれない」と仮定した戦略設計と環境整備が必要です。
Q8:当時はどの業者を使っていた人が勝ちやすかったのですか?
A:明言は難しいですが、約定力の高いECN系口座や低スリッページ業者が優位でした。
Q9:トレードの勝敗はポジションの方向だけで決まるのですか?
A:いいえ。同じ方向でも、建玉タイミング・決済判断・ロット管理が結果を大きく分けます。
Q10:この記事にあるような戦略はFX初心者にも使えますか?
A:一部の考え方(資金管理・環境整備など)は非常に有効ですが、ショック相場の逆張り投資は高リスクのため経験者向けです。
スイスフランショックで大儲けした人たちの勝者の戦略とは?のまとめ
【あわせて読みたい関連記事】


【本記事の関連ハッシュタグ】