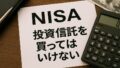本記事は、「iDeCoを始めたら厚生年金が減るのでは?」という疑問や不安に対して、制度の仕組みをわかりやすく解説します。

節税や将来の資産形成に役立つiDeCoですが、その一方で「年金が減る」「損をする」といった誤解も多く見られます。社会保険や年金制度とiDeCoの関係性を正しく理解することで、誤解を解き、不安なく制度を活用する判断ができるようになります。はたして厚生年金に本当に影響はあるのか?その答えを丁寧に紐解いていきます。
-
iDeCoと厚生年金の関係性と誤解されやすいポイント
-
社会保険料や標準報酬月額への影響の有無
-
制度を損なく活用するための注意点と工夫
-
ケース別の活用法と得する人の特徴
- iDeCoと厚生年金の関係を正しく理解しよう
- 誤解を解き、iDeCoを活かすための判断軸
iDeCoと厚生年金の関係を正しく理解しよう
「iDeCoで厚生年金が減る」と言われる理由とは?
iDeCoを始めると「将来の厚生年金が減るかもしれない」と心配する声があります。
この不安の背景にあるのが、「所得控除を受けることで社会保険料が下がり、結果的に将来の年金も減ってしまうのでは?」という誤解です。
確かに、iDeCoは掛金の全額が所得控除となり、課税所得が減る仕組みです。
このことから「所得が下がれば標準報酬月額にも影響が出て、厚生年金が減るのでは?」と不安になるのは自然なことかもしれません。
ですが実際には、iDeCoの掛金は“給与からの控除”ではなく、“個人が拠出した後に税制優遇を受ける”形のため、標準報酬月額や社会保険料には基本的に影響しない仕組みになっています。
つまり、「iDeCoを始めたせいで厚生年金が減る」という心配は、制度を正しく理解すればほぼ根拠のない誤解であることがわかります。
iDeCoと社会保険の仕組みはどうつながっているのか?
iDeCoは「私的年金制度」に位置づけられ、公的年金(厚生年金・国民年金)とは別に運用されるものです。
ただ、誤解が生まれやすいのが、「所得控除によって収入が下がる=年金が減る」という一見つながって見える仕組みの部分です。
ここで整理しておきたいのは、厚生年金の将来受取額を決めるのは“標準報酬月額”と“加入期間”であるという点です。
| 年金の決まり方 | 内容 |
|---|---|
| 標準報酬月額 | 毎月の給与+賞与の平均(税引前)で決まる |
| 加入期間 | 厚生年金に加入していた年数(原則40年で満額) |
つまり、iDeCoによる所得控除はあくまで“課税所得”に対してのものであり、社会保険制度の計算基準には直接影響しません。
この仕組みを正しく押さえておくことで、「なんとなく不安だからiDeCoをやめておく…」という消極的な判断を避けることができます。
所得控除による標準報酬月額への影響はある?
iDeCoによる所得控除が標準報酬月額に直接影響することはほとんどありません。
標準報酬月額は、会社が提出する「報酬月額届」や「賞与支払届」などによって決まり、ここで基準になるのはあくまで「額面の給与・賞与」です。
つまり、控除後の“手取り”ではなく、“支給額ベース”で判断されます。
| 判断される項目 | iDeCoの影響有無 |
|---|---|
| 支給総額(額面給与) | 影響なし |
| 健康保険・厚生年金の保険料 | 影響なし |
| 源泉徴収・住民税の金額 | 控除がある分軽減 |
ただし、企業によっては「給与天引きでのiDeCo加入」を認めているケースもあります。
その場合、控除前の支給額ではなく、すでに掛金を差し引いた金額を報酬月額と誤認して処理されてしまうケースも、わずかながら報告されています。
そのため、給与天引き型のiDeCoを導入している企業に勤めている場合は、
-
社会保険の算定基礎届の内容に誤りがないか
-
iDeCo掛金が報酬に含まれている扱いになっているか
ということを人事・労務部門に確認するのが確実です。
とはいえ、正しい運用がされていれば、iDeCoが標準報酬月額や厚生年金の将来額を減らす要因にはなりません。
厚生年金が減るケースと減らないケースの違い
iDeCoの加入によって厚生年金が実際に“減る”ケースは、非常に限定的です。
ですが、制度の運用や収入の変化によって、間接的な影響が出る可能性がゼロとは言えません。
ここで「減るケース」「減らないケース」を明確に分けて見てみましょう。
減らないケース(大多数)
-
iDeCoを自分で拠出している(給与からの天引きではない)
-
勤務先の給与明細上で、iDeCoが給与額に含まれて報告されている
-
標準報酬月額の届出に誤りがない
→ この場合、標準報酬月額は正しく維持され、将来の厚生年金には影響なし
減る可能性があるケース(まれ)
-
給与天引きでiDeCoに加入しており、天引き後の額で報酬月額を申告してしまっている
-
転職・退職によって給与が一時的に下がり、それが標準報酬月額に反映された
-
勘違いや事務処理ミスで、iDeCo拠出額が“手取り減”ではなく“収入減”と誤解された処理
→ こうしたケースでは、結果として厚生年金の計算基準が下がり、将来の受給額が若干少なくなることがあります。
このように、正しい手続きと理解があれば、「厚生年金が減る」というリスクは制度上ほとんど存在しないといえます。
心配な方は、給与明細や標準報酬月額の確認をおすすめします。
公的年金と私的年金の関係性を整理しておこう
年金制度は「3階建て構造」で設計されています。
| 階層 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 1階:国民年金 | 基礎年金(全国民対象) | 全員 |
| 2階:厚生年金 | 報酬比例(会社員など) | 被用者(会社員・公務員) |
| 3階:私的年金 | iDeCo・企業年金など | 任意加入(個人選択) |
iDeCoはこのうちの「3階部分」にあたる、自分の意志で積み立てる私的年金です。
つまり、「将来の収入を補完するために作られた制度」であり、1階・2階の公的年金制度とは性質が異なります。
たとえば、厚生年金は収入に比例して将来の年金額が決まりますが、iDeCoは「拠出額 × 運用結果」で将来の受取額が変わる、完全に自己責任の積立制度です。
この違いを理解していないと、「iDeCoを始めたら厚生年金が減るかも」という誤解につながります。
あくまで両者は独立した制度であり、iDeCoは公的年金を“減らす”のではなく“補う”仕組みであると理解しておきましょう。
給与からのiDeCo拠出は社会保険料に影響する?
iDeCoの掛金は、原則として本人の銀行口座から引き落とされる形で拠出します。
この場合、給与からは差し引かれないため、社会保険料や厚生年金の計算に影響を与えることはありません。
ですが、一部の企業では「給与天引き方式」でのiDeCo拠出を導入していることがあります。
この場合は、以下の2パターンが考えられます。
正しく処理されている場合(安心)
-
給与明細上、iDeCoは「任意控除」として処理
-
社会保険の算定対象には“天引き前の給与”が報告されている
→ 問題なし。厚生年金の標準報酬月額に影響なし。
間違って処理されている場合(注意)
-
iDeCo天引き後の金額を報酬月額として申告
-
社会保険料・厚生年金の算定対象が下がってしまう
→ 結果的に将来の厚生年金が微減する可能性がある。
このように、企業の処理方法によってごくまれに影響が出ることがあるため、「給与天引きされている人」は人事担当への確認が推奨されます。
退職金や年金受取時にも“控除の仕組み”がある
iDeCoの大きな特徴のひとつが、掛金だけでなく「受け取り時」にも税制上のメリットがあることです。
具体的には、受け取るときに「退職所得控除」または「公的年金等控除」が適用されます。
一時金として受け取る場合
・ iDeCo加入年数も加算対象
年金形式で受け取る場合
このように、受け取り時にも控除の仕組みがあるため、課税対象額が少なくなり、手取りが増える可能性があります。
つまり、iDeCoは「始める時・積み立てている間・受け取るとき」の3段階すべてで税制優遇が受けられる“超優遇制度”といえるのです。
厚生年金との関係においても、この控除の仕組みを理解していれば、受取総額で損をする可能性は極めて低いといえるでしょう。
所得が下がると将来の年金額が減るは本当か?
「所得控除を受けて課税所得が減ると、厚生年金も減ってしまうのでは?」という不安は根強くあります。
ですが、前述のとおり、厚生年金の将来受給額を決定するのは標準報酬月額(額面給与)と加入期間であり、課税所得の多寡は関係ありません。
つまり、iDeCoによって所得控除があったとしても、“税金は軽くなるが、年金の計算には影響しない”というのが正しい理解です。
注意すべきなのは、「iDeCoによる控除ではなく、実際に収入が減った場合(転職・減給など)」です。
この場合は標準報酬月額が下がり、厚生年金の受取額も減る可能性があります。
ただし、これはiDeCoに限った話ではなく、あらゆる給与変動に共通するルールです。
iDeCo特有のリスクと考える必要はありません。
自営業と会社員で影響の出方は違うのか?
iDeCoは、自営業者(第1号被保険者)と会社員・公務員(第2号被保険者)とで制度の設計や上限額に違いがあります。
| 区分 | 掛金の上限額(月額) | 社会保険との関係 |
|---|---|---|
| 自営業 | 68,000円 | 国民年金のみ(基礎年金) |
| 会社員 | 12,000〜23,000円 | 厚生年金+企業年金等あり |
この違いにより、iDeCoが社会保険や将来の年金に与える影響にも若干の違いがあります。
-
自営業の場合
・そもそも厚生年金に加入していないため、iDeCoが「公的年金の代わり」としての役割を持つ
・標準報酬月額のような概念がないので、控除による影響もなし -
会社員の場合
・厚生年金との併用。拠出方法や企業の処理次第で影響の有無が変わる
・ 控除そのものは制度上影響しないが、処理ミスには注意
このように、iDeCoが厚生年金に与える影響は「制度の使い方」ではなく「職種や拠出の仕方」で違ってくるのが実態です。
制度の本来の目的と“損得”の誤解に注意
最後に強調したいのは、iDeCoの目的は「公的年金を削る」ことではなく「補う」ことにあるという点です。
制度の主な目的は以下のとおりです。
-
公的年金だけでは足りない将来資金を補完する
-
自助努力による資産形成を促す
-
国全体として“持続可能な年金制度”を支える
にもかかわらず、「厚生年金が減るなら損」と短絡的に考えてしまうと、本来得られるはずの節税効果や運用メリットを失うことになりかねません。
iDeCoは節税と資産形成が同時にできる制度であり、活用次第で将来の経済的不安を軽減する強力なツールです。
「一時的な不安」ではなく、「仕組みの理解」をもとに判断することが、後悔のない選択につながるでしょう。
誤解を解き、iDeCoを活かすための判断軸
iDeCoのメリットとリスクを正しく整理しよう
iDeCoは節税効果が大きく、将来の資産形成にもつながる“優遇制度”として知られています。
ただし、メリットだけを強調されることも多く、リスク面までしっかり把握しておくことが大切です。
【iDeCoの主なメリット】
-
掛金が全額所得控除 → 所得税・住民税が軽減
-
運用益が非課税 → 長期投資に有利
-
受取時にも退職所得控除や年金控除あり
-
自分の資産を自分でコントロールできる
【iDeCoの主なリスク・注意点】
-
原則60歳まで引き出せない(流動性が低い)
-
元本保証型でない商品も多い(運用損の可能性)
-
加入期間や拠出額によって受取額が変わる
-
口座管理手数料が毎月発生する
iDeCoは「制度として非常に優れている」反面、資金拘束や運用リスクなど、事前に知っておきたいポイントも多いのが実態です。
だからこそ、“理解したうえで”活用することが何より重要です。
年金だけでは足りない現実とiDeCoの役割
公的年金(国民年金+厚生年金)は、老後の基礎的な生活費を支える制度ですが、現実にはそれだけでは生活が苦しくなるケースも少なくありません。
たとえば厚生労働省の「老後生活費調査」によると、夫婦世帯で必要とされる生活費の平均は月約27万円。
一方、年金の平均受給額は夫婦合計で月20万円前後にとどまります。
| 老後生活費の目安 | 約27万円/月(夫婦) |
|---|---|
| 公的年金の平均支給額 | 約20万円/月(夫婦) |
| 月々の不足額(平均) | 約7万円 |
この“足りない部分”をどう補うかが、多くの人にとっての課題です。
そこで重要なのが、iDeCoのような「自分で準備できる年金制度」です。
-
税制優遇を受けながら将来資金を積み立て
-
長期運用で増やす可能性を確保
-
公的年金では届かない部分を“自力で補う”
という設計は、今後の“人生100年時代”を生き抜くうえでますます欠かせないものになるでしょう。
将来の受取額より“可処分所得”で考える視点
「iDeCoを使うと厚生年金が減る?」という議論の背景には、“将来の年金額”だけで損得を考えてしまう傾向があります。
ですが、より現実的なのは、“今と将来の可処分所得(使えるお金)をトータルで見る”という考え方です。
iDeCoの最大の強みは、掛金が全額所得控除されるため、今すぐに税負担が減る=手取りが増えるという点にあります。
たとえば、年収500万円の人が月2万円を拠出した場合、年間で約5〜6万円の節税効果があります。
| 項目 | 金額例(目安) |
|---|---|
| iDeCo拠出額(月) | 20,000円 |
| 年間拠出額 | 240,000円 |
| 年間節税額(概算) | 約50,000〜60,000円 |
「老後の年金額が若干減るかも」と悩むよりも、“今使えるお金が増える+将来も年金的に受け取れる”という視点で考えると、より合理的な判断ができます。
企業型DCとの違いと併用の注意点
近年では、企業が導入している「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と、個人で加入する「iDeCo(個人型DC)」の併用が可能になりました。
ただし、併用にはいくつかの制約があるため、制度の違いと注意点をしっかり理解しておく必要があります。
| 項目 | iDeCo(個人型) | 企業型DC(会社が導入) |
|---|---|---|
| 拠出者 | 本人 | 会社(+本人がマッチング拠出可) |
| 掛金の上限 | 職業・加入状況で異なる | 会社規定による |
| 併用可能性 | 要件を満たせば可能 | 勤務先の就業規則に依存 |
| 制限・注意点 | 登録事業所かどうか、同時加入かなどを確認 |
企業型DCがある場合、iDeCoの掛金上限は月12,000円に制限されることがあります。
また、企業型DC側で「個人型DCとの併用を認めていない」場合もあります。
そのため、併用したいと考えている方は、まず勤務先の就業規則や人事部門に確認することが第一歩です。
厚生年金とのバランスを考えた運用設計とは?
iDeCoを活用する際に大切なのは、厚生年金を“減らさないように避ける”ことではなく、“うまく補完する”設計を考えることです。
厚生年金は、収入に応じて将来の給付額が決まる“報酬比例”型の制度です。
一方、iDeCoは積立額と運用成果によって将来の受取額が変わる“積立・運用型”の制度です。
両者のバランスを取るには、以下の視点が有効です。
たとえば、iDeCo内で債券型や元本確保型商品を一定割合含めることで、リスクを抑えながら厚生年金とのバランスを取りやすくなります。
重要なのは、「厚生年金の代わり」ではなく「補完役」としての設計を意識することです。
途中でやめたくなったときの対処法は?
iDeCoは原則60歳まで引き出しができない制度のため、「途中でやめられない」という不安の声もあります。
実際には、以下のような“やめる”の代わりになる対応策があります。
掛金の停止(拠出の中断)
-
一時的に掛金を止めることは可能(最短1か月〜)
-
停止中も資産はそのまま運用継続
-
停止手続きは運営管理機関を通じて簡単に可能
転職・退職後の継続
-
自営業や無職になってもiDeCo口座は維持可能
-
国民年金加入状況に応じて掛金上限が変更される
60歳前の解約は原則不可
-
原則、途中解約や引き出しは不可
-
例外は「障害状態になった場合」や「受給資格の喪失」など
このように、「絶対に60歳まで続けなければならない」わけではなく、柔軟にペースを調整する選択肢もあることを知っておきましょう。
受取方法によって税金のかかり方が変わる?
iDeCoで積み立てた資産は、60歳以降に「一時金」または「年金形式」で受け取ることができます。
そしてこの受取方法によって、税制上の扱いも変わってきます。
| 受取方法 | 適用される控除 | 税制メリット |
|---|---|---|
| 一時金受取 | 退職所得控除 | 所得の1/2を控除対象にできる場合あり |
| 年金形式受取 | 公的年金等控除 | 年金額に応じた控除で課税軽減可能 |
どちらの方法にもメリットはありますが、以下のように使い分けるとよいでしょう。
いずれの場合も、受取時に「税金がかかるから損」という考えではなく、税制優遇を活かした設計を意識することで、手取りを最大化することが可能です。
年金額を減らさずにiDeCoを活用するコツ
ここまでの内容をふまえ、「厚生年金を減らさず、iDeCoのメリットを最大限に活かす」ための実践的なコツをまとめておきます。
-
iDeCoは“課税所得”に影響するだけで、標準報酬月額には影響しないと理解しておく
-
会社で給与天引きをしている場合は、報酬月額が正しく報告されているかを確認
-
iDeCoの拠出額は無理なく続けられる金額から設定(後から変更も可)
-
定期的に資産配分の見直しや商品変更を行うことでリスクコントロール
-
受け取り方(年金 or 一時金)は、将来の収入や控除枠をもとにシミュレーション
制度に対する誤解や不安を抱えたままでは、せっかくのチャンスを見送ってしまう可能性があります。
仕組みを理解し、事前に確認すべき点を押さえておけば、「厚生年金も守りつつ、自分の老後資金も育てる」ことは十分可能です。
本当に得するのはどんな人?ケース別に解説
iDeCoは「誰にでも得な制度」と言われることもありますが、実際には職業・収入・税率・家族構成などによって向き不向きがあります。
ここでは代表的なケース別に「得しやすい人」の特徴を見ていきましょう。
年収500万円以上の会社員(扶養控除なし)
-
所得税率が高いため、所得控除による節税効果が大きい
-
掛金の上限(月2.3万円)を活用することで、年間で数万円以上の節税も
自営業者(国民年金の第1号被保険者)
-
掛金の上限が月6.8万円と高く、積極的な老後資金づくりが可能
-
公的年金が基礎年金のみなので、iDeCoの活用価値が特に高い
転職予定・フリーランス転向予定の人
-
転職や独立後も口座が継続可能
-
上限額や掛金を柔軟に変更できるため、ライフステージに合った使い方ができる
退職金が少ない予定の人
-
受取時に一時金を選ぶと、退職所得控除をフル活用して非課税で受け取れる可能性あり
iDeCoは、所得のある現役世代にとってはほぼ例外なく“活用メリットが大きい制度”です。
ただし、制度の恩恵を最大化するには、自分の状況に合った設計と受け取り戦略が重要です。
よくある質問Q&A10選
Q1. iDeCoを始めると厚生年金が本当に減るんですか?
A. いいえ、原則としてiDeCoの拠出は課税所得を減らすものであり、厚生年金の計算に使われる「標準報酬月額」には影響しません。
Q2. iDeCoを始めると社会保険料も下がるって聞いたのですが本当ですか?
A. 誤解されがちですが、iDeCoの掛金は社会保険料の計算対象には含まれません。社会保険料は「標準報酬月額(額面給与)」に基づいて計算されるため、iDeCoによる所得控除があっても保険料や将来の厚生年金額に影響は基本的にありません。
Q3. 給与天引きでiDeCoを拠出しているけど大丈夫?
A. 基本的には問題ありませんが、報酬月額の届出内容に誤りがないか、念のため会社に確認しましょう。
Q4. iDeCoはやめたい時に途中解約できますか?
A. 原則不可です。ただし、掛金の停止は可能で、資産はそのまま運用されます。
Q5. iDeCoで損するケースってありますか?
A. 運用損失が出た場合や、短期間で使うお金を誤って拠出した場合にはデメリットになり得ます。
Q6. 自営業と会社員では、iDeCoの使い方はどう違いますか?
A. 自営業は上限額が高く、年金補完としての役割がより重要。会社員は厚生年金の上乗せとして使います。
Q7. 企業型DCがあるとiDeCoは使えないの?
A. 併用は可能ですが、会社の規定や拠出限度額に制限があるため、事前に確認が必要です。
Q8. 将来の受け取りは一時金と年金、どちらが得ですか?
A. 所得状況や他の退職金・年金収入によって異なります。控除枠を踏まえてシミュレーションが必要です。
Q9. 節税額ってどれくらい変わるものですか?
A. 年収や税率によりますが、月2万円の掛金で年間5万円以上の節税になることもあります。
Q10. iDeCoとNISA、どっちを先に始めたらいいですか?
A. 流動性を重視するならNISA、長期の老後資金づくりを優先するならiDeCoが適しています。
iDeCoで厚生年金は減るのか?誤解されがちな仕組みを徹底解説!のまとめ
最後にこの記事のポイントをまとめました。
【あわせて読みたい関連記事】



【本記事の関連ハッシュタグ】