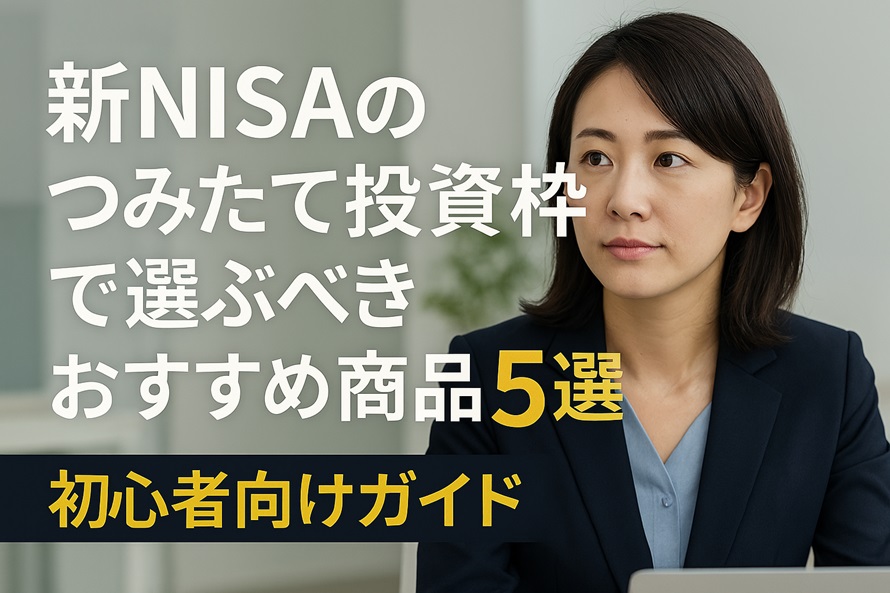本記事では、新NISA制度における「つみたて投資枠」でどの商品を選ぶべきか悩んでいる方に、2025年時点でのおすすめファンドと選び方の判断基準を詳しく解説していきます。

新NISAでは制度の非課税枠を最大限活用することが将来の資産形成に直結しますが、ただ人気という理由だけで商品を選ぶと、想定よりも成果が伸びないケースも少なくありません。長期にわたって安心して積み立てを続けるための視点を具体例とともに整理しましたので、ぜひ参考にされて下さい。
-
新NISAのつみたて投資枠で失敗しない選び方がわかる
-
長期運用に向いたおすすめ商品の特徴を整理
-
人気商品のリスクと正しい見極め方を理解
-
自分に合うファンドを選ぶ判断基準を持てる
つみたて投資枠の選び方と基本ポイント
つみたて投資枠とは?成長投資枠との違いを押さえる
つみたて投資枠を上手に活用するには、まず「どのような目的で設計された制度なのか」を正しく理解しておくことが不可欠です。
制度そのものはシンプルですが、使い方を誤ると本来の強みを活かせないまま終わってしまいます。
つみたて投資枠は、新NISAの中でも「長期・分散・積立」の3要素に特化した非課税制度です。
対象商品は、金融庁の条件を満たした信託報酬が低く、資産クラスが分散されている投資信託に限定されており、毎月一定額を淡々と積み上げる設計になっています。
これに対して成長投資枠は、個別株・ETF・一部の投資信託など商品選択の自由度が高い分、短期〜中期の戦略的な使い方も可能です。
【比較視点】“積立スタイル”から見た制度の設計思想
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 投資手法の前提 | 毎月定額積立を自動で継続 | 好きなタイミングで自由に売買 |
| 投資対象の選定ルール | 金融庁が定めた基準を満たす投資信託のみ | 上場株式・ETF・REIT・指定インデックス投信など |
| 想定される運用スタイル | 長期安定成長・リスク分散志向 | 資産形成+資金活用・リターン最大化型 |
| 初心者への適合性 | 高い(設計が明快で放置しやすい) | 中〜上級者向け(判断と調整が必要) |
投資に慣れていない方にとっては、自由度よりも「制限のある仕組み」の方が安全に使えるという事実があります。
つみたて投資枠は、まさにその代表例であり、「自動で・低コストで・長く続けられる仕組み」として、初心者が最初に選ぶべき制度として設計されているのです。
新NISAの非課税メリットはどこまで影響するか?
つみたて投資枠の最大の魅力は、運用益にかかる税金が一切発生しないことです。
この「非課税」という特性が、長期での資産形成にどれほどの差を生むかを数値で見ると、その重要性が実感できます。
通常、投資信託や株式で得た利益には約20.315%の税金がかかります。これは、100万円の利益が出た場合に20万円以上が税金で差し引かれるという意味です。
ですが、新NISAの枠内で得た利益は、どれだけ増えても課税されることは一切ありません。
課税口座とNISA口座の20年間運用での違い(5万円×12ヶ月×20年)
| 項目 | 課税口座 | 新NISA(非課税) |
|---|---|---|
| 元本(20年間積立) | 1,200,000円 × 20年 = 240万円 | 同左 |
| 年利5%での最終資産 | 約405万円 | 約405万円 |
| 税金(利益分165万円) | 約33.5万円 | 0円 |
| 実質手元に残る金額 | 約371.5万円 | 約405万円 |
上記のように、最終的に約30万円以上の差が出るにもかかわらず、多くの人はこの「見えない差」に気づかず、普通口座や課税口座で積立を続けてしまうケースもあります。
また、この“非課税効果”は、リスクのある値動きに対する心理的な安心材料にもなるという副次的なメリットもあります。
仮に値上がり益が出ても、売却時に税金が差し引かれる心配がないため、「利益確定のタイミングを逃す」ようなストレスも減るのです。
少額からでも、非課税の恩恵を受けながらコツコツ積立できるという点で、つみたて投資枠は初心者が最初に選ぶ制度として非常に理にかなっています。
特に将来の資金計画が漠然としている段階では、「いつ解約しても税金がかからない」という安心感が、長期運用の継続につながります。
初心者が避けるべき“なんとなく投資”の危うさ
つみたて投資枠は、制度として非常に安全性が高く、誰でも始めやすい仕組みになっています。
ですがその一方で、「選ぶハードルが低い」ことがかえってリスクを見逃す原因になることもあります。
特に初心者に多いのが、「ランキング上位だから」「YouTubeで勧めていたから」など、根拠の薄い理由で商品を選んでしまうパターンです。
つみたて投資枠で選べる商品は数百本以上あり、そのすべてが“非課税対象”ではあるものの、内容・リスク・運用成績には大きな差があります。
「どれでも似たようなもの」と思ってしまうと、長期で積立を続けるなかで大きな後悔に繋がる可能性があります。
初心者が陥りがちな“なんとなく選び”の例
| 選び方の例 | 一見魅力的だが… |
|---|---|
| SNSやブログで評判が良かった | 一時的な人気であり、長期運用に不向きな場合も |
| リターンが高いものを選んだ | 高リターン=高リスクで、値動きに耐えられないことも |
| 金融機関のおすすめに従った | 営業目的の商品提案で、手数料が高いケースもある |
とくに「数年後に流行が終わって償還された」「高リスク商品に振り回された」といったケースは、これまで実際に数多く起きています。
つみたて投資枠は制度としては安心ですが、選ぶ商品次第では積立自体がストレスや不安の元になることを忘れてはいけません。
商品選びの基本は、
-
自分のリスク許容度を把握すること
-
長期視点で“継続しやすい内容”かを見極めること
-
手数料などのコスト面も冷静に比較すること
この3点を守るだけでも、つみたて投資枠の効果を最大限に引き出すことができます。
「安心して10年以上続けられるか?」という視点で、必ず一度立ち止まって選ぶことが大切です。
積立に向いている投資信託の特徴とは?
つみたて投資枠を活用するうえで、どの商品を選ぶかは成果に直結します。
制度上は金融庁が厳選した「積立向き」の投資信託に限定されていますが、その中でも実際に“続けやすく成果が出やすい”商品を選ぶには、見るべきポイントがあります。
共通するのは、コストが低く、分散性が高く、運用実績が安定していること。
どれか1つでも欠けていると、積立投資の強みである「時間を味方につける力」が弱まってしまいます。
積立に向いている投資信託の3条件
| 特徴 | なぜ重要か |
|---|---|
| 信託報酬が低い | 長期になるほどコスト差が運用成績に直結する |
| 資産がグローバルに分散されている | 単一市場の影響を受けにくく、安定成長が期待できる |
| 長期で安定した運用実績 | “将来も積立を続けられる”という信頼感につながる |
たとえば、同じ全世界株式型インデックスファンドでも、信託報酬が0.1%台のものと0.5%を超えるものでは、20年後の資産額が数十万円以上変わることもあります。
また、新興国株に偏ったり、日本株の比率が極端に高い投信は、短期では魅力的でも、国際的な分散が効かないことでリスクが高まりやすい傾向があります。
さらに、投信によっては設定から日が浅く、長期の実績データが確認できない場合もあります。
そういった商品は、制度の非課税期間をフルに活かすという観点からすると不確実性が高く、慎重な判断が求められます。
つみたて投資枠を活かすには、「見た目の成績」よりも“いかに長く安心して続けられるか”という視点が重要です。
選ぶべき投信は、あなたの資産を「ゆっくり、確実に育ててくれるパートナー」かどうかで判断するのが成功への近道です。
販売会社よりも信託報酬に注目すべき理由
つみたて投資枠の商品を選ぶ際、どの金融機関で買うかよりも重要なのが「信託報酬」です。
これは投資信託の運用にかかる年間の手数料で、同じような商品でも、このコスト差が20年後の資産額に大きく影響するためです。
販売会社(証券会社や銀行など)は、あくまで“投資信託を売っている窓口”に過ぎません。
どこで買っても運用中の中身は同じでも、コストは商品ごとに固定されているため、「どの投信を選ぶか」がすべてを決めると言っても過言ではありません。
信託報酬0.1%の差が生む20年後の資産の違い(年利5%、月3万円積立)
| 信託報酬 | 最終資産額(20年後) | 差額 |
|---|---|---|
| 年0.1% | 約1,228万円 | ― |
| 年0.3% | 約1,192万円 | ▲36万円 |
| 年0.5% | 約1,158万円 | ▲70万円 |
※すべて同じ利回り・積立条件での比較
多くの初心者が「証券会社のおすすめ」や「口座開設時の特典」で商品を選んでしまいがちですが、それは本質的な判断軸ではありません。
選ぶべき基準は“商品そのものの維持コスト”=信託報酬です。
たとえば、ある証券会社で勧められた投信が年0.6%、一方で別の証券会社で扱っている同種のインデックスファンドが年0.1%であった場合、同じ運用成果でも、コストによる資産目減りが明確に差となって現れます。
つみたて投資は長期で続けるほど、見えないコストの積み重ねが最終リターンを左右します。
そのため、どこで買うかよりも、何を買うか、どれだけ低コストか──この視点で選ぶことが、本当に賢い制度活用の第一歩です。
インデックス型とアクティブ型の違いと選び方
つみたて投資枠を利用する際、「インデックス型」と「アクティブ型」のどちらを選ぶべきか迷う人は少なくありません。
どちらにもメリットはありますが、長期・低コスト・安定運用を重視する場合は、インデックス型の方が基本的に相性が良いというのが実情です。
インデックス型は、日経平均やS&P500といった特定の指数に連動する運用を目指すファンドです。
一方でアクティブ型は、指数を上回る成果を狙って、ファンドマネージャーが銘柄を積極的に選定・運用します。
インデックス型とアクティブ型の比較(積立に向くかどうか)
| 項目 | インデックス型 | アクティブ型 |
|---|---|---|
| 運用の目的 | 指数と同じ動きを目指す | 指数を上回るリターンを目指す |
| コスト(信託報酬) | 年0.1%台が中心 | 年0.5〜1.5%以上と高めが多い |
| 成果の安定性 | 市場と連動して長期的に安定しやすい | ファンドごとに差が大きく、波も激しい |
| 積立との相性 | 非常に高い | 商品選びを間違えると継続困難になることも |
つみたて投資において重視すべきは、「コストが低く、継続しやすいかどうか」です。
アクティブ型の中にも優れた実績を持つファンドは存在しますが、運用方針が変わったり、途中で償還されたりと、積立を続ける上での“継続リスク”が付きまといます。
特に初心者にとっては、パフォーマンスの波に一喜一憂しやすく、途中で積立をやめてしまう原因にもなりかねません。
一方、インデックス型は運用内容が明快で、心理的にも続けやすいというメリットがあります。
「どちらが優れているか」ではなく、「積立に向いているのはどちらか」という視点で判断することが大切です。
迷ったときは、まずインデックス型で基礎を固めてから、必要に応じてアクティブ型を検討する──この順番が現実的な選び方と言えるでしょう。
リスク分散を意識した商品の見分け方
つみたて投資枠で商品を選ぶ際に見落とされがちなのが、「リスク分散」の観点です。
どれだけ人気がある商品でも、特定の資産や地域に偏っている場合、想定外の下落に巻き込まれるリスクが高くなります。
リスク分散とは、資産(株式・債券・不動産など)や地域(日本・先進国・新興国)をバランスよく組み合わせることで、一つの市場が下がっても全体の価値を守る構造を作ることです。
これが、長期積立において“ブレにくい資産形成”を実現する鍵となります。
リスク分散が効いている vs 効いていない商品例
| 商品の特徴 | リスク分散の評価 |
|---|---|
| 米国株100%型インデックス | △ 地域集中(1国依存) |
| 新興国株集中型ファンド | △ 成長性はあるが値動きが荒い |
| 全世界株式型インデックス | ◎ 地域・資産の分散が広い |
| バランス型(株式+債券) | ◎ 資産クラスの組み合わせが良い |
「米国株が強いから米国一本で良い」といった考え方は、一見合理的に見えますが、為替・政策・経済変動といった外的要因に強く左右されやすくなります。
特に、為替が円高方向に動く局面では、ドル建て資産の価値が目減りすることもあり、収益が出ているのに実質利益が出ていないという状況に陥るケースもあります。
一方で、全世界株型やバランス型は、市場の成長に連動しながら、どこか一部の下落を他の資産で吸収する仕組みがあるため、安定性に優れています。
これは、長期で投資を続けるうえで心理的な安定にもつながります。
長期運用に強い“信頼できる運用実績”の見方
つみたて投資枠では、長期間積み立てていくことが前提となるため、商品の「過去の実績」が信頼できるかどうかが非常に重要な判断材料になります。
単に直近の成績が良いというだけではなく、安定して成果を出してきた背景や市場との関係性を読み取る視点が求められます。
特に注目すべきは、「設定来リターン」「シャープレシオ」「純資産の推移」といった継続性と信頼性を示す指標です。
これらを見ることで、一時的な好成績ではなく、長期的に積立に適しているかどうかが見えてきます。
信頼できる運用実績を見抜く3つのチェックポイント
| チェック項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 設定来の運用年数 | 少なくとも5年以上の実績があるか |
| 運用成績の安定度 | 毎年のリターンが極端にブレていないか |
| 純資産の推移 | 年々増加しており、資金流出が発生していないか |
例えば、過去10年間のリターンがプラスだったとしても、途中で大きくマイナスになった年が何度もあるファンドは、長期で積み立てるには不安定な傾向があります。
一方、全体のリターンは中庸でも、毎年安定して3〜7%前後のリターンが出ているようなファンドは、積立との相性が良く、続けやすい商品といえます。
また、純資産の増減にも注意が必要です。長期で積立する場合、資金の流出が続いているファンドは運用が縮小・終了するリスクがあり、突然の償還に巻き込まれる恐れもあります。
長期運用を前提とするなら、「派手な成績」より「着実な成長」に着目することが大切です。
実績の裏にある継続性と運用規模の安定性を冷静に見極めることで、10年後、20年後も安心して積立を続けられる土台が築けます。
ネット証券と銀行、つみたて投資に向いているのはどっち?
つみたて投資枠を活用する際、多くの人が最初に迷うのが「どこで始めるか」という選択です。
銀行の窓口で申し込む安心感を取るか、それともネット証券の利便性を優先するか。
この選択が将来の運用成果に与える影響は想像以上に大きく、特につみたて投資では“選ぶ金融機関”がコストや使いやすさに直結します。
結論からいえば、つみたて投資を長期で効率よく続けたいなら、ネット証券の方が圧倒的に向いているのが現実です。
ネット証券と銀行の比較(つみたて投資との相性)
| 比較項目 | ネット証券 | 銀行(店舗型) |
|---|---|---|
| 取扱商品の豊富さ | 数百本以上 | 数十本程度に限定されがち |
| 手数料・信託報酬 | 業界最低水準の商品が多い | 比較的高コストな商品が多い |
| 手続きのしやすさ | スマホやPCで完結、反映も早い | 窓口での対面、時間がかかる |
| 情報の透明性 | 自分で比較・選定しやすい | 銀行側の推奨商品に偏りがち |
特に銀行では、投資信託の選択肢が限られていたり、手数料の高いアクティブ型投信が中心になっていることも多く、長期の積立には不利な条件がそろってしまいがちです。
一方、ネット証券では数百本の中から選べるうえ、信託報酬の低い優良ファンドが豊富に揃っており、コスト面でも選択肢の広さでも明確な差があります。
さらに、積立設定や変更・停止がスマホで完結する点も、運用の柔軟性という意味で非常に重要です。
生活の変化に応じてすぐに対応できることは、長期で投資を継続するうえで大きな安心材料になります。
安心感を求めて銀行を選ぶのもひとつの考え方ですが、費用・商品選択・利便性すべての面で見たとき、ネット証券の方が“積立という目的”にはよりフィットしているのが事実です。
迷ったときは、まずネット証券での口座開設から検討することをおすすめします。
2025年版!つみたて投資枠で選ぶべきおすすめ商品5選
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の魅力
つみたて投資枠で最初に検討すべき代表的な商品が、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」です。
その最大の魅力は、1本で世界中の株式に分散投資ができることにあります。
地域配分や銘柄選びを自分で調整する必要がなく、初心者でも手軽に“地球全体に投資”できる設計が評価されています。
この1本で投資できる地域の割合(2025年3月末時点)
| 地域 | 比率(目安) |
|---|---|
| 米国 | 約60% |
| 日本 | 約6% |
| 欧州 | 約15% |
| 新興国 | 約10% |
| その他 | 約9% |
※MSCI ACWI(オール・カントリー・インデックス)に連動
eMAXIS Slimシリーズは、信託報酬が最安水準に設定されており、長期投資におけるコスト負担を限界まで抑えている点でも高い評価を受けています。
中でもオールカントリーは、米国に偏りすぎず、それでいて日本や新興国もバランスよく含むため、リスク分散の観点でも理想的な構成といえます。
また、投資信託の中でも純資産が1兆円を超えており、資金の流入が安定しているため、途中償還や繰上げのリスクが非常に低いことも安心材料です。
個別の国や地域を選ぶ必要がなく、すでに全世界に分散されている構造のため、「どこに投資すべきか悩みたくない」「王道で失敗したくない」方にとっては、非常に使いやすい“長期積立の基盤商品”となるでしょう。
オルカンは長期的な運用に向いたファンドですが、一時的な価格下落に不安を感じる方も少なくありません。→ オールカントリーが下落する主な理由と今後の対処法はこちらの記事で詳しく解説しています。
SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの強み
つみたて投資枠で安定した成長を目指すなら、「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」も非常に有力な選択肢です。
この商品は、アメリカの代表的な株価指数であるS&P500に連動する運用を目指しており、米国経済の成長にそのまま乗る形で資産形成が進められるのが最大の特長です。
S&P500の過去20年の年平均リターン(2004〜2023年)
| 年数 | 年平均リターン(税引前) |
|---|---|
| 20年間平均 | 約8.9% |
| 最良年 | +32.4%(2013年) |
| 最悪年 | -18.1%(2022年) |
※為替・手数料は含まず(出典:Bloomberg)
このファンドは、バンガード社の米国ETF(VOO)を実質的に運用対象としているため、世界的に評価の高い米国ETFの恩恵を受けながら、日本円で気軽に積立できるのがポイントです。
さらに、SBI証券グループによって提供されていることもあり、信託報酬は0.09%台と最低水準を維持しています。
米国の株式市場は、IT・ヘルスケア・金融・消費など世界をリードする企業群で構成されており、
「成長力に集中投資したい」「リターンを重視したい」人にとっては、インデックス型商品の中でも非常に魅力的な選択肢となります。
ただし、米国偏重であることから為替の影響を受けやすく、リスク分散の観点では全世界型に比べてやや偏りがある点は念頭に置くべきです。
とはいえ、成長期待と実績の高さは非常に魅力的で、特に中長期で資産を増やしたい方には候補の一角として強く推奨できる一本です。
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドの特長
つみたて投資枠で「全世界株に投資したいけれど、コストも使い勝手も重視したい」という方には、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」も有力な選択肢です。
この商品は、eMAXIS Slim全世界株式と同様に、全世界の株式市場にまとめて投資できる設計となっており、分散性と継続性のバランスに優れています。
最大の特徴は、楽天証券ユーザーに特化した運用設計とポイント連携のしやすさです。
楽天ポイントを使って積立ができるだけでなく、楽天キャッシュとの連携により、ポイント還元+自動積立の仕組みを簡単に構築できるのが強みです。
全世界株式ファンドの2大主力比較
| 項目 | 楽天・オールカントリー | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|---|
| 運用対象インデックス | FTSEグローバル・オールキャップ指数 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス |
| 信託報酬(年率・税込) | 約0.0561%(2025年3月時点) | 約0.1133% |
| 購入方法の柔軟性 | 楽天ポイント・楽天キャッシュ対応 | 一般的なクレカ積立・現金積立 |
| 設定来純資産残高の増加ペース | 急速に成長中 | 安定して高水準 |
FTSEグローバル・オールキャップは、より小型株も含めた分散が効いており、構成銘柄の幅広さが魅力です。
そのうえ、信託報酬が2025年現在で0.06%を下回る水準まで下がっている点は、コスト重視の長期投資において非常に有利です。
一方で、純資産の規模や運用実績の蓄積はeMAXIS Slimに軍配が上がるため、「より分散された指標で運用したい」「楽天経済圏の活用で積立効率を高めたい」といった人にとっては、本商品は相性の良い選択肢になります。
ニッセイ外国株式インデックスファンドの評価
つみたて投資枠で“日本を除く先進国株式”に集中して投資したい方にとって、「ニッセイ外国株式インデックスファンド」は非常に安定した選択肢です。
このファンドは、MSCIコクサイ・インデックスに連動し、米国・欧州を中心とした先進国市場へ広く分散投資できる構造となっています。
特に注目すべきは、長期運用の実績と圧倒的なコスト競争力です。
投資対象国と構成比率(2025年3月末時点)
| 国・地域 | 構成比率(目安) |
|---|---|
| 米国 | 約70% |
| イギリス | 約6% |
| フランス | 約4% |
| カナダ | 約3% |
| その他先進国 | 約17% |
※MSCIコクサイ指数に基づく構成
このファンドの魅力は、信託報酬が年0.09%台という最低水準に抑えられている点に加え、すでに運用実績が10年を超えており、純資産残高も7,000億円超と安定性が非常に高いことです。
また、全世界株型ファンドとは異なり、日本市場を含まないことで、よりグローバルな分散効果が得られるという側面もあります。
日本株を別で保有している人にとっては、このファンドを使うことでポートフォリオ全体の偏りを是正する役割も果たせます。
「全世界よりも先進国に重点を置いた戦略を取りたい」
そんな方にとって、ニッセイ外国株式インデックスファンドは堅実で実績ある一本として、ポートフォリオの中核を担う選択肢となるでしょう。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスのポテンシャル
「多少のリスクがあっても、将来の成長力に賭けたい」という方に適しているのが、「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」です。
このファンドは、アメリカのNASDAQ100指数に連動し、Apple・Microsoft・Amazon・NVIDIAといった世界を代表するテック銘柄に集中的に投資できる設計になっています。
ハイリスク・ハイリターンの特性を理解した上で活用すれば、資産の成長を加速させるための“攻めの1本”として非常に有効です。
NASDAQ100のセクター別構成(2025年3月末時点)
| セクター | 構成比率(概算) |
|---|---|
| 情報技術 | 約55% |
| 通信サービス | 約15% |
| 一般消費財 | 約12% |
| ヘルスケア・その他 | 約18% |
※代表銘柄:Apple、NVIDIA、Meta、Amazon、Google など
このファンドは、楽天・eMAXISシリーズのような全世界分散型と異なり、米国の成長企業に集中投資するスタイルです。
特に、ここ10年で最も成長したセクターであるIT・通信関連に重きを置いているため、市場が好調な局面では驚くほどのリターンが狙えます。
過去5年間(2019〜2023)の平均リターンは年率約16%と高く、積立でコツコツ買い増すことで、高値掴みのリスクを抑えつつパフォーマンスを享受できるのも特徴です。
一方で、値動きが激しくなる局面もあり、短期での下落耐性が問われる場面では継続が難しく感じることもあるため、つみたての軸にするのではなく、一部に組み込んで“成長アクセント”として使うのが現実的な活用法です。
初心者が避けるべき“人気だけで選ぶ”落とし穴
つみたて投資枠で最も多い失敗のひとつが、「なんとなく人気だから」という理由だけで商品を選んでしまうことです。
金融庁の基準を満たしているとはいえ、すべての商品が“万人にとって最適”なわけではありません。
人気=自分に合っているとは限らないという点を見落とすと、期待していた成果が得られず、積立を途中でやめてしまうリスクもあります。
人気だけで選んだ商品が合わないと感じやすい理由
| よくある選び方 | ありがちな結果例 |
|---|---|
| SNSで話題になっていた | 値動きが激しくて不安になり継続できない |
| ランキング1位だった | コストが高めで長期的に差が広がる |
| 有名人がおすすめしていた | 自分の投資目的や期間とは噛み合っていない |
たとえば、SNSで話題のファンドを選んだ結果、「思ったよりも値動きが激しく、積立をやめたくなった」という声は少なくありません。
また、成績が良い商品でも信託報酬が高ければ、長期的に見ると数十万円単位で成果に差が出ることもあります。
自分に合った商品を選ぶためには、以下の3点を重視することが重要です。
-
リスク許容度に見合っているか
-
投資期間と運用方針が一致しているか
-
継続しやすいコスト水準か
人気や評判をきっかけに商品を知るのは悪いことではありませんが、最終的な判断は「自分にとって続けやすいかどうか」で下すべきです。
情報の熱量に流されず、冷静な基準を持つことが、後悔しない選択へとつながります。
よくある質問Q&A10選
Q1. つみたて投資枠で最も人気のある商品はどれですか?
A. 「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」が最も多くの投資家から選ばれており、分散性・低コスト・安定性の3拍子がそろっています。
Q2. つみたて投資枠のおすすめ商品は人によって違いますか?
A. はい。年齢・収入・投資経験によってリスク許容度が異なるため、「万人に最適な1本」は存在しません。自分に合った商品を選ぶことが大切です。
Q3. 人気上位のファンドだけを選んでも大丈夫ですか?
A. 必ずしも安全とは言えません。信託報酬が高い場合や値動きが大きい商品も含まれるため、構成内容やコスト面も確認する必要があります。
Q4. つみたて投資枠は全世界株式と米国株式のどちらを選ぶべきですか?
A. 分散重視なら全世界株式、成長性重視なら米国株式が選ばれる傾向です。どちらも一長一短なので、自分の投資方針と照らし合わせて判断しましょう。
Q5. NASDAQ100に連動する商品は初心者に向いていますか?
A. 値動きが激しいため、積立を続けられるメンタルがある人には向いていますが、不安を感じやすい方には不向きです。ポートフォリオの一部に取り入れるのが現実的です。
Q6. つみたて投資枠ではリスクの高い商品も選べますか?
A. 金融庁の厳選基準により極端なハイリスク商品は除外されていますが、NASDAQ100型のようなボラティリティの高い商品も含まれています。
Q7. 投資初心者におすすめの商品はありますか?
A. はい、eMAXIS Slim 全世界株式や楽天・オールカントリーなど、分散性が高くコストが低いインデックスファンドが推奨されます。
Q8. つみたて投資枠で商品を途中で変更することは可能ですか?
A. 可能です。ただし変更後も同じつみたて枠を使い続けるため、過去の運用結果はそのまま残り、新たに買い直すことにはなりません。
Q9. 年間投資額が少ない場合、どの商品から始めればよいですか?
A. 少額でも長期で効果が出る「全世界株式」や「先進国株式」タイプから始めるのが理にかなっています。1,000円単位で積立可能な商品も多数あります。
Q10. つみたて投資枠の商品は途中で償還されることはありますか?
A. 基本的に少額投資非課税制度に対応した商品は償還リスクが低いですが、純資産の減少やファンド統合により終了する可能性はゼロではありません。純資産の推移は確認しましょう。
新NISAのつみたて投資枠で選ぶべきおすすめ商品5選!初心者向けガイドのまとめ
最後にこの記事のポイントをまとめました。
【あわせて読みたい関連記事】



【本記事の関連ハッシュタグ】