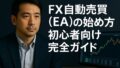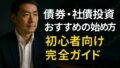「投資信託とETFってどう違うの?」「初心者にはどっちがいいの?」
これから資産運用を始めようとする方が必ず一度は抱く疑問です。
どちらも少額から始められて分散投資ができる商品ですが、仕組み・取引方法・コスト・活用場面には明確な違いがあります。特に、積立NISAやiDeCoなどの制度を使う際には、それぞれの特徴を理解しておくことが非常に重要です。

本記事では、2025年時点の最新情報をもとに、投資信託とETFの違い・選び方・おすすめ商品・活用法までを初心者にもわかりやすく解説。これから資産形成をスタートする方が、自分に合った方法を見つけられるよう、体系的にガイドします。
- 📌投資信託とETFの違いがひと目でわかる
- 📌初心者に向いているのはどちらかが判断できる
- 📌目的別に選ぶおすすめ商品がわかる
- 📌制度(NISA・iDeCo)との相性も整理されている
投資信託とETFの違いを徹底比較
投資信託とは?仕組みとメリット・デメリット
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を一つのファンドとしてまとめ、専門の運用会社が株式や債券などの複数の資産に分散投資する金融商品です。
個人投資家は、少額からでもプロの運用成果を享受できる点が魅力です。
📌メリット
-
✅少額から始められる:100円から投資可能な商品もあり、初心者に最適です。
-
✅自動積立が可能:定期的な積立で、長期的な資産形成がしやすくなります。
-
✅分散投資が容易:1つの商品で複数の資産に投資でき、リスク分散が図れます。
-
✅NISAやiDeCoに対応:税制優遇制度との相性が良く、非課税での運用が可能です。
📌デメリット
-
❌リアルタイムでの売買ができない:注文から約定までタイムラグがあり、即時の取引は不可です。
-
❌信託報酬が比較的高め:運用管理費用がETFより高い傾向があります。
-
❌分配金の仕組みが複雑:普通分配金と特別分配金があり、税制面での理解が必要です。
特に分配金については、以下の記事で詳しく解説しています。
投資信託の安全性については、【投資信託ランキング×安全性】初心者が選ぶべき2025年の安定商品は?を参考にされて下さい。
ETFとは?上場投資信託の特徴を解説
ETF(上場投資信託)は、証券取引所に上場されており、株式と同様にリアルタイムで売買できる投資信託です。
インデックスに連動する商品が多く、低コストでの運用が可能です。
📌メリット
-
✅リアルタイム取引が可能:市場の動きに合わせて即時の売買ができます。
-
✅信託報酬が低い:インデックス連動型が多く、運用コストが抑えられます。
-
✅透明性が高い:保有資産の構成が公開されており、投資先が明確です。
-
✅分配金の受け取りが可能:定期的に分配金が支払われる商品もあります。
📌デメリット
-
❌ 少額投資が難しい:1口単位での購入となり、投資額が高くなる場合があります。
-
❌ 自動積立が困難:証券会社によっては積立サービスに対応していないことがあります。
-
❌ 分配金の再投資が手動:分配金の再投資を自動で行う仕組みがない場合があります。
金ETFと金の投資信託の違いについては、「金の投資信託はおすすめしない?金ETFとの違いを徹底比較!」で詳しく解説していますので参考にされて下さい。
両者の違いを一覧表で比較
投資信託とETFは、どちらも「投資家から資金を集めて運用する商品」ですが、購入方法やコスト、柔軟性に大きな違いがあります。
下表にて両者の主な違いを整理します。
| 比較項目 | 投資信託 | ETF(上場投資信託) |
|---|---|---|
| 購入方法 | 証券会社や銀行経由、基準価額で1日1回 | 証券取引所で市場価格にて売買可能 |
| 売買タイミング | リアルタイムでない(タイムラグあり) | 株式同様にリアルタイムで売買可能 |
| 最低投資額 | 数百円~(100円積立対応も多数) | 数千円~(1口単位での購入) |
| 手数料・信託報酬 | やや高めなものが多い | 比較的低コストな商品が多い |
| 分配金の再投資 | 自動(特定口座内) | 手動の場合が多い |
| 積立サービス | 対応(毎月自動積立など) | 非対応が多い |
| NISA対応 | ◎(積立NISAとの相性も良好) | 〇(成長投資枠で利用可) |
| 流動性・透明性 | 比較的低い | 高い(保有資産も随時開示) |
➡️ 「少額・自動積立・初心者向き」は投資信託、「コスト・柔軟性・上級者向き」はETFが一般的な選び方です。
取引コストや信託報酬の違いとは?
コスト面での比較は、投資信託とETFの選び方に大きな影響を与える重要なポイントです。
ここでは「信託報酬」「売買手数料」「スプレッド」などの視点で整理します。
📌信託報酬(運用管理費)
-
投資信託:年率0.3~1.5%程度が一般的
-
ETF:インデックス型なら0.1%以下の商品も多数あり
➡️ 同じインデックスに連動する商品でも、ETFの方が低コストになりやすい傾向があります。
📌売買時の手数料
-
投資信託:ノーロード(購入手数料0円)商品が多い一方、一部で信託財産留保額がかかる場合あり
-
ETF:株式と同様に売買手数料が発生(証券会社ごとに異なる)
➡️ 頻繁に売買するならETFの手数料に注意が必要です。
📌スプレッド(売値と買値の差)
-
ETFには流動性の低い銘柄でスプレッドが大きくなるリスクがあります。
→ 小型ETFや海外ETFなどで顕著
コスト重視でETFを選ぶ場合は、信託報酬だけでなくスプレッドと売買手数料も含めた「実質コスト」で判断するのが基本です。
運用の自動化・積立しやすさの違い
投資信託とETFは、どちらも少額から資産形成できる点で初心者に人気ですが、積立のしやすさや運用の自動化という面では大きな違いがあります。
📌投資信託は自動積立に完全対応
投資信託は、楽天証券・SBI証券などのネット証券を通じて、毎月一定額を自動で積み立てる設定が可能です。
注文のたびに操作する必要がなく、完全に自動化された資産形成ができます。
また、積立NISAやiDeCoなど、税制優遇制度との相性も良く、長期積立の仕組みが整っています。
📌 ETFは積立設定が手間になる
ETFは株式と同じように市場で売買されるため、自動積立の仕組みが証券会社側に用意されていないケースが多いです。
毎月自分でETFを買い付ける必要があり、積立投資としてはやや管理の手間がかかります。
ただし、ETF積立に対応している証券会社や、定期的に買付できるラップ口座なども一部存在しています。
流動性・リアルタイム性の差は?
ETFと投資信託では、売買のスピードとタイミングの自由度にも明確な違いがあります。
📌ETFはリアルタイムで取引可能
ETFは株式と同じように取引所に上場されており、相場が開いている時間ならいつでも売買可能です。
価格はリアルタイムに動いており、スプレッドも小さい傾向があります。
そのため「今の価格で買いたい・売りたい」という判断がしやすく、短期売買やタイミング重視の投資家に向いています。
📌投資信託は注文から約定までにタイムラグあり
一方、投資信託は1日1回算出される「基準価額」での売買となるため、注文から実際の約定までにタイムラグがあるのが特徴です。
たとえば午後に注文を出しても、その日の夜に基準価額が決まり、翌営業日に約定するという流れになります。
短期トレードには向いていませんが、長期積立であれば特に問題はありません。
NISA・iDeCoで使うならどっちが有利?
投資信託とETFのどちらをNISAやiDeCoで活用するかは、税制優遇の観点や運用管理のしやすさが判断基準になります。
📌投資信託は積立NISA・iDeCoの主力商品
積立NISAやiDeCoでは、金融庁の基準を満たした長期・分散・積立に適した低コスト投資信託が制度対象として選定されています。
手間をかけずに、毎月自動積立で非課税投資ができる点が最大のメリットです。
ETFは積立NISAの対象外であり、iDeCoでも扱っている金融機関はごく一部に限られます。
📌ETFは一般NISA向き
ETFは一般NISAであれば非課税枠の中で売買が可能ですが、積立設定や分配金の再投資などを自動化しにくいため、初心者には少しハードルが高い選択肢と言えます。
制度の使いやすさ・非課税枠の活用効率という観点では、投資信託の方が圧倒的に有利です。
初心者が最初に選ぶべきはどちら?
「これから資産形成を始めたい」という初心者にとっては、操作のわかりやすさ・積立のしやすさ・管理の手軽さが最優先です。
📌初心者には投資信託が向いている
-
自動積立に対応しており、買い忘れやタイミングの心配がない
-
少額からでも分散投資が可能(100円〜)
-
積立NISAやiDeCoの制度をフル活用できる
-
売買タイミングに迷わず、長期で積立できる設計
📌ETFは少し中級者向け
ETFは手数料の低さや流動性の高さが魅力ですが、自分でタイミングを見て購入する必要があるため、相場に慣れていないと戸惑いやすい傾向があります。
まずは投資信託で投資習慣を作り、後にETFを組み合わせていくのが自然なステップです。
目的別おすすめ活用法と商品選び【2025年最新版】
長期投資に向いているのは投資信託
長期投資においては、積立しやすさ・管理のしやすさ・心理的な安定感が非常に重要です。
この点で投資信託は、ETFよりも初心者にやさしい設計となっています。
📌長期投資向きの理由
-
自動積立が可能で「ほったらかし運用」が実現しやすい
-
分配金を自動で再投資できる(効率的な複利運用)
-
価格の変動に一喜一憂せず、基準価額でコツコツ資産形成できる
特に、積立NISAを利用した積立投資は20年非課税という長期視点に最適で、長く続けるほど恩恵が大きくなります。
短期・分散投資で力を発揮するETF
ETFは、タイミングを見て売買できる機動性の高さと、幅広い投資先が魅力です。
そのため、中〜短期の分散投資やテーマ投資にも向いています。
📌ETFが活きるケース
-
相場の上昇局面での一括購入&短期売却
-
業種や地域を分けたテーマ投資(例:AI、インド、ヘルスケアETF)
-
株式・債券・REITなど複数資産への分散が1本で可能
また、日本国内だけでなく米国ETFなども少額から買えるため、海外分散も容易です。
タイミング重視でアクティブに運用したい場合、ETFは非常に有効な選択肢となります。
2025年注目のインデックス型ETF3選
インデックス型ETFは、低コストかつ幅広い分散が可能なことから、長期投資の柱として非常に人気があります。
2025年時点で注目される代表的なETFを3つ紹介します。
MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558)
-
米国のS&P500指数に連動し、Apple・Microsoft・Amazonなど主要企業に分散投資
-
信託報酬0.078%程度と非常に低コスト
-
楽天証券やSBI証券で簡単に購入可能
iシェアーズ・コアMSCI 先進国株(1657)
-
日本を除く先進国の大型・中型株をカバー
-
通貨分散・地域分散ができるバランス型ETF
-
為替リスクを取る代わりに世界経済の成長を取り込める
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型(1678)
-
新興国の中でも今後人口成長が見込まれるインド市場に連動
-
インド経済の内需拡大や中間層成長をテーマにできるETF
-
インド関連の個別株に投資しなくても、手軽にアクセス可能
インド市場への投資は、ETFだけでなくテーマ型ファンドとの比較も有効です。上記リンクの記事では、投資信託との違いも含めて詳しく解説しています。
初心者向けの低リスク投資信託はこれ
投資初心者がまず選ぶべきは、値動きが安定していて、分散効果が高く、信託報酬が低い投資信託です。
ここでは、2025年時点でおすすめできる代表的な低リスク投資信託を紹介します。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
-
国内外の株式・債券・REITの8つの資産クラスに均等投資
-
相場環境に左右されにくく、長期安定型
-
信託報酬はわずか0.1133%程度と低コスト
幅広い資産に「自動で分散」されるため、投資先を選ぶ手間もなく、初心者の最初の1本に非常に適しています。
たわらノーロード 先進国債券
-
米国・欧州・オーストラリアなどの先進国の国債に分散投資
-
値動きが非常に安定しており、守り重視の資産形成に向いている
-
信託報酬も0.2%以下と良心的
ニッセイ日経平均インデックスファンド
-
日本の代表的な株価指数「日経平均株価」に連動
-
国内株式に慣れるためのステップとしてもおすすめ
-
楽天証券やSBI証券の積立NISA対象ファンド
これらの投資信託はすべて100円から積立が可能で、長期・積立・分散の基本を実践しやすい設計です。
特に最初の1~2年は、大きく増やすより「投資を継続する感覚」を身につけることが重要です。
同じく日経平均を母体としたファンドとして、近年注目されているのが「日経平均高配当利回り株ファンド」です。掲示板などで賛否が分かれるこのファンドの実態や、投資前に知っておきたい注意点については「日経平均高配当利回り株ファンド掲示板の評判・口コミは本当か?」を参考にされて下さい。
積立NISAで選ぶべき商品とは?
積立NISAは、年間40万円までの非課税枠で最長20年間の運用が可能な国の制度です。
この制度で資産形成を行うには、安定性・低コスト・長期運用向きの商品を選ぶことが重要です。
📌積立NISAのおすすめ条件
-
信託報酬が0.3%以下
-
インデックス型で分散性が高い
-
長期的に運用実績のあるファンド
📌代表的なおすすめ商品
-
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
→ 世界の株式市場を1本でカバー -
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
→ 米国の主要企業に連動。長期成長性重視 -
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
→ 米国の大型〜中小型株まで分散投資
積立NISAでは、値動きの激しいアクティブ型や新興国集中型ファンドは避けるのが賢明です。
🔗 関連記事:iDeCoで月1万円は意味ない?知恵袋の意見もご紹介!
※記事内で「積立の誤解」や「少額でも意味がある理由」について触れています。
ETFの落とし穴とリスク管理の基本
ETFは非常に便利でコストも低い商品ですが、運用にあたっていくつかの“落とし穴”や注意点があります。
理解しておかないと、想定外の損失につながることもあります。
📌よくある落とし穴
-
流動性が低いETFを買ってしまい、思うように売れない
-
海外ETFの分配金にかかる外国税控除を見落とす
-
為替リスクを軽視して円建て換算損が出る
📌リスク管理のポイント
-
取引量が少ないETFは避け、出来高・スプレッドを確認する
-
長期保有の際は為替ヘッジの有無にも注意
-
定期的にポートフォリオ全体のリバランスを実施
ETFは「低コスト・分散効果」が魅力ですが、個別株と同様の注意力が必要な“投資商品”であることは忘れてはいけません。
両方を組み合わせた分散戦略とは?
投資信託とETFのどちらが優れているかを一概に決めるのではなく、両方を適切に組み合わせることで、より柔軟かつ効率的な資産形成が可能になります。
📌組み合わせの一例
-
長期積立:投資信託
→ eMAXIS Slim オール・カントリーなどを積立NISAで毎月自動積立 -
短期テーマ投資:ETF
→ iシェアーズ ナスダック100などで米国ハイテクを狙う -
守りの資産:債券系ETF
→ AGG(米国債券ETF)や国内REIT ETFなど
📌メリットとバランス
| 視点 | 投資信託 | ETF |
|---|---|---|
| 積立のしやすさ | ◎(自動) | △(手動) |
| 売買タイミングの自由度 | △ | ◎ |
| 分配金の再投資 | ◎(自動) | △(要手動) |
| 費用 | ○(やや高め) | ◎(低コスト) |
両方を組み合わせることで、資産全体のバランス・流動性・成長性のバランスが整います。
ETFと投資信託の選び方まとめ
これまでの比較・解説をもとに、投資信託とETFの選び方をシンプルに整理します。
📌投資信託が向いている人
-
初心者・投資経験が浅い人
-
積立NISAやiDeCoを活用したい人
-
自動積立で着実に資産形成したい人
📌ETFが向いている人
-
自分の判断でタイミング投資をしたい人
-
テーマ・地域・資産クラスごとに細かく分散したい人
-
リアルタイムで相場に対応できる中級者以上の投資家
どちらも一長一短があり、「どちらか一方を選ばないといけない」わけではありません。
ライフスタイル・投資経験・目的に応じて最適な選択ができるよう、選択肢を持っておくことが重要です。
高配当ETFに興味がある方は、楽天証券で実際に購入できるおすすめ銘柄を比較したこちらの記事を参考にしてください。
【2025年ランキング】楽天証券で買えるおすすめ高配当ETF5選
よくある質問Q&A10選
Q1:ETFと投資信託、初心者にはどちらが向いていますか?
A:自動積立や制度活用がしやすい投資信託の方が初心者には向いています。
Q2:ETFは積立NISAで使えますか?
A:いいえ、ETFは積立NISAの対象外です。使えるのは一般NISAとなります。
Q3:投資信託とETF、どちらがコストは安いですか?
A:一般的にETFの方が信託報酬は低く設定されています。
Q4:分配金はどちらが有利ですか?
A:投資信託は自動再投資型が多く、ETFは分配金を現金で受け取る形式が一般的です。
Q5:ETFはスマホからでも買えますか?
A:はい、証券会社のスマホアプリから株式と同様に売買可能です。
Q6:長期で放置できるのはどちらですか?
A:積立設定が可能で再投資も自動化されている投資信託の方が、長期放置には向いています。
Q7:ETFにはリスクがありますか?
A:あります。為替変動や市場の流動性など、株式同様の価格変動リスクがあります。
Q8:NISAとiDeCoでは投資信託とETFどちらが使えますか?
A:積立NISAとiDeCoは投資信託が中心です。ETFは一般NISAでの利用が基本です。
Q9:投資信託とETFは両方買ってもいいですか?
A:もちろん可能です。目的や資金に応じて組み合わせる分散戦略が効果的です。
Q10:少額でも始められるのはどちらですか?
A:投資信託は100円から積立可能な商品が多く、ETFは1単位の金額が必要です。
少額投資のしやすさでは投資信託が優位です。
【2025年版】投資信託とETFはどっちがいい?初心者向け完全ガイドのまとめ
【本記事の関連ハッシュタグ】