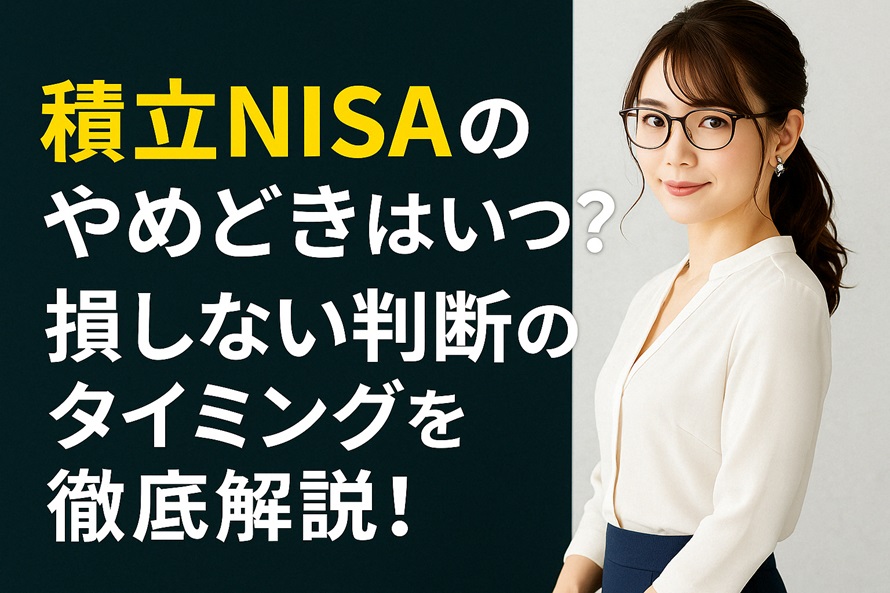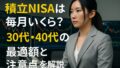積立NISAを始めたものの、「今やめた方がいいのか?」「続ける意味はあるのか?」と迷っていませんか?途中解約は自由ですが、判断を誤るとせっかくの非課税メリットを失ってしまう可能性もあります。

この記事では、積立NISAのやめどきに悩む方に、損しない判断タイミングや売却・一時停止の違い、一部売却の活用法までわかりやすく解説します。
- 📌積立NISAはいつでも途中解約・売却が可能
- 📌やめても非課税枠は戻らないため売却は慎重に判断
- 📌一部売却・一時停止という柔軟な選択肢も活用可能
- 📌やめどきには「出口戦略」を持つことが重要
👉「そもそも積立NISAを続けるべきかどうか」に不安を感じている方は「積立NISAはやめたほうがいい?知恵袋のリアルとFPの見解」を参考にしてください。
積立NISAの「やめどき」とは?判断基準と注意点
積立NISAは途中でやめても大丈夫?基本ルールを確認
積立NISAは「20年間非課税で積み立てられる制度」ですが、実はいつでも途中で売却・停止が可能です。
金融庁の公式ルールにも「途中解約不可」といった制限は一切なく、投資信託の売却=自由という設計になっています。
✅ 途中でやめる=2種類の選択肢がある
-
積立を止めて保有は継続(積立停止)
-
積立もやめて保有資産を売却(解約・取り崩し)
どちらも手数料はかからず、証券口座内での手続きのみで完了します。
ただし、一度使った非課税枠は戻らないため、やめるタイミングは慎重に考える必要があります。
✅ 途中解約で損するわけではないが…
「途中でやめる=損失確定」と誤解している人もいますが、損失が出るかどうかは“売却時の評価額”次第です。むしろ、利益が出ていればいつ売っても税金は非課税のままです。
➡️ 「いつ売るべきか」を判断することこそが、やめどきを見極める上でのポイントです。
関連記事:
👉 積立NISAはやめたほうがいい?どこがいいか知恵袋の感想も紹介!
※まだ始めるか迷っている方はこちらの記事も参考にしてください。
損しない「やめどき」の考え方とは?よくある3つの例
積立NISAをやめるタイミングは人それぞれですが、「損しないやめどき」には一定のパターンがあります。
以下のような状況では、一度やめる・一部売却する判断が有効なこともあります。
明確な資金ニーズがあるとき(教育費・住宅資金など)
将来のための積立とはいえ、急な支出が発生した場合にはやめる=生活防衛として合理的です。ただしこの場合でも「一部売却」や「積立の一時停止」で対応できる可能性もあるため、全売却より柔軟な選択を検討すべきです。
投資信託が高騰して大きな利益が出たとき
「これ以上の上昇は見込めない」「目的額に達した」など、利益確定のタイミングとしてやめるのは理にかなっています。利益分のみを売却することで、非課税枠を最大限活用しながら資金を取り崩すことも可能です。
含み損を抱えて不安になっているとき
このケースでは、感情に流されてやめてしまうと損を確定する可能性が高くなります。長期運用を前提とした制度なので、一時的な含み損では冷静に判断すべきです。
➡️ 含み損が気になる方には、以下の記事をご確認ください。
含み損が出たらやめるべき?判断の落とし穴
「評価額がマイナスになっている」「損が出ていて不安」――このような理由で積立NISAをやめる人は少なくありません。
ですが、含み損が出ているからといってすぐに解約するのは注意が必要です。
このブログでは何度も申し上げている通り、積立NISAは長期投資を前提とした制度です。
評価額がマイナスになるタイミングは、誰にでも必ず訪れます。
特に開始から2〜3年以内は市場の上下動の影響を受けやすく、むしろ“よくあること”と捉えるのが妥当です。
評価額が下がっている段階で売却すると、その損失は確定します。
それが一時的な価格下落だった場合、売らなければ回復していた可能性もあるのです。
積立NISAは、積立そのものを一時的に止めることも可能です。
投資信託を売却せずに運用は続けられるため、感情に流されず冷静な判断がしやすくなります。
積立NISAをやめたら返金される?お金の行き先とタイミング
積立NISAをやめると「返金される」と考える方もいますが、厳密には少し違います。
ここでは、売却時のお金の流れとタイミングについてわかりやすく解説します。
✅ 売却=保有中の投資信託を時価で現金化
積立NISAを「やめる」とは、証券口座で保有中の投資信託を売却することを意味します。
売却時点の基準価額に応じて、その分が現金として確定されます。
✅ 売却代金は「証券口座の預り金」に入金される
売却した資金は、通常は2~3営業日後に証券口座の「預り金(現金)」に反映されます。
そこから自分の銀行口座に出金するには、別途「出金手続き」が必要です。
✅ 売却=自動返金ではないので注意
「解約=銀行に自動振込される」と誤解している方も多いですが、実際には、
-
売却
-
証券口座へ着金
-
ユーザーが「出金操作」を行う
というステップを踏む必要があります。
手続きをしなければ、現金は証券口座に留まったままです。
途中解約・売却するとどうなる?制度上のデメリットとは?
積立NISAでは「解約=ペナルティがある」と誤解されがちですが、制度上、途中解約や売却に直接的な罰則や手数料はありません。
とはいえ、長期運用を前提とした制度のメリットを途中で手放すことによる“実質的なデメリット”は存在します。
✅ 一度使った非課税枠は戻らない
積立NISAでは毎年の非課税枠が決まっており、その年に使った分は売却しても非課税枠として再利用できません。
たとえば、ある年に36万円分のファンドを買い、翌年すぐに売却しても、その分を別の商品に差し替えることは不可です。
✅ 「20年非課税」のカウントは継続されない
非課税期間は“買付した年から20年間”と固定されており、売却後に再エントリーしても、カウントは新たに始まります。
つまり、売るたびに20年の積立スパンが途切れるため、本来の制度設計に適した「複利×長期」の恩恵が薄れます。
✅ デメリットは「金銭的損失」より「機会損失」
➡️ 「すぐに現金が必要」「目標達成済み」など明確な理由がある場合を除いて、解約前に一時停止や一部売却を検討する余地があります。
「一時停止」と「解約」は何が違う?再開できるパターンも解説
積立NISAをやめる=「すべてを解約・売却する」と考える人が多いですが、実際には「積立の一時停止」だけでも運用は継続できます。
✅ 一時停止とは?
-
積立設定を一時的にゼロにすること
-
保有中の投資信託は売却せずそのまま運用継続
-
設定変更は証券会社のマイページから数クリックで完了
この方法であれば、非課税枠を維持しながら、無理なく積立NISAを“中断”することが可能です。
✅ 解約(売却)との違い
| 比較項目 | 一時停止 | 解約(売却) |
|---|---|---|
| 投資信託の保有 | 継続される | 売却して現金化 |
| 非課税枠 | 継続利用可能 | 枠は消費済み・再利用不可 |
| 復活可否 | いつでも積立再開可能 | 同一年度内で再購入しても枠は戻らない |
| リスク | 少ない(市場に残し続ける) | 損益確定+機会損失のリスクあり |
✅ 再開はいつでも可能
多くのネット証券では「毎月」「隔月」などのスケジュール設定が柔軟で、再開時期も自由です。
積立余力が戻ったタイミングで再開することで、非課税運用を長く活かすことができます。
➡️ やめようか迷っている場合は、まず一時停止という選択肢を第一に検討するのが賢明です。
暴落時はやめる?続ける?下落相場での判断軸
「相場が急落して不安…」「今すぐやめた方がいいのでは?」
暴落時は誰もが不安になりますが、短期的な値動きに反応して判断すると後悔する可能性が高くなります。
✅ 積立NISAは“長期前提の制度”であることを思い出す
積立NISAは「20年間の非課税投資」を前提とした制度です。
相場が下がっている局面では、むしろ“安く買えるタイミング”と捉えることもできます。
✅ 積立をやめたくなったときの3ステップ判断
-
家計が本当に厳しいか?(生活に支障が出ている?)
-
下落が一時的な可能性はないか?(ニュースや経済要因を確認)
-
目的に照らして必要か?(教育費・住宅資金などの直近ニーズ)
これらを冷静に見直したうえで、「やめる or 一時停止」かを判断することが大切です。
✅ 下落相場でやってはいけないのは「感情による全売却」
感情的に売却したあと、すぐに相場が回復してしまったというのはよくあるパターンです。
この失敗を防ぐには、「一時停止」や「積立額の減額」といった柔軟な対応を選択肢に入れることが重要です。
ケース別のやめどきと対応方法【一部売却・停止・出口戦略】
利益分だけ売却する方法とは?一部売却の注意点
「全部はやめたくないけど、少し利益を確定したい」という場合、一部売却(利益分のみ売却)という選択肢があります。
✅ 一部売却は証券口座から簡単にできる
たとえば、投資信託の評価額が30万円あり、元本が20万円の場合、含み益の10万円だけを売却することも可能です。
証券会社の「金額指定売却」機能を使えば、任意の金額だけ現金化することができます。
✅ 非課税の恩恵を残したまま資金を確保できる
一部売却であれば、残りの投資信託は引き続き非課税運用の対象になります。
非課税枠を最大限活用しつつ、必要な資金を効率的に取り崩すことが可能です。
✅ 注意点:非課税枠は「戻らない」
➡️「売却してから買い直せばいい」といった考え方は、制度上のデメリットを伴います。
積立をやめずに売却だけできる?部分解約という選択肢
積立NISAを利用していると、「資金が必要になったから売却したい、でも積立は続けたい」と考える場面もあるでしょう。
この場合、積立を継続しながら保有商品を一部売却することは可能です。
✅ 積立設定と売却は別管理されている
積立NISAでは、
-
毎月の「積立設定」
-
すでに購入済みの「保有資産」
は別々に管理されています。
そのため、積立を止めずに保有中のファンドのみ売却する(部分解約)ことは制度上問題なくできます。
✅ 使い分けの例
-
月々の積立はそのまま継続
-
急な出費には評価額の一部を現金化して対応
このように、“出口戦略”の一部として部分売却を活用するのが賢い方法です。
✅ 売却の順番(ファンドの選定)には注意
➡️ できるだけ“古い年”の分から売却する方が効率的です(保有年数の短いものは温存)。
一部売却しても非課税枠は戻らない?制度の落とし穴
「一部売却すれば、その分の非課税枠が空くのでは?」と考える方もいますが、積立NISAの非課税枠は“年間上限額制”であり、再利用はできません。
✅ 非課税枠は“その年に買った分”で固定される
積立NISAの非課税投資枠は、年間最大40万円(2023年まで)または年間120万円(2024年以降の新NISAのつみたて投資枠)です。
この枠は使った瞬間に消費され、売却しても復活しない点に注意が必要です。
✅ よくある誤解
「いったん売却して、また買い直せば同じことでは?」
➡️ いいえ、再購入時には新たな枠を使うことになり、使い回しはできません。年間枠には限りがあるため、売却の判断は“資金の必要性”と“非課税の優先度”を天秤にかけて行うべきです。
✅ 長期的には“売らずに寝かせる”選択が最も有利なケースも
-
非課税のまま放置=利益が大きくなっても課税されない
-
一度売却すると、非課税のリスタートはできない
➡️ 将来の出口戦略を意識しながら、“むやみに売らない”判断も長期投資では大きな武器になります。
やめどきでも焦らないために「出口戦略」を考えておく
積立NISAは“始め方”よりも“終わり方”に悩む制度です。
いざ売却しようとすると「どのタイミングがベストなのか?」「どうやって取り崩せばいいのか?」という疑問が生まれます。
✅ 出口戦略とは「取り崩し方の設計図」
-
一括で売却して現金化
-
必要な分だけ取り崩す(定額・定率方式)
-
利益が出ている銘柄から順に売却
このように、将来の生活設計や資金ニーズに応じて、出口の形を前もって考えておくことが「やめどきの迷い」をなくす近道です。
✅ よくある取り崩し戦略の例
| 戦略タイプ | 内容 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 一括売却 | 全体を一気に売却 | 教育費・住宅購入など一時的に大きな資金が必要な人 |
| 定額取り崩し | 毎月一定額を売却 | 老後の生活資金に使いたい人 |
| 利益確定型 | 利益が出た商品から順に売る | 投資成果を確保しながら資産を残したい人 |
✅ 非課税期間終了時の対応も要チェック
20年の非課税期間が終了したあとは、自動で課税口座(特定口座など)へ移管されます。
この時点での売却も可能ですが、非課税の恩恵を最大限活かすには“期間満了前の計画的な出口”が望ましいとされています。
積立NISAをやめるタイミングは何歳が多い?平均データと傾向
「みんなはいつやめてるの?」という声もよく聞かれます。
金融庁が公表しているNISA関連の年代別データを参考にしながら、やめどきの傾向を見ていきましょう。
✅ 実際の利用動向:40代〜50代で売却が増える傾向
金融庁の「NISA口座の利用状況調査」によれば、売却を行っている層は40代後半〜60代に集中しています。
教育費や住宅資金、老後生活費など、ライフイベントと重なる時期に売却する人が多いと推測されます。
✅ やめる理由は「利益確定」だけではない
-
ライフステージの変化(教育費、転職、退職など)
-
市場環境の変化(相場の暴落や急騰)
-
精神的負担(評価額の変動への不安)
こうした要因から「一括売却」や「一時停止」を選択するケースも多く見られます。
✅ 年齢だけでやめどきを決めるのはNG
「40代になったから」「20年経ったから」という理由だけで売却を判断するのではなく、自分の目的と資金計画に沿ってタイミングを決めることが最も重要です。
口座を解約したらお金はいつ・どこに振り込まれる?
積立NISAをやめる(=保有商品を売却する)と、現金はどのように戻ってくるのでしょうか。
「解約=すぐ銀行口座に返金される」と誤解されることも多いですが、実際には段階的な処理が発生します。
✅ 売却代金はまず「証券口座内」に着金する
売却が成立すると、その資金は証券口座の預り金として反映されます。
タイミングとしては、約定から2〜3営業日後が一般的です。
✅ 銀行口座へ出金するには「別途操作」が必要
預り金は自動的に銀行口座へは振り込まれません。
利用中の証券会社の「出金依頼」画面から、
-
振込先銀行口座の選択
-
出金金額の指定を行う必要があります。
✅ 出金までの流れ(例:楽天証券・SBI証券)
-
投資信託を売却
-
約定(注文が成立)
-
約定日の2営業日後に証券口座へ入金
-
ユーザーが出金依頼
-
出金申請の翌営業日に銀行口座へ反映
➡️ 「解約したのに振り込まれない」と感じた場合は、証券口座の預り金欄をまず確認してみましょう。
積立NISAを途中でやめて後悔したケースと共通点
積立NISAを「なんとなくの不安」や「短期的な値動き」でやめてしまい、あとで後悔する人も少なくありません。
ここでは実際によくある後悔のパターンをご紹介します。
✅ ケース①:含み損で焦って売却 → 数ヶ月後に回復
「10万円の損失が怖くて全売却。
でも半年後に相場が戻っていて、売らなければプラスになってた…」
このように、一時的な不安に負けて“安値売り”してしまうケースは非常に多いです。
✅ ケース②:生活費が一時的に厳しくなって全解約 → 数ヶ月後に回復余地があった
「数万円を捻出したくて積立NISAを解約。
でも後で考えると、積立額を減らすだけでよかった。」
このパターンでは、一時停止や部分売却で乗り切れた可能性があります。
✅ ケース③:目的が曖昧なまま始めて、出口戦略が描けず投げ売り
「なんとなく始めたけど、何のために続けているか分からなくなって途中で売却。」
このように、“目的と期間”を定めず始めた場合に、迷走してやめてしまうリスクもあります。
➡️ 積立NISAは「売却しないと意味がない制度」でもありますが、タイミングと目的を誤ると、せっかくの非課税メリットが十分に活かせないという点を忘れないようにしましょう。
「寝かせる」だけで良い?20年非課税を最大限活かす考え方
積立NISAは、一度買った投資信託を「寝かせる(ホールドする)」だけでも十分に制度メリットを享受できます。
売却のタイミングに迷った場合、無理に動かず“放置”という判断も有効です。
✅ 非課税運用=長く持つほど恩恵が大きい
積立NISAの最大の特徴は、20年間の非課税期間が保証されていることです。
これは、値上がり益・分配金ともに課税されないという非常に大きなメリットであり、短期的に売却してしまうと、この“時間による成長”を放棄することになります。
✅ 寝かせる=下落も含めて“時間で均す”戦略
積立投資は「ドルコスト平均法」により、価格の上下を平均化して買い進めていく仕組みです。
よって、価格が下がっても積立を継続すれば取得単価は下がり、将来的に回復しやすくなります。
✅ 「投資=動かすもの」という先入観を捨てる
多くの人が「利益が出たら売る、損が出たらやめる」といった短期売買的な感覚で投資を捉えがちですが、積立NISAは“寝かせる=正解”となる数少ない制度です。
よくある質問Q&A10選
Q1. 積立NISAは途中で解約しても大丈夫ですか?
A. はい、いつでも解約・売却が可能です。解約に関しての手数料やペナルティも基本的にありません。
Q2. 解約したお金はどこに振り込まれますか?
A. 証券口座の預り金に入金され、その後自分で銀行口座に出金依頼を行う必要があります。
Q3. 一部だけ売却することはできますか?
A. 可能です。金額や口数を指定して、一部のみ売却することができます。
Q4. 積立NISAをやめると、非課税枠は戻りますか?
A. いいえ、一度使った非課税枠は売却しても復活しません。
Q5. 含み損が出ているときに売却するのは損ですか?
A. 含み損の状態で売却すると損失が確定します。長期投資を前提に冷静に判断しましょう。
Q6. 積立NISAを途中でやめて、再開することはできますか?
A. 積立設定の一時停止と再開は可能です。売却後の再積立では新たな非課税枠を使うことになります。
Q7. 積立NISAは何年寝かせるのが理想ですか?
A. 非課税期間の上限は20年です。少なくとも10年以上の長期運用が望ましいとされています。
Q8. 積立NISAを一時停止したら損になりますか?
A. いいえ。一時停止によって直接的な損失が生じることはありません。資金に余裕ができたら再開すれば問題ありません。
Q9. 利益が出ている分だけ売ることは可能ですか?
A. はい。評価益の一部を金額指定で売却することで、部分的な利益確定も可能です。
Q10. 積立NISAをやめたら、また始められますか?
A. 積立NISAの口座自体は維持できます。売却後も枠が残っていれば、新たに商品を購入することは可能です。
積立NISAのやめどきはいつ?損しない判断のタイミングを徹底解説!のまとめ
【あわせて読みたい関連記事】

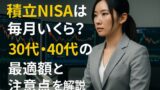
【本記事の関連ハッシュタグ】