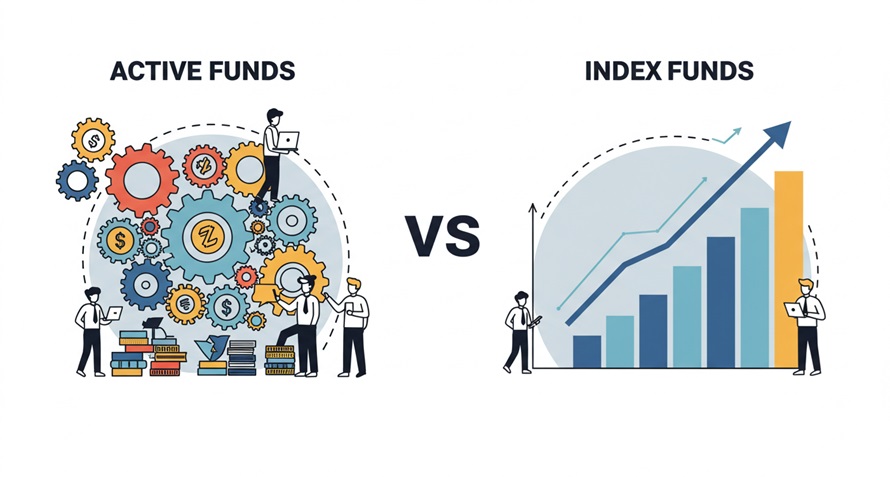本記事は、アクティブファンドの基本から「やめとけ」と言われる理由、さらに日本株と世界の投資信託の違いやランキング上位ファンドの特徴まで、長期保有を検討するうえで押さえておきたい視点を網羅的に解説していきます。
手数料やパフォーマンスの安定性といったファンド選びの重要ポイントに加え、アクティブファンドとインデックスファンドの違いや選び方もわかりやすく整理しましたので是非参考にされて下さい。
-
アクティブファンドがやめとけと言われる理由がわかる
-
長期保有におけるアクティブファンドの注意点が理解できる
-
日本株と世界のアクティブファンドの違いが比較できる
-
投資信託の選び方やランキングの見方が整理できる
アクティブファンドはやめとけ?その理由と実態
アクティブファンドはやめとけと言われる根拠とは?
結論からお伝えすると、「アクティブファンドはやめとけ」と言われる主な理由は、高コストの割にリターンが安定しない点にあります。
特に投資初心者や長期保有を前提に考えている方にとっては、慎重な選択が求められる投資信託です。
アクティブファンドは、特定の指数(インデックス)を上回るリターンを目指す投資信託で、ファンドマネージャーが独自の判断で銘柄選定や運用を行います。
理論的には「市場平均を超えるパフォーマンス」を期待できますが、実際には多くのファンドがインデックスファンドに劣る成績にとどまっています。
たとえば、アクティブファンドの多くは信託報酬が年1.0%前後であるのに対し、インデックスファンドは年0.1〜0.3%が主流です。
この差は長期保有するほど運用成果に大きな差を生みます。
さらに、ファンドマネージャーの裁量や相場観に依存する分、成績の振れ幅が大きく、再現性が低いのもリスク要因となります。
アクティブファンドが勝てない理由を解説
アクティブファンドが市場平均に勝てない理由は複数ありますが、最も大きな要因は市場の効率性と運用コストの高さです。
現代の金融市場では、個別株の情報は非常にスピーディーに市場価格へ織り込まれており、プロの運用者であっても“割安株”や“お宝銘柄”を探し出して高パフォーマンスを出すのは難しくなっています。
これを「効率的市場仮説」と言い、アクティブ運用の成果を妨げる根本的な要因のひとつです。
さらに、アクティブファンドは銘柄の入れ替えや調査・分析に多くのコストがかかるため、インデックスファンドよりも信託報酬が高くなりがちです。
この“コスト差”が、長期的に見ると運用成績に大きく影響します。
たとえば、年率リターンが5%のインデックスファンドと、同じパフォーマンスを出したアクティブファンドでも、手数料が0.9%高ければ、10年後の資産額には数十万円単位の差が出ます。
このような構造的な不利が、アクティブファンドが勝ちにくい理由です。
インデックスファンドとの違いをわかりやすく解説
アクティブファンドとインデックスファンドの違いは、「運用の目的と手法」にあります。
-
アクティブファンドは、市場平均を上回る成績(いわゆる「α」)を狙い、ファンドマネージャーが企業分析や業界動向を元に銘柄を選びます。裁量の余地が大きく、トレンドに乗った成績を出すこともあれば、予測が外れて市場全体に劣後することもあります。
-
インデックスファンドは、日経平均株価やS&P500、TOPIXなどの市場平均に連動する成績(「β」)を目指す投資信託で、手数料も低く、安定性が高いのが特長です。
インデックスファンドは投資対象の見直しも定期的かつルールに基づいて行われるため、「ほったらかし投資」に向いており、長期で運用する初心者には特におすすめされる傾向があります。
一方、アクティブファンドは運用の中身や方針が時期によって変わることもあり、定期的なチェックが欠かせません。
| 比較項目 | アクティブファンド | インデックスファンド |
|---|---|---|
| 目的 | 市場平均を上回ることを目指す | 市場平均に連動することを目指す |
| 信託報酬(平均) | 0.8% ~ 1.5% | 0.1% ~ 0.3% |
| 運用方法 | 運用者の裁量で銘柄選定 | 指数に基づいて自動運用 |
| 長期保有の適性 | 低い(都度チェックが必要) | 高い(放置しやすい) |
| 初心者との相性 | 向いていない | 向いている |
| パフォーマンスの安定性 | 不安定(マネージャー次第) | 安定(指数に準じる) |
違いをしっかり理解した上で、自分の投資目的やスタイルに合ったファンド選びが重要です。
投資初心者がアクティブファンドで失敗しやすい理由
投資初心者がアクティブファンドで失敗しやすい最大の理由は、「見た目の成績」や「人気ランキング」に過度に依存して選んでしまう点にあります。
アクティブファンドの中には、直近1年や3年といった短期の運用成績が非常に優れているものもあります。
これを見て「このファンドが一番良さそう」と飛びついてしまうのは、初心者にありがちなパターンです。
ですが、過去のリターンは未来を保証するものではなく、特にアクティブファンドは市場環境に応じて成績が大きく変動するため、短期的な成績だけで判断するのは非常に危険です。
また、ファンドマネージャーの交代や運用方針の微調整など、見えにくい内部的な変化も影響します。
初心者の場合、そうした情報を読み取るのは難しく、結果として“買った時は良かったけれど数年後には低迷”というケースも珍しくありません。
さらに、販売会社が出している「おすすめファンド」や「売れ筋ランキング」には、販売手数料の高い商品が多く含まれている傾向があります。
これは、金融機関側の事情であり、必ずしも「長期保有に適した商品」とは限りません。
失敗を避けるには、ランキングに惑わされず、信託報酬や組入銘柄、長期のパフォーマンス推移など、本質的なデータを確認して判断することが重要です。
アクティブファンドの手数料がパフォーマンスに与える影響
アクティブファンドを選ぶ際に見落とされがちなのが「手数料が成績に及ぼす影響」です。
特に信託報酬(保有している間に自動的に差し引かれる年間の運用コスト)は、長期保有でのトータルリターンに直結する重要な要素です。
多くのアクティブファンドでは、信託報酬が年1.0%前後に設定されています。
一方、人気のインデックスファンドは0.1〜0.3%程度が主流であり、この差は決して小さくありません。
例えば、年5%のリターンを出しているファンドがあったとしても、信託報酬が1.0%であれば、実質的な利回りは4%になります。
インデックスファンドで信託報酬が0.2%であれば、実質4.8%のリターンとなり、20年後には数十万円以上の差がつくこともあります。
また、アクティブファンドには売買回転率が高いものが多く、組み替え時の売買手数料や内部的なコストが加算されている場合もあります。
これらは運用報告書などに詳しく記載されているものの、普段あまり意識されない「見えないコスト」として、パフォーマンスをじわじわと圧迫します。
結果として、「市場平均と同じくらいの成果」しか出せなかった場合でも、手数料で差し引かれてしまい、実質的にはインデックスファンドに大きく劣後するケースが多いのです。
アクティブ投資のデメリットを知っておこう
アクティブファンドには「市場を上回る成果が狙える」という魅力がある一方で、リスクや手間といったデメリットも明確に存在します。
このように、アクティブファンドには「狙えるけれど難しい」「上手くいけば大きいが失敗すれば痛い」といった、投資上級者向けの要素が含まれているのです。
ほったらかし投資との相性が悪い理由
アクティブファンドは、近年注目を集めている「ほったらかし投資」とは基本的に相性が良くありません。
ほったらかし投資とは、日々の値動きに振り回されず、長期的に積み立てて資産形成を目指す手法ですが、アクティブファンドはこのスタイルと真逆の性質を持っています。
理由は、アクティブファンドが常に「市場に勝つこと」を目指して、銘柄の入れ替えやタイミングを重視する運用を行っているためです。
市場の環境が変わると、そのファンドが一気に不調になることもあります。
また、ファンドマネージャーの交代や運用方針の変更などが起きれば、保有し続けて良いのか再評価が必要になります。
ほったらかしで運用するということは、「中身が変わらない」「仕組みが明確で継続的」であることが前提となります。
その点、インデックスファンドは一定のルールで市場全体をカバーし、構成も自動的に調整されるため、何もせずとも時代に合わせて内容が最適化されるというメリットがあります。
一方で、アクティブファンドはそうではありません。情報収集や運用方針のチェックが欠かせず、放置している間にパフォーマンスが大きく悪化しているということも十分にあり得ます。
“放ったらかし”で成功したい人には、アクティブファンドは不向きな選択肢です。
長期保有でもアクティブファンドは報われにくい?
アクティブファンドは「短期的な運用で成果を出す」イメージを持たれがちですが、長期保有で報われるケースもゼロではありません。
ただし、それは非常に限定的です。
アクティブファンドの中でも長期にわたってインデックスを上回るリターンを出しているものはありますが、割合で言えばごく一部にすぎません。
たとえば、米国で公表されている「SPIVAレポート」では、10年以上のスパンでインデックスに勝ち続けているアクティブファンドは全体の10〜20%未満というデータも存在します。
また、特定の相場環境に強いファンドでも、数年後にはその運用テーマが通用しなくなることもあります。
これがアクティブファンドの宿命です。
さらに、信託報酬などのコストが複利で積み重なるため、リターンを圧迫し続ける構造になっています。
インデックスファンドであれば、市場全体の成長に乗る形で10年、20年と保有することが可能ですが、アクティブファンドの場合は「途中で中身を見直す必要がある」ため、完全な長期保有には向きません。
長期間の運用で安定したリターンを狙いたいなら、やはり低コストで構成が明快なインデックス型の投資信託が優位です。
新NISAでのアクティブファンドの扱いとは?
2024年からスタートした新NISA制度では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に分かれています。
アクティブファンドは基本的に成長投資枠の対象商品として位置づけられています。
つまり、毎月コツコツと積立する「つみたて投資枠」では購入できないケースが多く、アクティブファンドを活用するには年間最大240万円までの成長投資枠を使う必要があります。
ただし、すべてのアクティブファンドが成長投資枠で購入できるわけではありません。
対象となるには金融庁が定める一定の条件(販売手数料ゼロ、信託報酬の上限など)を満たす必要があるため、人気ファンドであっても非対象となっているケースもあります。
新NISAは「非課税期間が無期限」「ロールオーバーが不要」という長期投資に有利な制度です。
したがって、コストの低い商品を選ぶことが何よりも重要になります。
その点で、手数料の高いアクティブファンドは制度の趣旨にそぐわないという意見もあり、慎重に選ぶ必要があります。
JPX日経400対応アクティブファンドの実力とは?
「JPX日経400」は、企業の資本効率や収益性、ガバナンスなどを重視して選ばれた日本株の株価指数です。
最近では、この指数に連動するアクティブファンドや、同様の評価基準を取り入れた運用戦略のファンドも登場しています。
一見、質の高い企業に集中投資できるという点で魅力的に思えますが、注意点もあります。
アクティブファンドでJPX日経400に関連する商品は、構成銘柄が流動的で、継続的に同じ銘柄を保有し続ける保証がないという特性を持ちます。
つまり、今期は優れた企業でも、翌期には除外されてしまうこともあり、投資対象が入れ替わりやすい傾向があります。
さらに、JPX日経400自体のリターンも、TOPIXや日経平均と比べて一貫して優れているとは言えず、相場によって強さにバラつきがある点にも留意が必要です。
このようなファンドを活用する際は、「指数の評価基準が投資目的に合っているか」「構成変更の頻度によってパフォーマンスが不安定にならないか」といった視点でしっかりと比較検討することが大切です。
インデックスとアクティブの見分け方は?
投資初心者にとって、「この投資信託はアクティブなのかインデックスなのか?」を見分けるのは意外と難しく感じるかもしれません。
ですが、ポイントを押さえれば比較的簡単に判断できます。
まず、商品名に「インデックス」や「指数連動」などの表記があるかを確認しましょう。
たとえば「○○インデックスファンド」「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」などの名称は、インデックスファンドであることを示しています。
一方で、「厳選」「戦略」「アクティブ」「グロース」「○○リサーチ」などのキーワードが含まれている商品は、アクティブファンドである可能性が高いです。
次に、投資信託の目論見書や販売ページの「運用方針」欄を見てください。
そこに「特定の指数に連動する投資成果を目指します」と書かれていればインデックスファンドです。
逆に「ベンチマークを上回る成果を目指して…」と記載があればアクティブファンドです。
また、信託報酬にも注目しましょう。
インデックスファンドは通常0.1~0.3%程度、アクティブファンドは0.8~1.5%程度が一般的です。
これも大きな見分けポイントになります。
さらに、ファンドが参考としている指数にも注目です。
S&P500やTOPIX、日経平均株価などの広く知られている指数をベンチマークにしていればインデックスファンドの可能性が高く、特定のテーマやスタイルを強調している場合はアクティブファンドと考えてよいでしょう。
見分ける際のチェックポイントまとめ
-
ファンド名に「インデックス」などが含まれているか
-
目論見書に「指数に連動する」と明記されているか
-
信託報酬が0.3%未満かどうか
-
「ベンチマークを上回る成果を目指す」などの記述があるか
このように複数の視点から確認することで、インデックスかアクティブかを比較的簡単に判別することができます。
迷ったときは、金融庁や証券会社の公式情報を活用するのもおすすめです。
アクティブファンドの世界と日本の最新ランキング
アクティブファンドの世界ランキング上位はどこ?
アクティブファンドは世界中に無数に存在しますが、その中でも過去の運用実績や資産規模などから高く評価されているファンドがあります。
特に米国を中心とする世界市場では、「伝統と実績」が評価基準として重視されています。
たとえば、世界的に有名なアクティブファンドとして以下がよく挙げられます。
-
フィデリティ・コントラファンド(Fidelity Contrafund)
米国の大型グロース株に投資する代表的なファンドで、過去20年以上にわたり市場平均を上回るパフォーマンスを記録したこともあります。 -
ティー・ロウ・プライス・ブルーチップ・グロース(T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund)
成熟企業を中心に分散投資し、安定した運用を行っているアクティブファンドです。 -
スコットランド・ベイリー・ギフォード・グローバル成長株ファンド
欧州系のアクティブファンドで、テスラやアマゾンへの早期投資で注目を集めたファンドです。
これらのファンドは世界ランキングで常に上位に入り、特に資産規模、長期リターン、手数料の透明性といった評価項目で高い評価を得ています。
ただし注意点として、世界ランキング上位のファンドが「これからも勝ち続ける」保証はありません。
また、日本からは直接投資できないファンドもあるため、類似の戦略を持つ投資信託を選ぶ視点が求められます。
日本株アクティブファンドのランキングと傾向
日本国内のアクティブファンドにも、注目すべき人気商品が多数存在します。
特に、日本株に特化したアクティブファンドは、国内の個人投資家から安定した支持を得ており、ランキングでも上位常連のファンドがいくつかあります。
2025年現在、実績・規模ともに高い評価を受けている日本株アクティブファンドには以下のようなものがあります。
-
ひふみ投信
個人投資家に圧倒的な人気を誇るアクティブファンドで、成長企業を見極める独自の調査手法が特徴。信託報酬は約1.078%。 -
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)
資本効率の高い企業への集中投資が特徴で、長期保有を前提とした運用スタイルを取っています。 -
三井住友・中小型株ファンド
中小企業の成長性に着目したアクティブファンドで、TOPIXを上回る成績を記録する年もあります。
これらのファンドに共通するのは、「個別企業の分析力に基づく選別投資」です。
インデックスとは違い、どの企業に何%投資するかがファンド独自で決まるため、運用方針と実際の中身に大きな違いが生まれる点が特徴です。
ただし、短期的に好成績でも中長期ではパフォーマンスが落ちることもあるため、保有する際は「継続的に運用方針を見直す」意識が必要です。
最強のアクティブファンドは本当に存在する?
「最強のアクティブファンド」と呼ばれる投資信託は、ランキングや口コミで話題になることがありますが、結論としては一時的に最強だったファンドは存在しても、永続的に最強なファンドは存在しないというのが現実です。
アクティブファンドのパフォーマンスは、ファンドマネージャーの判断、投資テーマ、市場環境によって大きく左右されます。
たとえば、グロース株が強い相場では成績がよくても、バリュー株中心の相場では大きく崩れることがあります。
つまり、「相場に合っているかどうか」が勝敗を分ける最大のポイントになります。
また、「過去の成績が良いから」という理由で投資してしまうと、逆にピークでつかんでしまい、その後のパフォーマンス低下に悩まされることも少なくありません。
これは、多くの投資家が「ランキング1位」などの短期的な人気に引き寄せられて投資してしまうためです。
本当に最強のファンドを探すのではなく、「自分の投資目的に合っているか」「長期保有に耐えられるか」を軸に選ぶ方が、結果的に満足度の高い運用につながります。
アクティブファンドのおすすめは?
アクティブファンドを選ぶ際に「おすすめ」を探す気持ちはよくわかりますが、まず前提として知っておくべきなのは、すべての人にとって“万能なおすすめファンド”は存在しないという事実です。
資産形成の目的やリスク許容度、保有期間によって選ぶべきファンドは変わるため、万人向けの商品は存在しません。
とはいえ、一定の基準で「おすすめしやすいアクティブファンド」は存在します。
以下のようなポイントで絞り込むと良いでしょう。
-
長期で安定した成績を残している(3〜5年以上)
-
純資産残高が大きく、運用の安定性が高い
-
信託報酬が比較的低く、透明性が高い
-
運用方針や組入銘柄の情報がしっかり開示されている
これらの観点から見て、国内では「ひふみ投信」や「厳選投資」などがよく挙げられます。
ただし、過去に良かったからといって、今後も良いとは限らない点には十分な注意が必要です。
おすすめを探すことよりも、「自分の投資目的に合った商品を比較検討すること」こそが、最適なアクティブファンド選びの第一歩です。
インデックスに勝っているアクティブファンドの特徴
アクティブファンドの中には、一定期間において市場平均(インデックス)を上回る成績を出しているものも存在します。
こうしたファンドに共通する特徴を知ることは、今後のファンド選びに役立ちます。
主な特徴は以下のとおりです。
-
銘柄選定に明確な戦略がある(たとえば「ROEの高い企業に限定する」など)
-
集中投資により、トレンドに乗った企業を大きく組み入れている
-
長年同じファンドマネージャーが運用している
-
組入銘柄の入れ替えが少なく、運用方針がブレない
インデックスに勝つには「差別化された視点」が必要です。市場と同じような構成であれば、当然ながらインデックスと似た成績にしかなりません。
逆に、ファンド独自の調査力や中長期視点での分析力がある場合、市場の過小評価を受けている銘柄に投資してリターンを得る可能性があります。
ただし、このようなファンドでも「常に勝ち続ける」わけではありません。短期では負ける局面もあり、それを耐える強さが必要です。
ランキング上位ファンドの共通点とは?
アクティブファンドのランキングで上位に入るファンドには、いくつかの共通点があります。
それを知ることで、自分でファンドを評価する際の参考になります。
上位常連のファンドは、純資産残高が数百億〜数千億円と大きく、資金流入が継続しています。これにより、信託報酬の実質コストも抑えられる傾向があります。
3年以上、できれば5年〜10年といった長期のパフォーマンス履歴があるファンドは、運用力の“地力”が問われたうえで評価されている証拠です。
組入上位銘柄や運用方針、月次レポートなどがしっかりと公開されているファンドは、投資家にとって安心材料になります。
一時的なトレンドやブームに乗るだけでなく、堅実な銘柄選定と分散を意識しているファンドが上位に残りやすいです。
これらを踏まえると、「ランキングの上位にある=信頼できる」とは限りませんが、上位に長く残り続けているファンドは一定の信頼に足る実力を持っていると判断できます。
世界と日本で見るアクティブファンドの違い
アクティブファンドは世界中で広く展開されていますが、日本と海外(特に米国や欧州)とでは運用スタイルや投資家のニーズに違いがあります。
まず、日本のアクティブファンドは、比較的保守的な運用が多く見られます。
企業訪問や業績分析に基づいた銘柄選定を行い、長期的な成長を重視するスタイルが主流です。
また、分散投資よりも集中投資の傾向が強く、特定のテーマや業界にフォーカスしたファンドも多く存在します。
一方で、米国や欧州のアクティブファンドは、トレンドやマクロ経済を重視した戦略が多く見られます。
AIやESGといったテーマ投資が活発で、ファンドマネージャーの個性や投資哲学が前面に出るケースも少なくありません。
ランキングで上位に入るような海外のファンドは、資産規模も数兆円クラスに達しており、グローバルに分散されたダイナミックな運用が特徴です。
また、手数料体系にも違いがあります。
海外では成功報酬型やパフォーマンス連動型の料金設定が一般的な一方、日本では信託報酬が年率で固定されているケースが大半です。
この点でも、日本の投資家にとってはコスト面の検討が重要になります。
| 比較項目 | 日本のアクティブファンド | 世界(特に米国)のアクティブファンド |
|---|---|---|
| 運用スタイル | 保守的・国内企業中心 | ダイナミック・グローバル分散型 |
| 投資対象 | 大型株や中小成長株、日本企業重視 | 米国株中心、成長テーマ型(AI・ESGなど) |
| 人気テーマ | バリュー株、安定収益企業 | グロース株、新興企業、メガテック |
| ファンド規模 | 数十億~数百億円規模が多い | 数千億~数兆円規模も存在 |
| 手数料体系 | 信託報酬が年率で固定 | 成功報酬型やパフォーマンス連動型あり |
| 情報開示の充実度 | 月次レポート中心、やや保守的 | 詳細な分析やポートフォリオ解説が多い |
世界と日本のアクティブファンドを比較することで、自分に合った投資スタイルが見えてくるはずです。
S&P500は長期保有で何倍になるのか?
S&P500とは、アメリカの代表的な株価指数であり、インデックスファンドのベンチマークとしてもよく使われています。
長期保有によってどの程度の資産成長が期待できるかを知っておくことは、アクティブファンドと比較する上でも重要です。
過去の実績を振り返ると、S&P500は年率約7〜10%のリターンを記録しており、複利の力によって長期では大きな成果を出しています。
仮に年率7%で運用できた場合、10年で資産は約2倍、20年で約4倍、30年でおよそ8倍に膨らむ計算です。
もちろん、これはあくまで平均的なリターンであり、必ずしも毎年プラスになるとは限りません。
ですが、過去の統計では15年〜20年以上保有した場合、元本割れの確率はほぼゼロに近づいています。
このように、S&P500のような広範なインデックスに連動する商品は、長期的に見て堅実な資産形成ができる選択肢です。
アクティブファンドが市場に勝てるかどうかという視点と併せて、こうした指数の実力も冷静に比較しておくことが大切です。
インデックス投資の落とし穴と注意点
インデックス投資は低コストでシンプル、そして安定した成績が期待できるという点で広く支持されていますが、万能な投資手法というわけではありません。
いくつかの落とし穴や注意点も存在します。
まず一つは、指数の構成銘柄に偏りがあることです。
たとえば、S&P500やNASDAQ100は、米国の大型IT企業の割合が高く、特定のセクターに依存した動きになりやすいという特徴があります。
そのため、経済全体の成長を反映しているとは限らず、実はかなりテーマ性が強い場合もあります。
また、インデックス投資では、市場全体が不調な時期には当然ながらファンドの評価額も下がります。
これはアクティブファンドのように相場の変化に対応する柔軟性がないため、下落局面を回避するという運用はできません。
さらに、長期で保有してもリターンが出るとは限らず、タイミングによっては大きな含み損を抱えることもあります。
市場のピークで買ってしまうと、回復までに数年かかることも珍しくありません。
このように、インデックス投資は安定性が魅力である一方、リスクがゼロではないという認識を持ち、適切な分散と長期視点を持つことが重要です。
長期投資で元本割れしない仕組みとは?
長期投資は「元本割れしにくい」と言われますが、それにはいくつかの要因があります。
特にインデックス投資やバランスファンドを用いた長期運用では、リスクが時間とともに平均化されるため、損失の可能性が低減される構造になっています。
まず、株式市場全体は経済の成長とともに拡大する傾向があるため、短期的な下落があっても長期では右肩上がりになることが多いです。
これを支えているのが、企業の利益成長や人口の増加、技術革新などの構造的な経済要因です。
次に、長期で積立を行うことで、価格が高い時期も安い時期も平均して購入することになり、購入価格が平準化されます。
これが「ドルコスト平均法」と呼ばれる手法で、下落局面でも積立を続けることがリスク分散につながります。
加えて、再投資による複利の効果も見逃せません。
運用益をそのまま再投資することで、時間の経過とともに加速度的に資産が増える仕組みになります。
こうした要素が合わさることで、20年以上の長期スパンで元本割れを避けられる可能性が高まるのです。
ただし、完全にリスクをゼロにすることはできないため、ポートフォリオのバランスや生活設計と連動させることが重要です。
eMAXIS Slim(S&P500)のデメリットも知っておこう
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、低コストかつ人気のインデックスファンドとして知られています。
信託報酬は年0.09372%(2025年時点)と業界最安水準で、多くの投資家に選ばれていますが、デメリットも存在します。
一つ目は、投資先が米国株式に偏っていることです。
S&P500はアメリカを代表する500社で構成されていますが、国際分散投資という観点から見ると、地域的な偏りがあるとも言えます。
特に米国の景気が悪化した場合、その影響をダイレクトに受けるリスクがあります。
二つ目は、上位銘柄の比重が極端に高い点です。
現在のS&P500は、アップルやマイクロソフトなどの巨大IT企業が指数の20%以上を占めており、個別銘柄の影響を大きく受けやすくなっています。
これはインデックス投資のつもりが、実質的にはITセクターへの偏重投資になっているとも言えます。
三つ目は、為替リスクの存在です。
円で運用する場合、為替レートの変動によって基準価額が上下することがあり、米国株が上昇していても円高の影響で評価額が減少する可能性もあります。
こうした点も踏まえて、eMAXIS Slim(S&P500)を選ぶ際は、魅力だけでなくリスク面もしっかり理解したうえでポートフォリオに組み入れることが大切です。
よくある質問Q&A10選
Q1. アクティブファンドはやめとけって本当?初心者には向かないの?
A. アクティブファンドは手数料が高く、成果が不安定な場合があるため、初心者や長期保有を前提とした投資には不向きとされることがあります。ただし、目的に合えば一部は有効です。
Q2. アクティブファンドとインデックス型投資信託はどちらが安定している?
A. 一般的にインデックス型の投資信託はコストが低く、長期的に安定した成績を出しやすいとされています。アクティブファンドは運用方針次第で差が大きく、選定の難易度も高いです。
Q3. 日本株に投資するアクティブファンドは成績が悪いの?
A. 日本株を対象にしたアクティブファンドの中にも優れた実績を出しているものはありますが、市場平均を継続的に上回るファンドは少なく、選定には慎重さが求められます。
Q4. 世界のアクティブファンドのランキングでは何が評価されている?
A. 世界ランキングでは、長期のパフォーマンス、純資産規模、リスク管理、手数料のバランスなどが評価されます。特に米国では成長株への投資戦略が評価される傾向があります。
Q5. アクティブファンドを長期保有するのは間違い?
A. アクティブファンドを長期保有する場合、途中で運用方針やマネージャーが変わることがあり、安定した成果を得るのが難しいとされます。継続的な見直しが必要です。
Q6. アクティブファンドのおすすめランキングは信頼できる?
A. 短期的なランキングは変動が大きいため、必ずしも信頼できるとは限りません。長期視点での実績や、コスト、組入銘柄の開示など総合的にチェックすることが重要です。
Q7. 投資信託でアクティブ型を選ぶときの注意点は?
A. 高コスト、運用の一貫性、リスクの大きさに注意が必要です。また、販売会社のおすすめが必ずしも自分に合っているとは限らないため、比較と理解が欠かせません。
Q8. 世界株に投資するアクティブファンドにはどんな魅力がある?
A. 世界株型アクティブファンドは成長市場やテーマ別投資に強みがありますが、分散性が低かったり為替リスクを伴うケースもあり、投資対象と目的の明確化が大切です。
Q9. 日本株のアクティブファンドで長期的に成績が良い商品はある?
A. 長期的に安定した成果を出している日本株アクティブファンドもありますが、数は限られています。純資産の規模や運用歴の長さ、信託報酬の水準などを確認しましょう。
Q10. アクティブファンドはやめとけという意見はどこから来るの?
A. 多くのアクティブファンドがインデックスを下回る結果になっていることや、手数料負けしやすい構造があるため、長期的に見て非効率とされることが理由です。
アクティブファンドはやめとけ?日本株から世界のランキングと長期保有についてのまとめ
最後にこの記事のポイントをまとめました。
【あわせて読みたい関連記事】



【本記事の関連ハッシュタグ】