
本記事では、長期投資で人気の「オルカン(全世界株式)」と「S&P500(米国株)」の過去30年の平均利回りを比較し、それぞれの特徴やリスク、選び方のポイントを徹底的に整理しました。

インデックス投資に挑戦したいけれど、どちらを選ぶべきか悩んでいる方に向けて、利回りだけにとらわれず、自分に合った投資判断ができるよう、実例やデータを交えながら解説。将来の資産形成に役立つインデックスの「選び方」の是非参考にされて下さい。
-
オルカンとS&P500の過去30年間の平均利回りとその背景
-
地域分散・リスク・配当など、インデックスの性質の違い
-
投資目的やリスク許容度に応じた適切な選び方
-
実際のシミュレーションに基づく資産形成のイメージ
オルカンとS&P500の平均利回りを30年データで比較
オルカン(全世界株式)の基本構成と特徴
オルカンとは、「全世界株式インデックス」の通称で、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(MSCI ACWI)などをベンチマークとする全世界の株式市場をカバーするインデックスファンドを指します。
具体的には、以下のような特徴があります。
-
先進国・新興国を含む全世界約50カ国以上の株式が対象
-
日本を含む先進国が約85%、新興国が約15%の構成比
-
地域・業種・通貨を自動的に分散してくれる
-
時価総額加重平均により、世界経済全体に連動
代表的な投資信託には以下のようなものがあります。
| 商品名 | ベンチマーク | 信託報酬(年率) |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | MSCI ACWI(除く日本)など | 約0.05775%~ |
このように、1本で世界中に分散投資ができる「究極のほったらかし投資」として人気を集めています。
以下はSTSで提供させていただいている無料で視聴できる動画セミナーです。ちなみに年間100~1000万円を増やすような投資賢者たちは実は”NISA”、”米国株”、”米国債”、”投資信託”にほとんど投資をしていません。その理由もチェックしておいてください。
S&P500の構成とアメリカ経済との連動性
S&P500は、米国の代表的な株価指数で、アメリカを代表する大型株500社で構成されています。
アップル、マイクロソフト、アマゾン、テスラなど、時価総額上位の成長企業を含むため、米国経済そのものの成長を享受できるインデックスとも言われています。
構成の特徴は以下の通りです。
-
テクノロジー・医療・金融の3業種が全体の約65%を占める
-
上位10銘柄で全体の30%以上の比重を持つ(GAFAMが中心)
-
長期で見るとインフレに強く、成長性も高い
代表的な投資信託・ETFには以下のようなものがあります。
| 商品名 | ベンチマーク | 信託報酬(年率) |
|---|---|---|
| SBI・V・S&P500インデックスファンド | S&P500 | 約0.0938% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | S&P500 | 約0.093% |
S&P500は世界中の機関投資家にも利用されており、運用資産残高・流動性ともに世界トップクラスの信頼性を誇ります。
オルカンとS&P500の過去30年平均利回りを比較
それでは、注目の「過去30年間(1994年〜2023年)」の年平均利回りを比較してみましょう。
信頼できるデータをもとにした参考値は以下の通りです。
| 指数 | 年平均利回り(1994〜2023年) |
|---|---|
| S&P500 | 約10.5%〜11% |
| オルカン(MSCI ACWI) | 約6.5%〜7.5% |
このように、S&P500の方が明確に高いパフォーマンスを記録しています。
理由はシンプルで、米国がこの30年間で世界経済を牽引し、GAFAMなどのメガテックが指数全体の成長をけん引したためです。
一方でオルカンは、ヨーロッパや日本など成長鈍化傾向の国も含むため、「平均点」はやや抑えられる構造となっています。
年ごとのリターン推移とボラティリティの違い
長期平均ではS&P500が有利ですが、年ごとのリターンの“荒れ方”=ボラティリティにも注目する必要があります。
下記は直近5年間の年間リターン(参考)です。
| 年度 | S&P500 | オルカン |
|---|---|---|
| 2019年 | +31.5% | +26.6% |
| 2020年 | +18.4% | +16.3% |
| 2021年 | +28.7% | +21.4% |
| 2022年 | -18.1% | -18.5% |
| 2023年 | +24.2% | +21.8% |
どちらも同じような動きをしていますが、S&P500の方が上下の振れ幅がやや大きく、変動リスクも高い傾向があります。
つまり、
-
リスクを取りつつ高利回りを狙うならS&P500
-
ボラティリティを抑えて広く分散したいならオルカン
という棲み分けが見えてきます。
為替リスクの影響はどちらに強く出るのか?
どちらも外貨建て資産を含むインデックスであり、円ベースで見たときの「為替の影響」は避けられません。
| 指数 | 為替の影響の度合い |
|---|---|
| S&P500 | 米ドル建て100% → 円安で上振れしやすい |
| オルカン | 通貨分散(ドル・ユーロ・円・新興国など)→ 為替影響は相殺されやすい |
近年は円安が進行しており、S&P500への投資は為替差益込みで実質利回りがさらに上がっている状態です。
ただし、今後円高に転じた場合はその分マイナス影響も受けやすくなるため、オルカンの通貨分散はリスク分散として有効と考えられます。
地域分散の有無がリターンに与える影響
オルカンとS&P500の大きな違いのひとつが「地域分散の有無」です。
S&P500は米国株のみに特化している一方で、オルカンは全世界を対象に地域分散されたインデックスです。
この分散の効果はリスク管理の観点で重要ですが、利回りの面では以下のような傾向があります。
| 指数 | 地域分散 | リターン傾向 |
|---|---|---|
| S&P500 | 米国100% | 高成長・高利回り・ボラティリティ大 |
| オルカン | 米国6割+先進国+新興国 | リスク分散型・利回りはやや控えめ |
実際、オルカンのパフォーマンスは米国市場の動きに大きく影響されます。
というのも、オルカンの時価総額の約60%はS&P500に含まれる米国株で構成されているためです。
つまり、オルカンを買う=米国を中心に据えつつ、ヨーロッパ・日本・新興国もカバーするという投資スタンスとなります。
GAFAMなど大型米国株の比率とインデックスへの影響
S&P500のパフォーマンスの強さは、GAFAM(Google、Apple、Facebook[現Meta]、Amazon、Microsoft)を中心とした米国の超大型グロース株の寄与によるものです。
2024年時点で、S&P500におけるGAFAM+NVIDIAなどの構成比は以下の通りです。
| 銘柄 | 構成比(S&P500) |
|---|---|
| Apple | 約7.0% |
| Microsoft | 約6.5% |
| Amazon | 約3.5% |
| NVIDIA | 約3.2% |
| Meta | 約2.3% |
これらわずか数銘柄で指数全体の20%超を占めているため、S&P500は一部企業の動きに大きく左右されます。
逆に、オルカンでは米国株のウエイトが6割あるとはいえ、ヨーロッパ・アジア・新興国の企業も含まれるため、成長企業への依存度がやや分散されています。
リターン重視ならS&P500、リスク分散を意識するならオルカンという考え方ができます。
新興国株を含むことのメリット・デメリット
オルカンにはS&P500にはない「新興国株」が含まれている点が注目されます。
その比率は全体の約10~15%程度で、中国・インド・ブラジル・南アフリカなどが代表的です。
メリット
-
将来的な人口増・経済成長の恩恵を受けやすい
-
分散によって一部先進国の不調を補える可能性がある
デメリット
-
政治・通貨リスクが高く、株価の変動も激しい
-
現時点ではパフォーマンスが先進国に劣る傾向がある
| 地域 | 年平均利回り(過去20〜30年) |
|---|---|
| 米国(S&P500) | 約10.5〜11% |
| 新興国(MSCI EM) | 約6.0〜7.0% |
現時点では新興国がオルカン全体のパフォーマンスを下げている構造になっていますが、将来的な成長ポテンシャルも内包しているため、投資家のスタンス次第で評価が分かれます。
過去の危機時に強かったのはどちらか?
リーマンショック(2008年)やコロナショック(2020年)のような金融危機の際、オルカンとS&P500のどちらが強かったかを見ることで、下落耐性を比較することができます。
リーマンショック時(2008年の下落率)
| 指数 | 下落率 |
|---|---|
| S&P500 | -37.0% |
| オルカン | -40.3% |
コロナショック時(2020年初〜3月末)
| 指数 | 最大下落率 |
|---|---|
| S&P500 | 約-34% |
| オルカン | 約-32% |
このように、危機時にはほぼ同様の水準で下落するが、回復力には差があることが分かります。
S&P500は米国の金融・ITセクター主導で急回復しやすいのに対し、オルカンは回復速度がやや遅れる傾向にあります。
ただし、地域分散によって一国の暴落に対する“クッション効果”がある点は見逃せません。
配当・信託報酬・コスト面の比較
最後に、投資で実際に重要なのが「運用コスト」と「配当の取り扱い」です。
コストは利回りに直接響くため、見逃せないポイントです。
| 比較項目 | S&P500 | オルカン |
|---|---|---|
| 信託報酬(投信) | 約0.093% | 約0.057%(最安値帯) |
| 配当利回り(参考) | 約1.3〜1.5% | 約1.5〜2.0% |
| 配当の扱い | 再投資型(投信) or 分配型(ETF) | 同様 |
信託報酬では、オルカン(eMAXIS Slim全世界株式など)がわずかに安いケースもあります。
配当利回りはほぼ同等〜ややオルカンが高い傾向にありますが、長期保有なら配当よりも再投資の効果が大きく影響します。
つまり、利回りだけでなく「実質的な手取りリターン」を考慮することが、インデックス投資成功のカギです。
30年スパンで見るインデックス選びの考え方
利回りだけでインデックスを選ぶべきか?
利回りの高さは重要な指標ではありますが、「利回り=正解」ではありません。
とくにインデックス投資は長期にわたって積み上げていくものなので、利回りだけでなく以下の観点も踏まえる必要があります。
-
自分の投資目的(資産形成?老後?教育資金?)
-
想定する投資期間(10年?30年?)
-
日常的な値動きへの耐性(下がっても動じないメンタル)
-
投資にかけられる時間・労力・関心度
たとえば、「多少の上下は気にせず、高成長を狙いたい」ならS&P500が向いていますし、「手堅く世界全体に分散して持ちたい」ならオルカンという選択もアリです。
利回りは“指標”であって、“最終判断”ではないという意識が大切です。
投資目的別に見るオルカン・S&P500の向き不向き
インデックスを選ぶ際、利回りと同じくらい重要なのが目的との相性です。
以下は、目的別におすすめされる傾向の一例です。
| 投資目的 | 向いているインデックス | 理由 |
|---|---|---|
| 老後資金の積立 | オルカン | 長期分散でリスク軽減しやすい |
| 教育資金・10年以内の資金 | S&P500 | 高成長で短中期でもパフォーマンスが期待できる |
| 初心者の資産形成 | オルカン | 1本で完結・為替分散もある |
| 米国株に信頼がある人 | S&P500 | 米国の成長に集中投資できる |
どちらが正しいかではなく、「どちらが自分に合っているか」で判断することが成功への近道です。
積立投資との相性がいいのはどっち?
積立投資(ドルコスト平均法)において重要なのは、以下の2点です。
-
長く続けやすい仕組みであること
-
値動きのある商品であること(=リターンの“揺れ”を活かす)
この視点で見ると、両者とも積立に向いていますが、性格は異なります。
-
S&P500:上下の変動が大きく、押し目買いが効きやすい → 複利効果が強く出る
-
オルカン:変動は控えめ、堅実に積み上がる → 継続しやすく、心が折れにくい
特に初心者や途中でやめるリスクがある人には、“続けられる指数”=オルカンの方が相性が良いという見方もできます。
長期投資における「売らない力」とは?
どれほど優れたインデックスでも、売ってしまっては意味がありません。
インデックス投資は「売らない力=継続力」があって初めて成果が出る投資法です。
そのためには、
-
相場が下がっても「また上がる」と思える指数を選ぶ
-
生活に支障が出ない金額で運用する
-
定期的なメンテナンス以外は“放置”するスタンス
特にS&P500は下落時のボラティリティが大きいため、「一時的に30%下落しても握っていられるか?」という視点が求められます。
その点、オルカンは分散が効いており、「全世界が同時にダメになることは少ない」という安心感があります。
インデックス選びは、“未来を信じ続けられる銘柄”を選ぶことでもあるのです。
オルカンは広範な分散投資を行っている一方で、短期的に下落する局面もあります。
→ オールカントリーが下落する理由と今後の対処法はこちらの記事で詳しく解説しています。
リスク許容度別におすすめできる組み合わせ
「S&P500かオルカンか」で悩んだときは、両方を組み合わせるという選択肢も有効です。
以下は、リスク許容度別におすすめできるポートフォリオの一例です。
| リスク許容度 | 組み合わせ比率(S&P500:オルカン) | 特徴 |
|---|---|---|
| 高め(攻めたい人) | 80:20 | 高成長狙い、米国集中リスクもある |
| 中程度 | 50:50 | バランス重視、値動きも分散 |
| 低め(安定志向) | 30:70 | 安定運用、世界経済全体に幅広く分散 |
このように、自分の性格や目的に応じて、一方に偏らせず「いいとこ取り」する戦略も検討の価値があります。
実際に積立した場合のシミュレーション比較
ここでは、30年間の積立投資を前提に、オルカンとS&P500に投資した場合のシミュレーションを比較してみましょう。
仮に毎月3万円を積み立て、以下の年平均利回りで運用した場合の結果は以下の通りです。
| インデックス | 年平均利回り | 元本(30年) | 複利運用後の資産 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 10.5% | 1,080万円 | 約7,360万円 |
| オルカン | 7.0% | 1,080万円 | 約3,540万円 |
※配当再投資・税金考慮なし
このように、年利3〜4%の差でも30年間積み立てれば倍以上の差が出ることがわかります。
ただしこの数値は“過去”のデータに基づくシミュレーションであり、将来の結果を保証するものではありません。
それでも、「長期×複利」の効果の大きさを理解するには非常に参考になります。
投資信託とETF、どちらで始めるべき?
オルカンやS&P500は、ETFと投資信託のどちらでも投資できますが、初心者には「投資信託」が扱いやすい傾向があります。
| 比較項目 | 投資信託 | ETF |
|---|---|---|
| 少額での積立 | ◎ 毎月100円〜可能 | △ 一括で買うのが基本 |
| 手続きの簡単さ | ◎ 自動積立・NISA対応 | △ 証券口座で都度買付 |
| リアルタイム性 | × 1日1回価格決定 | ◎ 株と同じように売買可 |
ETFは「売買の自由度」が魅力ですが、投資信託の方がNISAでの利用や再投資の自動化に対応しており、手間なく“積立しっぱなし”ができる点で人気です。
長期運用を前提とするなら、信託報酬の低い投資信託から始めるのがおすすめです。
NISA・iDeCoで活用するならどちらが有利?
新NISAやiDeCoを使うことで、運用益や配当の非課税メリットを最大化できます。
どちらの制度でも、オルカン・S&P500の投資信託は人気商品となっています。
以下は、目的別におすすめの使い分け方です。
| 目的 | 向いている商品 |
|---|---|
| 老後資産形成(iDeCo) | オルカン:長期分散向け、着実に積み上げられる |
| 中長期の資産成長(新NISA) | S&P500:成長重視、配当再投資で複利も期待 |
iDeCoは「60歳まで引き出せない」などの制限がありますが、税制メリットが非常に大きいため、積立額の大きい人ほど恩恵が強くなります。
一方、新NISAでは自由度が高いため、より積極的にS&P500で攻める運用も可能です。
途中でリスク資産を切り替えるときの考え方
投資を始めた後、「やっぱりオルカンからS&P500に切り替えたい」「逆にもっと分散したくなった」などと考えることもあるでしょう。
その場合、以下のようなポイントを意識して判断するのが大切です。
-
運用期間がまだ長いなら: リスクを取りやすく、S&P500への移行も検討余地あり
-
相場が上がって含み益が大きいなら: 利益確定を含めた一部売却・切り替えも戦略的
-
相場下落中に不安を感じているなら: 焦って切り替えず“そのまま継続”の方が損しにくい
重要なのは、感情で動かず、あらかじめ自分の「方針」と「期限」を決めておくことです。
インデックス投資は“動かない”ことが成果に繋がる投資法です。
よくある質問Q&A10選
Q1. オルカンとS&P500、どっちが平均利回りは高いですか?
A. 過去30年の実績ではS&P500の方が明確に高い利回り(年平均約10.5〜11%)を記録しています。
Q2. オルカンの利回りが低いのはなぜ?
A. 世界中に分散しているため、成長が鈍い国の影響も受け、米国単独より平均利回りは下がる傾向にあります。
Q3. 初心者にはどちらがおすすめですか?
A. オルカンは1本で分散が効いているため、初心者でも心理的負担が少なく続けやすいです。
Q4. 積立投資に向いているのはどっち?
A. どちらも積立向きですが、S&P500はボラティリティが大きいため、リスクを取りたい人に向いています。
Q5. 将来の資産形成を考えるとどちらが有利?
A. 高成長を重視するならS&P500、安定的に分散したいならオルカンが適しています。
Q6. 配当金はもらえますか?
A. ETFでは分配金が出るものが多いですが、投資信託では再投資型が主流です。
Q7. 新NISAではどちらが人気ですか?
A. 両方人気ですが、成長を狙う人にはS&P500、初心者にはオルカンが選ばれる傾向があります。
Q8. 米国株に偏りすぎるのが不安です。
A. その場合はオルカンを選べば、地域分散が効いて米国リスクの偏りを和らげられます。
Q9. 為替の影響はどう考えればいいですか?
A. S&P500はドル100%のため円安時に有利。オルカンは通貨分散でリスクがやや緩和されます。
Q10. 両方買ってもいいですか?
A. はい。半々や自分のリスク許容度に応じた比率で組み合わせるのも効果的です。
オルカンとS&P500の平均利回りを比較!30年スパンで選ぶべきインデックスとは?のまとめ
最後にこの記事のポイントをまとめました。
【あわせて読みたい関連記事】
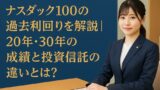


【本記事の関連ハッシュタグ】







