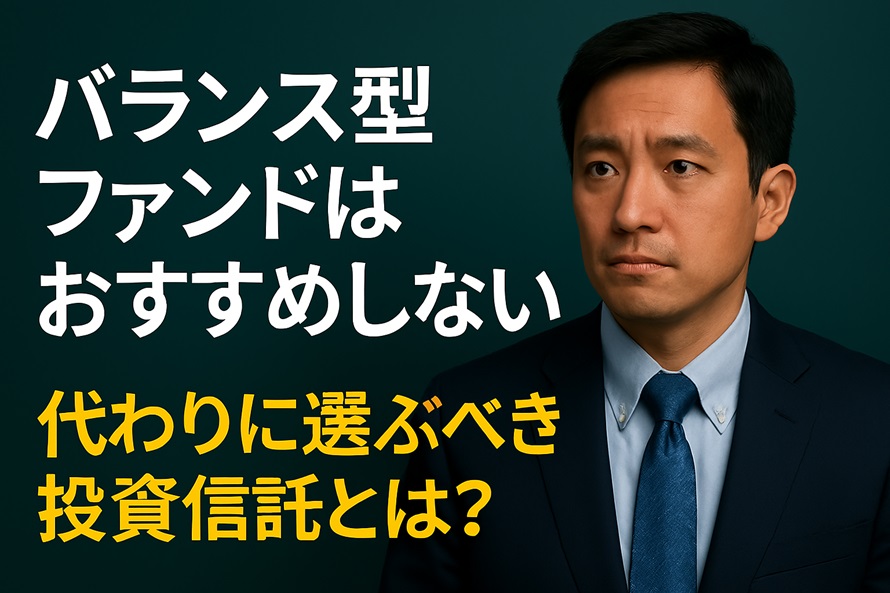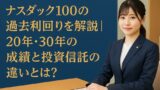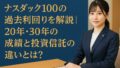本記事では、「バランス型ファンドはおすすめしない」と言われる理由を、具体的な構造やリスクとともに分かりやすく解説します。

一見すると便利そうに見えるこのタイプの投資信託ですが、実は柔軟性に欠けたり、長期的な成績が限定されやすいなどの課題もあります。投資信託を選ぶ際に重要なのは、「何が入っているか」だけでなく「なぜその構成なのか」を見極める視点。後悔のない資産形成のために、自分に合った投信選びのヒントをお届けします。
-
バランス型ファンドの基本構造と注意すべきポイント
-
なぜ「おすすめしない」と言われることがあるのか、背景を具体的に解説
-
インデックスファンドや低コスト投信など、代替となる選択肢の特徴
-
自分に合った投資信託を見極めるための考え方と判断基準
バランス型ファンドはなぜおすすめしない?注意すべき落とし穴
バランス型ファンドとは?仕組みと特徴をおさらい
バランス型ファンドとは、株式・債券・リート・海外資産など、複数の資産クラスを組み合わせて運用する投資信託です。
ひとつのファンドで「分散投資」ができることから、初心者向けの商品として広く紹介されています。
例えば、典型的なバランスファンドは次のような配分となっています。
| 資産クラス | 配分比率の例 |
|---|---|
| 日本株式 | 25% |
| 日本債券 | 25% |
| 海外株式 | 25% |
| 海外債券 | 25% |
このように“均等にバランス良く”資産を分散することでリスク軽減を狙うのが基本設計ですが、裏を返せば「常に同じ割合で持ち続ける」という制約も生まれます。
その結果、状況に応じた資産の入れ替えや最適化ができないというデメリットもあるのです。
投資初心者に選ばれがちだが、実は非効率な理由
初心者が最初に選ぶことの多いバランス型ファンドですが、必ずしも最適解とは限りません。
その理由は、「おまかせで楽に見えても、実は中身がコントロールできない不自由さ」にあります。
バランス型ファンドのよくある問題点は以下の通りです。
-
好調な資産クラスがあっても、その分配分が増えず成長を取りこぼす
-
不調な資産クラスも自動で再購入されてしまう
-
すべての資産が“そこそこ”に抑えられ、パフォーマンスが平凡
たとえるなら、「栄養バランスの良い定食」ではあるけれど、体調や目標(減量・増量)に応じた調整が利かない食事のようなものです。
投資においては「リスクを抑える」ことも大切ですが、必要以上に守りに入ることが長期的な成績を落とす原因にもなり得ます。
コスト構造に要注意!意外と高い信託報酬と手数料
バランス型ファンドは「1本で全部おまかせ」というイメージのせいか、コストについてあまり意識されていないことが多いです。
ですが実際には、複数のファンドを組み合わせている分、間接的なコストが上乗せされる構造になっている場合もあります。
以下はよくあるバランス型ファンドのコスト構造の例です:
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 信託報酬(表面) | 年率0.5〜0.8%程度が主流 |
| 内部ファンド費用 | 組み入れファンドごとに0.1〜0.3%上乗せされるケースも |
| 販売手数料 | 証券会社によっては2〜3%かかる商品も存在 |
つまり、実質の運用コストが1%を超えることもあるということです。
この点では、eMAXIS SlimシリーズやSBI・Vシリーズなど、インデックス型ファンドの低コストさが際立ちます。
バランス型を「初心者向け」として紹介する声がある一方で、長期で考えればコストの差が積み重なって大きな差となることも理解しておく必要があります。
資産配分が固定されており相場変動に対応しにくい
バランス型ファンドの最大の弱点の一つが「資産配分が固定されている」という点です。
どれだけ株式が上昇しても、債券が下落しても、基本的に自動リバランス(再配分)によって元の比率に戻されてしまいます。
たとえば2022〜2023年にかけての金利上昇局面では、債券価格が大きく下落しました。
このような時期においても、バランス型ファンドでは債券を自動的に買い増す仕組みになっており、下がる資産を買い続けるという非効率な動きをせざるを得ないのです。
また、特定の相場(たとえば株高・ドル安の局面)に集中投資したくても、バランス型ファンドでは柔軟に対応できません。
その結果、「資産は守れたけれど増えない」というジレンマに直面する投資家が多いのです。
4資産・8資産均等型の落とし穴とは?
バランス型ファンドの代表例としてよく紹介されるのが、「4資産均等型」や「8資産均等型」といったタイプです。
一見すると多様な資産に分散されていてリスクが抑えられているように見えますが、その中身とパフォーマンスには注意が必要です。
| タイプ | 主な構成内容 |
|---|---|
| 4資産均等型 | 国内株式・国内債券・先進国株式・先進国債券を各25% |
| 8資産均等型 | 上記に加えて新興国株式・新興国債券・国内REIT・海外REITなど |
たしかに「分散」は効いているのですが、分散しすぎることで“勝ち筋”が消えるという側面もあります。
特に8資産型は、新興国やREITなどボラティリティの高い資産も含まれているため、安定運用とは言い難い場面もあります。
また、配分比率が均等なために、本来伸びやすい資産の“伸び代”を自動的に削る仕組みにもなってしまうのです。
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
👉 4資産・8資産均等型バランスファンドは本当におすすめ?資産配分の意外な落とし穴
成績の良し悪しが分かりづらい構造になっている
バランス型ファンドは中身が多岐にわたるため、パフォーマンスの良し悪しが分かりづらいという欠点があります。
例えば、運用成績が悪いときに、
-
「どの資産が足を引っ張っているのか」
-
「どの部分がうまく機能しているのか」
といった分析がしにくいのです。
投資の本質は「学びと改善」です。
どの選択が良かったかを検証できなければ、経験値として蓄積されず、次に活かすことができません。
その点、バランス型ファンドは“全体として”の成績しか見えないため、投資家自身が成長しにくい構造でもあるのです。
各資産クラスがかえって足を引っ張るケースもある
バランス型ファンドのもう一つの問題は、異なる資産同士が“足を引っ張り合う”現象です。
例えば次のような状況が起こります。
-
国内株が大きく上昇しても、債券や海外REITが下落し、全体の成績が伸び悩む
-
成長性の高い資産に絞れないため、一部の好機を逃す
つまり、リスクを分散したつもりが、リターンも分散してしまうという結果に陥るのです。
これを避けるためには、「リスクを抑えつつ伸ばせる資産を自分でコントロールする」仕組みが必要になります。
それができないのが、パッケージ型のバランスファンドの限界です。
長期保有しても成果が出ないことがある理由
投資信託は一般的に「長期保有で成果を出す商品」と言われますが、バランス型ファンドではその常識が必ずしも当てはまりません。
その理由は次の通りです。
-
リスクを抑えすぎて“攻める局面”で利益が取れない
-
資産配分が機械的で、時代の変化に追いつけない
-
金利上昇や円高・円安など、マクロ環境の変化に弱い
実際に、10年以上保有してもインデックス型に比べてリターンが劣るというケースも報告されています。
つまり、「ほったらかしでいい」は誤解であり、運用目的に応じた投信を選ぶことが重要です。
投資教育の観点からもバランス型は学びが少ない
投資信託は「お金の勉強」としても有効な手段ですが、前述した通りバランス型ファンドはその意味で学びの機会が非常に限られた商品です。
理由はシンプルで、「中身がブラックボックス化しているから」。
以下のような基本的な感覚が身につきにくいのです。
-
株価と債券価格の関係性
-
為替がリターンに与える影響
-
セクターごとの成績差
これに対して、例えば「先進国株式インデックスファンド」や「米国債券ETF」などを組み合わせて運用する場合、資産ごとの値動きを体感でき、自分の判断力も育ちます。
長期で資産を育てるには、「投資そのものの理解」を深められる商品設計が望ましいのです。
代わりに選ぶべき投資信託と選び方のポイント
目的とリスク許容度に応じた投信選びが基本
バランス型ファンドが万人向けでないのは、投資の目的やリスク許容度は人によって異なるからです。
投信選びではまず、「自分が何のために運用するのか」「どこまでリスクが取れるのか」を整理することが重要です。
以下の表は、目的別に向いているファンドタイプをまとめたものです。
| 投資目的 | 向いている投信のタイプ |
|---|---|
| 資産を安定的に守りたい | 債券型インデックスファンド、短期国債ファンドなど |
| 資産を効率よく増やしたい | 株式型インデックスファンド、全世界株式型など |
| 積立で長期に育てたい | eMAXIS Slimシリーズ、SBI・Vシリーズなどの低コスト型 |
| 特定テーマに集中投資したい | セクター型・テーマ型アクティブファンドなど |
バランス型は「とりあえず1本買っておけば安心」的な位置づけで勧められがちですが、個々の投資目的に合っているかを確認せずに選ぶとミスマッチが起きやすいのです。
インデックスファンドとの違いを明確に理解する
バランス型ファンドと混同されがちなのが「インデックスファンド」です。
両者には明確な違いがあります。
| 比較項目 | バランス型ファンド | インデックスファンド |
|---|---|---|
| 資産構成 | 複数の資産クラスを混合 | 単一資産に連動(例:日経平均) |
| 資産配分の調整 | 基本的に固定 | 自分で組み合わせる必要あり |
| 投資家の関与度 | 少ない(自動でおまかせ) | 高い(構成やリバランスは自分次第) |
| コストの透明性・低さ | やや高い傾向 | 低コストで透明性が高い |
インデックスファンドは、たとえば「先進国株式」「米国債券」「TOPIX」など、市場全体の平均に連動するシンプルな設計です。
このため、中身が分かりやすく、コストも抑えられており、投資判断もしやすいという利点があります。
バランス型は「楽」ではあるものの、長期投資においては“理解できるものに投資する”という原則に照らして不利になる場面もあるのです。
「資産配分を自分で調整できる」ことの強み
バランス型ファンドを使わずに、自分で複数のインデックスファンドを組み合わせて資産配分をコントロールする手法は、“自作バランスファンド”とも呼ばれ、注目されています。
この方法には以下のようなメリットがあります。
-
自分のリスク許容度に応じて株式と債券の比率を変えられる
-
市場の動きに応じて、柔軟にリバランスができる
-
高利回りの資産クラスに比重を置くことでリターンを高められる
-
不調な資産を外して、シンプルな構成に見直すことも可能
たとえば、先進国株式:70%、先進国債券:30% のような配分で構成することで、パフォーマンスを意識した分散投資が可能になります。
このやり方は「難しそう」と感じる方もいますが、近年は証券会社の自動リバランス機能や積立シミュレーションも充実しており、意外と初心者でも簡単に始められます。
中身が見えるテーマ型・単体ファンドを選ぶ
バランス型ファンドでは中身が複雑で不透明なことが多いのに対し、中身が明確なファンドを選ぶことで投資判断がしやすくなります。
とくに近年は、特定の業界や企業に連動する“テーマ型”や“企業特化型”のファンドも増えてきました。
たとえば以下のような例が挙げられます。
-
トヨタグループ株式ファンド(国内大型企業グループに集中投資)
-
グローバルDX関連ファンド(テック系成長企業に着目)
-
クリーンエネルギー関連ファンド(脱炭素社会をテーマ)
こうしたファンドは、将来性のある分野に絞って投資したい方や、自分の関心分野に沿って投資したい人にとって魅力的な選択肢です。
実際に運用中の事例として、以下の記事ではトヨタグループ株式ファンドの戦略や実績を詳しく紹介しています。
👉 トヨタグループ株式ファンドは儲かる?中身と戦略を徹底解説
国内外株式・債券などの組み合わせ方の工夫
バランス型ファンドの代わりとして、自分で資産配分を設計する場合、株式・債券・REIT(不動産投資信託)などをどう組み合わせるかがポイントになります。
ここでは、目的別におすすめの組み合わせ例を紹介します。
| 投資目的 | 株式 | 債券 | その他(REITなど) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 成長重視(攻め型) | 70〜80% | 20〜30% | 0〜10% | 株式をメインに構成し、長期リターンを狙う |
| 安定運用(守り型) | 30〜40% | 60〜70% | 0〜10% | 値動きを抑えつつ、債券の安定感を活用 |
| バランス型(中庸) | 50% | 40% | 10% | 株・債券・REITを均等に近く配分 |
このように、自分のリスク許容度や投資期間に応じて資産を調整できることが、自作ポートフォリオの最大の利点です。
市場環境に合わせて、株式比率を増減させるなどの柔軟な戦略も可能です。
eMAXIS Slimなど低コストファンドの活用術
インデックス投資を基本に据えるなら、eMAXIS SlimシリーズやSBI・Vシリーズなどの低コストファンドは非常に有力な選択肢です。
以下は主要な人気ファンドとその特徴です。
| ファンド名 | 主な対象指数 | 信託報酬(年率) | 備考 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | MSCI ACWI | 約0.05775% | これ1本で全世界株式に投資可能 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | S&P500 | 約0.09372% | 米国株集中投資の王道 |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | CRSP US Total Market | 約0.0938% | バンガード連動で超低コスト |
これらのファンドは、長期積立に適しており、「コストを最小限に抑えつつ世界市場全体に投資」することが可能です。
結果として、複利の力を最大化し、時間を味方につけた堅実な資産形成が可能になります。
毎月分配型やターゲットイヤー型にも注意
「バランス型ファンドはやめたけど、他にも楽そうなファンドがある」と思いがちですが、“楽”を選んだ結果、さらに損をする商品も存在します。
代表的な例が以下のような投資信託です。
● 毎月分配型ファンド
-
毎月分配金がもらえるのは魅力的に見えるが、多くは元本の取り崩しで“見せかけの利益”を演出
-
手数料が高く、長期で見るとトータルリターンはマイナスになるケースも多い
● ターゲットイヤー型ファンド
-
一見、将来の目標時期に合わせて資産配分を調整してくれる便利な商品
-
ですが、中身はかなり保守的でリターンが非常に低い傾向にある
-
設定されたターゲットイヤー以外の使い方をすると、本来の設計が機能しない
自動積立と定期リバランスの組み合わせが有効
バランス型ファンドを避けて自分で複数の投資信託を組む場合でも、運用を「ほったらかし」にすることはできません。
そこで活用したいのが、自動積立と定期的なリバランスです。
-
自動積立:証券会社で毎月一定額を設定すれば、感情に左右されず継続できる
-
リバランス:半年〜1年ごとに資産配分の比率を見直し、当初のバランスに戻す作業
例えば、「先進国株式70%+先進国債券30%」というポートフォリオを組んだ場合、株式が大きく上昇すると構成比が80%近くになってしまうことがあります。
このまま放置するとリスクが高まるため、債券を買い増して元の70:30に戻す=リバランスが必要なのです。
最近では、SBI証券や楽天証券でも自動リバランス機能を備えたツールやサービスが用意されており、初心者でも無理なく実践できます。
積立NISAや新NISA制度をうまく使った投信戦略
2024年から開始された新NISA制度は、非課税枠の拡大と柔軟な積立戦略によって、長期資産形成をより加速させる制度となっています。
この制度を使いこなすことで、バランス型ファンドよりも高効率な資産形成が可能になります。
| 制度名称 | 年間投資枠 | 対象ファンドの特徴 |
|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 年120万円まで | 低コストのインデックスファンド中心 |
| 成長投資枠 | 年240万円まで | アクティブファンド・ETF・個別株など広範囲 |
これにより、たとえば以下のような使い分けが可能です。
-
つみたて投資枠では、eMAXIS Slimシリーズで安定積立
-
成長投資枠では、テーマ型やETFで機動的に攻める
バランス型ファンドは、構成や成長性に限界がある一方、新NISAでは“より伸びる商品”を非課税で効率よく積み立てるチャンスが得られます。
よくある質問Q&A10選
Q1. バランス型ファンドって、初心者でも使いやすい商品ですか?
A. 1本で複数の資産に分散できるのは便利ですが、柔軟性がないため、運用に慣れてきた人ほど物足りなさを感じることがあります。
Q2. バランス型ファンドが選ばれる理由と、その注意点は?
A. 手軽さが魅力ですが、相場に応じた調整ができない・コストが割高になりやすいといった点に気をつけましょう。
Q3. 投資信託は自分で組み合わせて持ったほうがいいのでしょうか?
A. 自由度は高くなります。資産配分を自分で考えられる人なら、単体のインデックスファンドを組み合わせる方法のほうが理にかなっています。
Q4. コスト面で見ると、どんな投資信託が優位ですか?
A. 年率0.1%未満の信託報酬を持つインデックスファンドは非常にコスト効率が良く、長期運用に向いています。
Q5. バランス型ファンドはおすすめしない理由はありますか?
A. 相場環境に応じた柔軟な調整ができない点や、長期投資においてリターンが限定されるため、おすすめしないことが多いです。
Q6. 自分で資産配分を考えるのが不安です。何から始めればよいですか?
A. 株式と債券の2種類から始めてみるのが良いでしょう。少額の積立から運用を学ぶ方法もあります。
Q7. 投資信託で資産を増やすにはどんなポイントが大事ですか?
A. 長期積立・低コスト・分散投資の3つが基本です。自分のリスク許容度に合った商品を選ぶことも欠かせません。
Q8. 市場環境が悪い時はどうすればよいですか?
A. 焦って売却せず、積立を続けることが結果的に平均取得単価を下げ、リターン改善に繋がります。
Q9. 投資信託の選び方がわからないときはどうすればいいですか?
A. 信託報酬の安さ・投資対象・過去の成績・運用方針などを比較しつつ、必要に応じてファイナンシャルプランナーに相談するのも一つの方法です。
Q10. バランス型ファンドは他のファンドと比べてリスクが高いのですか?
A. 一見リスクが低いように感じますが、過去のパフォーマンスや運用方針をよく調べずに選ぶと、思ったよりリスクが高くなることもあります。
バランス型ファンドはおすすめしない?代わりに選ぶべき投資信託とは?のまとめ
最後にこの記事のポイントをまとめました。
【あわせて読みたい関連記事】



バランス型ファンドではなく世界株に100%投資するインデックスファンドを検討したい方へ:→ オールカントリーがなぜ下落するのか?不安への対処法を解説
【本記事の関連ハッシュタグ】