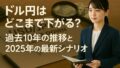本記事は、高配当株を選ぶうえで「買ってはいけない」とされる銘柄の特徴を、実例とともに深掘りしていきます。
利回りが高くても安心とは限らず、やめとけと警鐘を鳴らされる株式には共通点があります。
ランキング上位に登場する意外な銘柄や、インド株の注意点など、初心者が見落としやすいポイントも徹底的に解説しました。
高配当株投資で後悔しないために、避けるべき視点をしっかり押さえておきましょう。
- 📌買ってはいけない高配当株の見分け方がわかる
- 📌やめとけと言われる銘柄の共通点を理解できる
- 📌インド株を含む高配当株の注意点が整理できる
- 📌初心者が避けるべき株式投資の落とし穴が学べる
買ってはいけない高配当株とは?
高配当株でもおすすめしない理由とは?
高配当株は一見魅力的に見えますが、すべての銘柄が「安心して保有できる」とは限りません。
実際には、配当利回りが高すぎる企業には注意すべき理由があります。
結論から言うと、「配当の持続性」が疑わしい銘柄ほど、買ってはいけない高配当株に該当するのです。
高配当を維持するには、企業の利益が安定的に確保されていなければなりません。
ところが、業績が悪化しても配当だけを高く維持している企業は、財務を圧迫していたり、近い将来に減配する可能性が高くなります。
株主に一時的に配当で還元して株価を支えようとする動きは、投資家にとって危険信号とも言えます。
このような銘柄を選んでしまうと、配当収入どころか株価下落や減配による損失で「トータルでマイナス」になる可能性があります。
高配当という表面的な数字だけで判断するのではなく、配当余力や経営状況までしっかり見極める必要があります。
配当利回りだけで選ぶのは危険?
配当利回りが高いと、つい「お得に見える」ものですが、投資判断を利回りだけで決めるのは非常に危険です。
配当利回りが極端に高い場合、裏には「株価が大きく下がっている」という事実が隠れているケースが多くあります。
たとえば、株価が1,000円から500円に半減した企業が、そのまま1株あたり50円の配当を維持していれば、表面的な配当利回りは10%となります。
ですが、株価が下がった背景には業績悪化や将来への懸念がある可能性が高く、将来的に減配や無配に転じるリスクも小さくありません。
また、初心者の方がやりがちなのが「スクリーニングで配当利回り上位を並べて買う」という方法です。
これはあくまで入り口にすぎず、企業の配当方針・財務体質・利益成長性を見ずに購入してしまうと、“高配当”が“高リスク”に化けてしまうことがあります。
配当利回りはあくまで“結果”であり、将来も継続できる“配当の質”こそが重要なのです。
株価下落リスクが大きすぎる銘柄の特徴
「高配当株=値下がりしにくい」と思われがちですが、実はその逆で、配当狙いで買った銘柄ほど大きな株価下落に巻き込まれるリスクがあります。
特に注意すべきは、以下のような特徴を持つ銘柄です。
| 特徴 | リスク内容 |
|---|---|
| 景気の影響を強く受ける(海運・鉄鋼など) | 業績の浮き沈みが激しく、配当も不安定 |
| 一時的に業績が急回復している | 翌期以降の業績悪化で減配の可能性がある |
| 財務が脆弱(自己資本比率が低い) | 無理な配当維持で資本が減少し、株主価値が下がる |
| 特定事業への依存が大きい | 業界全体の逆風で企業全体が一気に傾くこともある |
たとえば、2021〜2022年にかけて好調だった日本の海運株(例:日本郵船・商船三井など)は、2023年にかけて業績が減速し、株価が大幅に下落しています。
配当も減配となり、高配当を期待していた投資家の中には含み損を抱えてしまったケースも少なくありません。
高配当だからといって安心して保有するのではなく、「今の配当は本当に続くのか?」という視点を持つことが何より重要です。
高配当なのにやめとけと言われる理由
高配当株の中には、見かけの利回りが高いにもかかわらず、投資家の間で「やめとけ」と警告される銘柄が存在します。
その理由の多くは、「持続可能性」と「業績の不透明さ」に起因しています。
まず、やめとけとされる典型的なケースは「減配リスクの高い企業」です。
表面的な利回りが6〜8%あっても、業績が悪化していれば、次期には減配または無配に転落する可能性があります。
減配が発表された途端、株価は暴落し、投資家は配当も株価も同時に失うことになります。
また、事業内容が不安定な企業も要注意です。
たとえば一時的な資源高で利益が急増したエネルギー関連企業や、景気の波をもろに受ける海運・建設などは、1~2年単位で業績が激しく変動します。
こういった企業が配当を増やすと、一見魅力的に映るものの、実態は“一瞬の輝き”で終わる可能性があります。
つまり、「高配当=安定」ではなく、「高配当=高リスク」であることを忘れてはいけません。
利回りだけで飛びつかず、業績の裏づけや将来の配当継続性を見極める視点が必要です。
高配当優良株と呼ばれる銘柄の落とし穴
“優良株”という響きは安心感を与えますが、高配当かつ優良とされる銘柄にも見逃せない落とし穴があります。
とくに初心者は「上場企業で有名だから大丈夫」といった安心感だけで投資してしまいがちです。
たとえば、財務体質が健全で知名度もある大企業であっても、「過去の栄光」に頼った経営を続けている企業はあります。
こうした企業は、新たな成長分野に投資せず、手元資金でとりあえず配当を出しているというケースも少なくありません。
また、「優良企業が配当を維持してくれる」と信じて長期保有を前提にしていると、突然の経営方針転換や業績悪化により、減配や配当方針の見直しに直面するリスクもあります。
実際、鉄鋼・化学・通信といった安定業種とされる分野でも、2023年以降で減配に転じた銘柄は複数確認されています。
“優良”とされる背景にどんなリスクが潜んでいるのかを、自分で見抜けるようになることが、失敗しないための第一歩です。
一時的な高配当に惑わされない見極め方
高配当銘柄に投資する際に最も重要なのは、「それが一時的な高配当なのか、持続的な高配当なのか」を見極めることです。
ここを見誤ると、スクリーニング上は魅力的に見えても、結果的に“地雷銘柄”を掴んでしまうことになります。
見極めに役立つポイントは以下の通りです。
| チェック項目 | 見るべき数字・資料例 |
|---|---|
| 配当性向が高すぎないか | 配当性向70%超は注意 |
| 売上や利益が安定しているか | 3〜5年の営業利益推移を確認 |
| 業種特有の景気敏感性が強いか | 海運・鉄鋼・不動産などは周期を要チェック |
| 自己資本比率や利益剰余金の水準 | 財務が弱い企業は長期投資に不向き |
特に「配当性向」は要チェック項目です。企業が稼いだ利益のうち、どれだけを配当に回しているかを示す指標ですが、これが80%や100%を超えていると、無理に配当を出している可能性が高くなります。
また、直近1〜2年だけ業績が良く、その数字をベースに高配当を出している企業も注意が必要です。
そうした銘柄は景気が一巡すれば急激に業績が悪化し、配当が維持できなくなるリスクがあるため、短期の数字だけではなく、過去数年の安定性を見る視点が重要です。
減配リスクを見抜けない初心者の失敗例
高配当株に投資する際、初心者が特に見落としがちなのが「減配リスク」です。
表面的な配当利回りに魅かれて購入しても、数ヶ月後に減配発表があり、想定していたリターンが得られないばかりか、株価まで大きく下落することは珍しくありません。
たとえば、ある企業が年間80円の配当を継続していたとしても、業績悪化が続き、急に40円へ減配されれば、配当利回りは半減。加えて、配当期待で買われていた株価も下落し、ダブルパンチを受ける形になります。
初心者の失敗として多いのは、以下のような傾向です。
- 配当性向が高すぎる(目安:70%以上)銘柄を見落とす
- 営業利益の成長鈍化に気づかない
- 減配の兆候がIR資料に出ているのに確認しない
- 一時的な業績回復で配当が上がった銘柄を安易に買う
減配リスクを避けるためには、過去3〜5年の配当推移と利益推移をセットで確認し、企業がどれだけ“余裕を持って”配当を出しているかを見極める必要があります。
買ってはいけない高配当株ランキングと見分け方
買ってはいけない株ランキング最新版
ここでは、さまざまな投資家の意見や市場評価、配当持続性、業績安定性などを総合して、2025年3月時点で「買ってはいけない」と言われている高配当株をいくつかピックアップしてご紹介します。
| 銘柄名 | 業種 | 表面利回り | 懸念点・注意点 |
|---|---|---|---|
| 日本郵船 | 海運 | 約6.5% | 減配が発表されており、今後も業績依存度が高い |
| 商船三井 | 海運 | 約6.2% | 景気敏感・配当変動が激しく、長期保有には向かない |
| INPEX | 資源 | 約5.8% | 原油価格次第で業績が大きく変動、長期安定性に不安 |
| あるインド株ETF | 海外ETF | 約7.0% | 為替・政策リスクが大きく、税制面の理解も必要 |
| 野村不動産HD | 不動産 | 約5.5% | 金利上昇局面では利回り維持が困難になる可能性がある |
※上記の利回りは2025年3月時点の概算であり、今後の業績・方針次第で変動します。
「ランキング」とはいえ、完全に避けるべきという意味ではなく、「目的と戦略に合わないなら避けるべき銘柄」という視点で見ることが大切です。
高配当株 日本郵船は本当に危険なのか?
日本郵船は、配当利回りが非常に高いことで注目される代表的な海運株の一つです。
2021年〜2022年にかけては、コロナ禍に伴う物流逼迫や運賃高騰の影響で業績が急拡大し、配当金も過去最高水準に達しました。
ですが、2023年以降の市況変化により業績が急減速し、それに伴い大幅な減配が発表されました。
このように、一時的な業績上昇に支えられた“過去の高配当”に引きずられると、今後もその水準が続くと勘違いしてしまい、投資判断を誤ることがあります。
また、海運業は国際情勢や原油価格、為替、景気循環など多くの外部要因に影響を受けやすく、収益と配当の安定性に欠けるという特性があります。
日本郵船も例外ではありません。
配当利回りの高さだけを理由に選ぶのではなく、「今後もその配当を維持できるのか?」という視点を持たないと、想定外の減配や株価下落に巻き込まれる可能性が高くなります。
長期保有に不向きな大型優良株の実態
「大型優良株」と聞くと、長期保有に適していそうなイメージを持たれるかもしれません。
たしかに資本金や売上高が大きく、一定の信頼性がある企業も多いですが、すべてが長期投資に向いているわけではありません。
たとえば、設備投資のサイクルが重く利益率が不安定な企業や、成熟産業に属しており成長性に欠ける企業などは、今後の配当維持や株価の上昇余地に不安が残ります。
加えて、伝統的な業種では、新規事業への投資に消極的な傾向も見られ、配当を出しながらも企業体力が徐々に衰えていくケースも存在します。
また、株主還元を優先するあまり、自己資本の健全性が低下している企業も注意が必要です。
配当利回りが高いからといって、無理な配当政策を続けていると、いずれ減配や株主価値の毀損につながります。
したがって、「大型=安定・安全」という思い込みを捨て、個別企業の財務・業績推移・配当方針を見極める目を持つことが、長期保有での失敗を防ぐ第一歩です。
インド株にも高配当株の落とし穴がある?
近年、成長性の高さから注目されているのがインド株です。
中でも一部のインド株やETFでは、配当利回りが5〜7%程度と高水準に見えるものもあり、「日本株よりも利回りが良い」と感じる投資家も多いようです。
ですが、インド株にも明確な落とし穴が存在します。特に注意したいのは以下の3点です。
- 為替リスクの大きさ:ルピーと円の変動によって、配当や評価額が減少する可能性があります。円高が進めば、せっかくの配当も相殺されてしまうことがあります。
- 税制や分配の不透明さ:現地で課税された後に、日本での課税が二重にかかる可能性があるなど、税務面での理解が不十分だと手取りが少なくなることもあります。
- 情報収集の難しさ:企業の財務状況や配当方針が日本企業ほど開示されておらず、個人投資家が正確に判断するのは難易度が高いです。
高配当株の「配当性向」が異常な銘柄の注意点
高配当株を選ぶ際に最も見落とされがちなのが「配当性向」です。
配当性向とは、企業が得た純利益のうち、どれだけを株主への配当に回しているかを示す指標で、健全な水準は30〜50%程度が一般的です。
この指標が70〜100%、あるいはそれ以上の水準にある場合、企業は「無理をして配当を出している可能性」があります。
つまり、将来的に減配リスクが非常に高いということです。
以下に、配当性向の目安とリスクレベルをまとめました。
| 配当性向 | 水準の目安 | リスクの見方 |
|---|---|---|
| 〜50% | 健全 | 利益の中で無理なく配当している |
| 51〜80% | 注意 | 業績悪化時に減配の可能性あり |
| 81%〜 | 高リスク | 継続困難な水準、減配や財務悪化懸念 |
例えば、ある企業が赤字にもかかわらず、前年の利益水準をもとに高額配当を維持しているとすれば、それは一時的な見せかけの還元であり、持続的とはいえません。
スクリーニングで高利回りの銘柄を見つけたときこそ、「配当性向はいくらか?」を必ずチェックする癖をつけることが、失敗しない高配当株選びの基礎です。
株式投資で初心者が避けるべき高配当株とは?
初心者が高配当株に挑戦すること自体は悪いことではありません。
むしろ、インカムゲイン(配当収入)を得られる戦略は、資産形成の一手段として有効です。
ですが、「避けるべき高配当株」をきちんと見分ける力がないまま投資を始めてしまうと、逆に資産を減らすリスクが高まります。
特に初心者が避けるべき高配当株には以下のような特徴があります。
-
配当利回りが極端に高く(7%超)、業績が安定していない
-
業種特有のリスクが大きく、外部環境に左右されやすい
-
自己資本比率が低く、財務基盤が脆弱
-
配当性向が高すぎて継続性に不安がある
-
投資家向け情報が少なく、IR開示が不十分
「高配当=優良」という思い込みは非常に危険です。
企業全体をきちんと調べずに“利回り”だけで購入する行動は、まさに初心者が最も避けるべき落とし穴のひとつです。
まずは利回りに惑わされず、業績・財務・配当方針の3点をしっかり確認したうえで、自分の資産に見合った無理のない投資を行いましょう。
高配当株でも永久保有すべきでない理由
「配当をもらい続けられるなら、ずっと持っていればいいのでは?」
こう思う方も多いですが、実は高配当株ほど“永久保有”に向かないケースも多く存在します。
理由の一つは、業績や外部環境によって配当方針が変わりやすい点にあります。
たとえ一時的に高い配当を出していても、数年後に減配や事業縮小が起これば、利回りは低下し、株価も下落します。
また、以下のような企業も“永久保有に不向き”とされます。
さらに、配当目的で保有していたにもかかわらず、株価が大きく下がっても「配当があるから手放せない」という心理に陥ると、機会損失や資産効率の低下につながるおそれがあります。
高配当株でも、一定の目標に達したら利確する、もしくは業績が悪化したら見直すなど、「売却タイミングを明確に決めておく」ことが、安定運用には不可欠です。
株で10パーセントルールを無視していないか?
「10パーセントルール」とは、購入価格から株価が10%下落したら売却するというリスク管理の考え方です。
特に高配当株ではこのルールを軽視してしまう投資家が多く、結果として損失が拡大する原因となります。
「配当があるから、多少下がっても大丈夫」と考えがちですが、株価が20%、30%と下がれば、配当金で得られる利益を大きく上回る損失を被ることになります。
たとえば、以下のようなケースです。
-
購入価格:1,000円
-
配当:50円(5%利回り)
-
株価が800円まで下落 → 含み損200円(20%)
-
配当で10年かけても損失を取り返せない可能性あり
このような状況を避けるには、自分の中で損切りライン(例:10%)を設定しておくことが極めて重要です。
高配当株であっても「配当があるから安心」という思い込みは、リスクを放置することと同義です。
冷静なルール設定と、機械的な実行力が、長期で生き残る投資家の共通点です。
曜日によって株を買ってはいけないって本当?
一部の投資家の間では、「株は月曜に買ってはいけない」や「金曜に買うのは避けるべき」といった話がまことしやかに語られます。これらは必ずしも根拠のない話ではありません。
実際、米国株や日本株の過去統計では、週明けの月曜はネガティブなニュースが反映されやすく、下げやすい傾向があります。
また、金曜日に株を買うと、週末の地政学的リスクや企業のネガティブ発表で週明けに急落するというパターンも、一定の確率で確認されています。
高配当株に関しても同様で、「週末前に配当落ちを避ける売りが出やすい」「月曜は買い手が手控えやすい」といった需給の偏りが、株価に影響を及ぼすことがあります。
とはいえ、「曜日だけで投資判断する」のは本末転倒です。
大切なのは、曜日の傾向を知った上で、自分のタイミング・資金管理・投資目的に合致しているかを判断材料にすることです。
曜日の迷信に引っ張られ過ぎず、冷静な戦略を立てることが、ブレない投資行動に繋がります。
高配当株なのにおすすめしない共通点
一見魅力的に見える高配当株でも、複数の共通点がある場合は「おすすめしない銘柄」として判断すべきです。
ここでは、特に注意すべき共通項を整理しておきます。
❌ おすすめしない高配当株の共通点
- 配当利回りが7%を超えており、異常値になっている
- 配当性向が80%を超えていて、財務に無理がある
- 業績が右肩下がりで将来性が見えない
- 株価が大きく下落した結果、利回りだけが高く見えている
- 財務基盤が脆弱で自己資本比率が低い
- 事業内容が時代にそぐわず、成長投資をしていない
- 企業IRが不十分で、投資家への説明責任を果たしていない
このような共通点をいくつも持っている銘柄は、高配当であっても“地雷株”となる可能性が高く、中長期で見ればむしろ資産を減らす要因となるおそれがあります。
高配当株を選ぶ際は、「利回りが高い」ではなく「安心して長く持てるかどうか」を基準にして判断することが、安定運用の鍵となります。
買ってはいけない株80銘柄の真相を検証
「買ってはいけない株80銘柄」という言葉は、ネット上で広く流布されている“要注意企業リスト”のような存在ですが、その多くは明確な基準がなく、一部は極端な印象操作や古いデータに基づいたリストであることも少なくありません。
では、なぜこうしたリストが注目されるのでしょうか?その背景には以下のような投資家心理と現実があります。
「80銘柄」は何を根拠に作られているのか?
こうしたリストの作成元は明らかにされていないことが多く、根拠も曖昧です。
典型的な掲載理由は以下の通りです。
-
業績が長期的に赤字
-
財務が極端に悪化している(債務超過など)
-
減配・無配を繰り返している
-
ストップ安や急落を経験している
-
株主優待や配当の改悪があった
-
急騰後に大きく値下がりし、回復の兆しがない
中には“かつて悪かった”という理由だけで載せられている企業もあり、現在の財務・業績状況と乖離しているケースも多くあります。
リストに実際に載っている代表的な銘柄と現在の状況
| 銘柄名 | 当時の評価 | 現在の状況(2025年時点) |
|---|---|---|
| レオパレス21 | 累積赤字・経営再建中 | 収益回復傾向だが黒字定着までは時間が必要 |
| シャープ | 債務超過・赤字継続 | 業績不安定、配当は出していない |
| そーせい | 赤字続き、開発型企業 | 業績ボラ大きく、投資家の評価は二分 |
| 日本郵船 | 配当利回り高騰で一時注目 | 減配済み、株価調整中 |
| タカタ(過去) | 経営破綻 | 現在は存在しない(過去のリスク象徴) |
このように、リストに挙げられた銘柄の“その後”を見てみると、一部は回復基調にあるものの、多くは依然として慎重な判断が必要な状態にあることがわかります。
リストに盲目的に従ってはいけない理由
「80銘柄リストに載っている=買ってはいけない」ではありません。
問題は、その企業が今もなおリスクを抱えているか、それとも改善傾向にあるかです。
たとえば、
- 経営再建中でコスト削減・黒字化が進んでいる
- 経営陣が刷新され、事業構造が見直されている
- 財務改善により配当復活を目指している
このような兆しがあれば、逆に割安で仕込める“再評価待ち銘柄”である可能性もあります。
つまり、「買ってはいけない株80銘柄」という言葉を鵜呑みにするのではなく、“なぜ避けるべきか”を理解し、“今はどうなのか”を自分で確認する姿勢こそが、情報に振り回されないために必要なのです。
よくある質問Q&A10選
Q1. 高配当株ならどれも長期保有向きですか?
A. いいえ。配当の持続性や業績安定性が欠ける場合は長期保有に不向きです。
Q2. 買ってはいけない高配当株にはどんな特徴がありますか?
A. 高すぎる配当性向、赤字体質、景気敏感業種などが共通点です。
Q3. 高配当株で損をするのはどんなときですか?
A. 減配・株価下落が同時に起きると、配当以上の損失になることがあります。
Q4. 初心者が避けるべき高配当株はありますか?
A. 財務が脆弱で情報開示の少ない企業は特に初心者には不向きです。
Q5. 高配当株の安全性はどう判断すればよいですか?
A. 配当性向・業績推移・自己資本比率などをセットで確認しましょう。
Q6. 「買ってはいけない株80銘柄」は信じてよいですか?
A. 一部は妥当ですが、鵜呑みにせず根拠を確認してから判断しましょう。
Q7. インド株の高配当ETFはおすすめですか?
A. 為替・税制・情報の壁があり、リスクを理解した上で投資判断が必要です。
Q8. 永久保有すべき高配当株とは?
A. 財務安定・配当持続性・将来の成長性をすべて備えた銘柄に限ります。
Q9. 高配当株はいつ買えばいいですか?
A. 業績好調時よりも、一時的な調整時に買う方がリスクを抑えられます。
Q10. 高配当株はNISAで買うべきですか?
A. 税金面のメリットが大きいため、NISAとの相性は良好です。
おすすめしない!?買ってはいけない高配当株ランキングをご紹介!のまとめ
【本記事の関連ハッシュタグ】