
本記事は、「お金に困ってない人の特徴が気になる」「貯金だけで本当に大丈夫?」と感じている方に今後お金に困らないためのマインドや方法を詳しく解説していきます。

資産運用や投資に前向きな人の習慣、リタイア後の備えに成功している人の思考パターンには共通点があります。今のうちに何を意識すべきか、貯蓄との違いや行動のヒントを交えながら具体的にお伝えしていきますので是非参考にされて下さい。
-
お金に困ってない人の特徴と共通する生活習慣がわかる
-
貯金と投資のバランスの取り方が理解できる
-
資産運用を始める際の考え方や行動のコツが学べる
-
リタイア後に向けた貯蓄・準備の重要性がつかめる
お金に困ってない人の特徴とは?
お金に余裕がある人の見た目や言動
お金に困っていない人は、見た目や振る舞いにもその余裕が表れています。
ブランド品を身に着けていることよりも、身なりが清潔で落ち着いた雰囲気を持っていることが特徴的です。

服や持ち物は必ずしも高級品ではなく、品質や機能性を重視して選ばれている傾向があります。
また、言葉遣いも穏やかで、人との会話に焦りがありません。
「時間にゆとりがある=経済的にも余裕がある」ことが見た目や言動ににじみ出ているのです。
さらに、無駄遣いや衝動買いに走らない冷静さも共通点といえるでしょう。
実はお金がない人の特徴とは?
見た目が派手だったり、財布の中にいつも現金がたくさん入っていたりしても、必ずしも経済的に安定しているとは限りません。
実はお金がない人ほど、見栄や周囲の評価に敏感で「豊かに見せたい欲求」にお金を使ってしまいがちです。
また、家計の管理が苦手な人も多く、「収入=使っていいお金」と考えがちで、支出を抑える意識が希薄です。
クレジットカードをリボ払いに頼る、貯金ゼロのまま生活水準を上げるなど、目先の快適さを優先する傾向が見られます。
表面的な印象に惑わされず、実際の家計管理や資産形成の習慣に注目することが重要です。
お金がない人に共通する口癖と行動
「どうせ自分には無理」「お金なんてあっても使っちゃう」など、自信や計画性のなさが口癖に表れることがあります。
こうした発言は、お金の問題を“自分の外”に原因があると考える傾向の表れです。
行動面では、コンビニでのちょこちょこ買いや、タイムセールだからと不要な物まで購入するなど、計画性のない支出が多いのが特徴です。
貯金や投資といった未来のための行動よりも、「今だけ得したい」気持ちが強く、結果としてお金が残りません。
また、収入が増えても支出が同じペースで増える「生活水準の引き上げ」も、貯まらない人に多く見られる現象です。
お金が貯まる人と貯まらない人の違い
お金が貯まる人とそうでない人の違いは、収入額の差よりも“使い方の習慣”にあります。
お金が貯まる人は、収入の一部を「先取り貯金」したり、固定費を定期的に見直したりするなど、お金を守る行動を当たり前のように継続しています。
また、財布の中身や家計簿を日常的に把握しており、使途不明金が少ないのも特徴です。
一方で、貯まらない人は「余ったら貯めよう」「何となく節約している」という感覚に頼っており、お金の流れをコントロールできていないケースが多く見られます。
継続的に資産を増やすためには、収入の大小よりも、日々の習慣の積み重ねが何より大切なのです。
貧乏な人の性格に共通する落とし穴
貧乏から抜け出せない人には、ある共通した“思考の癖”があります。
そのひとつが「短期的な快楽志向」です。
たとえば、日々のストレス発散として無計画な買い物を繰り返したり、将来の備えより“今が楽しければいい”という価値観でお金を使ってしまったりします。
また、自己投資や学びへの意識が低いのも特徴のひとつです。
新しい知識やスキルへの関心が乏しく、収入を上げるための努力を後回しにする傾向があります。
さらに、「お金の話をするのは卑しい」といった価値観に縛られ、金融リテラシーを身につけようとしないケースも少なくありません。
考え方の柔軟性がないこと=金銭的なチャンスを遠ざける要因となっているのです。
お金に困ったことがない人の生活習慣
お金に困らない人には、共通する“見えない習慣”があります。
それは、表面的な節約よりも、支出に優先順位をつけ、価値あるものにだけお金を使う判断力です。
たとえば、月の初めに「今月の予算」を決め、余ったら貯金ではなく、「最初から貯める金額を決めておく」など、意識ではなく仕組みで資産管理をしています。
また、健康維持や人間関係にお金と時間を投資しており、結果として医療費や孤立による出費を減らす“予防的なお金の使い方”が習慣化されています。
生活全体を通じて、「選択」と「継続」の判断基準を持っていることが、長期的な経済的安定につながっているのです。
金がたまらない人に見られる思考パターン
「今の収入では貯金なんて無理」「投資はお金持ちがするもの」など、お金に対する“思い込み”が資産形成のブレーキになっている人は少なくありません。
特に、「収入が増えれば自然に貯まる」と考えている人は要注意です。
収入が増えても支出も同じように増える“ラットレース”に陥るケースが非常に多いのです。
このタイプの人は、手元にお金があるとつい使ってしまう「財布のゆるさ」があり、“お金がある=使っていい”と解釈してしまう思考傾向が見られます。
根本的に必要なのは、「お金の使い方に意志を持つこと」。
つまり、意識的にお金に役割を与える習慣を作ることが、長期的な資産形成の第一歩となります。
お金に余裕がある人の習慣的な行動とは?
経済的に余裕のある人は、必ずしも「収入が高い人」とは限りません。
共通しているのは、お金に対する“継続的な関心”と“学び続ける姿勢”を持っている点です。
例えば、毎月資産状況を確認し、不要な支出を削減したり、目的に応じて投資商品の見直しをしたりと、日常的に“お金と対話する”習慣を持っています。
また、長期的な視点で人生設計を立てており、「いつまでにどれだけ貯めたいか」「リタイアまでにどんな資産を築きたいか」といった明確なビジョンを描いています。
こうした人たちは、「貯金」だけでなく「投資」や「保険」「税制優遇制度(例:NISAやiDeCo)」もバランスよく活用し、守りと攻めの両面から資産運用を行っています。
貯金だけで安心できる時代は終わった?
投資や資産運用に踏み出す人の共通点
結論から言えば、「貯金だけでは資産を守れない時代」において、すでに一歩踏み出している人たちには共通点があります。
| 投資を始めた人に多い特徴 | 内容 |
|---|---|
| 情報感度が高い | 経済や制度の変化に関心を持っている |
| 小さな額でも実践している | 月1万円程度からでも投資をスタート |
| 長期視点で考えている | 短期的な値動きに一喜一憂しない |
| リスクを学んで理解している | 損失の可能性を受け入れた上で管理できている |
こうした人々は、“増やす・守る・備える”の視点で資産を捉えており、単なる貯金ではカバーできない将来リスクに対応する力を育てています。
たとえばインフレ局面では、100万円の価値が数年で実質90万円以下になることもあり、「貯めるだけでは価値が目減りするリスク」を意識しているのです。
お金が貯まる人がしている投資の考え方
資産を築いている人たちは、単に投資をしているのではなく、“戦略的に投資を使っている”という点がポイントです。
以下は、ある年収500万円の30代会社員が実践している、現実的な資産配分の例です。
具体例:年収500万円・投資ビギナーの資産配分イメージ
| 資産区分 | 内容 | 割合目安 |
|---|---|---|
| 現金 | 生活費6ヶ月分(緊急用) | 20% |
| 積立NISA | 米国株・全世界株のインデックス | 30% |
| iDeCo | 債券・リート中心の運用 | 20% |
| 定期預金 | 学費・短期目標のための預金 | 20% |
| 自己投資 | 資格・スキル習得など | 10% |
このように、目的に応じて資金の役割を明確にし、「攻め」と「守り」のバランスをとっていることが特徴です。
また、毎月の積立額を先に設定し、“余ったら貯める”ではなく“最初に分ける”スタイルを徹底しています。
貯金よりも投資を選ぶ理由と背景
貯金だけに頼っていた時代は、金利が高く、預けておくだけでお金が増えたことが背景にあります。
ですが今は、都市銀行の普通預金金利は年0.001%前後(100万円預けても1年で10円程度)という超低金利時代。
一方、S&P500などのインデックス投資では、過去20年で平均年利7%前後という実績もあり、長期で見れば投資のほうが“資産を守る”手段として機能しています。
金利比較表
| 手段 | 年利 | 100万円を10年預けた場合の差 |
|---|---|---|
| 銀行預金 | 0.001% | 約100円 |
| 定期預金(優遇) | 0.1% | 約1,000円 |
| 投資信託(平均) | 5% | 約1,630,000円 |
上記の通り、同じ金額でも「置き場所」を変えるだけで10年後の差は歴然です。
もちろん、投資にはリスクもありますが、“知識と準備”があればリスクは管理できる時代です。
リタイアを見据えた資産形成の進め方
将来を見据えるなら、ただ「老後が不安」と感じるだけでなく、“いつまでにいくら必要か”という明確な目標設定が不可欠です。
金融庁のレポートによると、平均的な夫婦がリタイア後30年間を過ごすには約2,000万円の資産が不足すると言われています。
リタイア資産シミュレーション(ざっくりモデル)
-
毎月の生活費:25万円
-
年金見込み額(夫婦):18万円
-
毎月の不足額:7万円
-
不足額×12ヶ月×30年=約2,520万円
この差額を埋めるには、今のうちから月1〜3万円程度でも投資を積み上げていくことが鍵になります。
iDeCoや積立NISAなど、税制優遇のある制度を活用することで、少ないリスクで長期的な資産形成が可能になります。
正直みんな貯金どれくらいある?年代別比較
「みんなはどれくらい貯金してるの?」という疑問は、誰しも一度は持つものです。
以下は金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2023年)」をもとにした、年代別の平均貯蓄額の目安です。
| 年代 | 平均貯蓄額(2人以上世帯) | 貯金ゼロ世帯の割合 |
|---|---|---|
| 20代 | 約180万円 | 約38% |
| 30代 | 約440万円 | 約31% |
| 40代 | 約620万円 | 約29% |
| 50代 | 約1,050万円 | 約26% |
| 60代 | 約1,690万円 | 約19% |
※中央値は上記よりも大きく下がるため、「平均より少ないからダメ」とは限りません。
このデータから読み取れるのは、「実は多くの人が思ったほど貯められていない」ことです。特に20〜40代では、3人に1人以上が貯金ゼロという実態もあります。
重要なのは、「周りがどうか」ではなく、「自分が何のために、いつまでにいくら必要なのか」を逆算して目標設定することです。
手取り20万円台で実現できる貯蓄と投資のバランス
「手取りが少ないから投資も貯金も無理」と諦めていませんか?
実際には、手取り20万〜25万円でも、固定費の見直しと家計管理の工夫で十分に資産形成は可能です。
例:手取り22万円・一人暮らしの理想的な家計配分(目安)
| 項目 | 月額目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 家賃 | 60,000円 | 手取りの30%以内に抑える |
| 食費・日用品 | 40,000円 | 自炊中心にすれば余裕あり |
| 光熱・通信費 | 15,000円 | 格安SIMや電気の見直しを検討 |
| 保険 | 5,000円 | 不要な保険を見直して節約 |
| 貯金・投資 | 40,000円 | うち20,000円を積立NISAなどで投資 |
| 趣味・交際費 | 30,000円 | 無理なく楽しむ範囲で調整 |
| 予備費 | 10,000円 | 想定外の支出に備える |
このように、月4万円を将来のために回せば、年間48万円、5年で約240万円に。
少額でも“先取り貯蓄・積立”の仕組みを作ることで、確実に資産は積み上がります。
1年で100万円貯めるにはどうする?現実的な計画
1年で100万円を貯めるには、月平均8.3万円(週2万円程度)の貯蓄が必要です。
「そんなの無理!」と思うかもしれませんが、次のようにステップを組み立てることで現実味が増します。
100万円貯金ロードマップ(1年プラン)
-
毎月の貯金目標を明確にする
固定で5万円、変動で3万円(節約 or 副収入) -
先取り自動貯金を設定
給与振込口座から定期的に別口座へ移す仕組みを作る -
家計の無駄を3つ削減する
例:サブスク、外食頻度、コンビニ立ち寄り -
副業・ポイント活動で+月1万円を狙う
フリマアプリ出品、クラウドワークス、ポイ活など -
ボーナスは使わずそのまま貯蓄へ
ボーナス20万円×2回で合計40万円=年間目標の4割達成
これらを組み合わせることで、「手取り25万円以下でも100万円貯金」は十分に達成可能です。
重要なのは、“仕組み”と“継続性”を作ること。
我慢よりも、工夫と習慣の積み重ねが成功の鍵になります。
「貯金ゼロ」は実は珍しくない?データで見る実態
「自分だけ貯金がない」と感じて不安になる方は多いですが、実は貯金ゼロの人は決して少数派ではありません。
以下のデータをご覧ください。
日本人の貯金額(金融広報中央委員会2023)
| 世帯種別 | 貯金ゼロ世帯の割合 |
|---|---|
| 単身世帯 | 約39.6% |
| 2人以上世帯 | 約28.9% |
| 30代以下 | 約40%以上 |
| 全体平均(全年代) | 約30% |
つまり、3人に1人は実質的に“無貯金状態”なのです。
この背景には、低金利・物価高・賃金の停滞といった構造的な問題があり、「貯金できない自分が悪い」と思いすぎる必要はありません。
むしろ、重要なのはこの状況を受け入れつつ、今から小さくても積み上げる“行動力”を持てるかどうかです。
一歩踏み出せば、半年後、1年後に「お金が残る習慣」が自分の中に根付き始めます。
今のゼロは、“未来のスタートライン”に過ぎません。
参考:金融広報中央委員会
よくある質問Q&A10選
Q1. お金に困らない人ってどんな生活をしているの?

A. 毎月の支出を把握し、必要以上に見栄を張らず、支出に優先順位をつけています。
Q2. 貯金と投資、どっちが大事?

A. 両方必要です。生活防衛資金(貯金)を確保したうえで、余剰資金を投資に回すのが基本です。
Q3. 投資っていくらから始められますか?

A. 積立NISAなら月1,000円からでもOK。少額から無理なくスタートできます。
Q4. 生活費はいくらあれば安心?

A. 目安は「生活費の3〜6ヶ月分」を現金で用意しておくことです。
Q5. 手取り20万円でも貯金できますか?

A. 固定費を見直せば、月2〜4万円の貯金は十分に可能です。
Q6. お金に強い人の習慣って何ですか?

A. 毎月の収支管理・目標設定・金融知識のアップデートが習慣化されています。
Q7. 貯金が100万円あると安心ですか?

A. 一歩目としては理想的ですが、リタイアや大病への備えにはまだ不十分です。
Q8. 老後に必要なお金ってどのくらい?

A. 公的年金以外に2,000万円程度の備えがあると安心とされています。
Q9. お金が貯まらない人の最大の原因は?

A. 支出を把握せず、感覚でお金を使っていることが主因です。
Q10. 貯金ゼロからでも資産形成は可能ですか?

A. 可能です。重要なのは、金額ではなく“習慣と仕組み”をつくることです。
お金に困ってない人の特徴は?貯金より投資!?のまとめ
最後にこの記事のポイントをまとめました。
【あわせて読みたい関連記事】
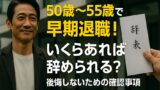

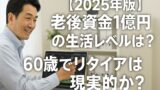
【本記事の関連ハッシュタグ】





